*紹介している教材にはプロモーションを含みます
大学受験で志望校合格に向けて重要になるのが世界史です。
そんな世界史ですが、範囲が広く「勉強の仕方がわからない」「成績が上がらなくて困っている」「どの参考書を使えば良いか迷う」そのような悩みを持っている人も多いのではないでしょうか。
この記事は、世界史学習でつまずいているあなたのために、世界史の勉強法を徹底的に解説します。この記事を読めば、志望校合格に必要な勉強内容、参考書、学習時間が明確になるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
なお、世界史の勉強法については以下の動画で詳しく解説しているので、あわせてチェックしてください。
世界史の勉強法の3ステップ
世界史の勉強は、大きく3つのステップに分けて考えるのがポイントです。
- 通史学習:歴史の流れを理解する
- 単語暗記:重要語句や人物名を確実に覚える
- 問題演習:志望校の出題形式にあわせて対策する
以下でそれぞれのステップを詳しく解説します。
ステップ1:通史学習で時代の流れを押さえる
まずは歴史の流れを把握する「通史」を行います。
最初に歴史の流れを把握する理由は「入試で流れを理解していないと正答できない問題が出題される」「流れを理解していた方が単語を覚えやすい」の2つです。
世界史のテストは、単語の暗記勝負ではありません。実際の入試では、以下のような形式で問題が出題されます。
- 「以下の出来事a~eを発生した順番にならべなさい」
- 「〜という過程を論述しなさい」
上記のように、時系列を問う問題が出題されるのです。
出来事の順番を並び替える問題は、歴史の流れを知らないと解けません。
また、記述問題では、出来事同士の関係やつながり、背景などに採点基準が置かれているケースが多いため、単語を羅列するだけではほとんど点数がもらえません。
しかし、時代の流れさえ理解していれば、具体的な年号を覚えていなくても正解できる可能性を高められるでしょう。
また、歴史の流れを把握すると、暗記するための「骨組み」が完成します。
そこに「単語」を覚えて「肉付け」していくと、世界史の全体像が理解しやすいです。
ざっくりと歴史の流れを押さえたら、次のステップに移行しましょう。
世界史の通史については、以下の記事で解説しています。
ステップ2:単語を暗記する
歴史の流れを大まかに把握したら、次は単語暗記に進みます。通史を終えたら、一気に単語の暗記を進めていきましょう。
当塾がおすすめする単語暗記方法は、最初は「穴埋め形式の問題集」で用語を覚え、完璧になったら「問題演習」と並行して一問一答に取り組むという方法です。
- STEP.1 『詳説世界史ノート』などの穴埋め問題集で、流れの中で単語を覚える
- STEP.2 問題演習をしながら『山川一問一答世界史』などで単語暗記の仕上げに取り組む
この流れを意識して学習を進めてみましょう。
「穴埋め形式」の問題集を使用すれば、歴史の流れが文章で記述されており、重要な箇所が空欄になっているため、歴史の流れを復習しながら単語を暗記できます。
一問一答は、私大レベルの単語を効率的に覚えたり、試験前に知識を整理したりするうえで非常に役立つ参考書です。流れの中で穴埋めができるようになったら、次のステップ3に進み、問題演習と並行して一問一答に取り組みましょう。
ここまでに紹介した勉強法と、これから紹介する参考書を活用すれば、用語の理解と暗記は十分に可能です。
しかし、学習を進めるなかで「この単語の意味って何だろう?」「教科書の説明だけでは理解できない…」といった疑問が生じることもあるでしょう。そのような場合は、用語集や資料集を活用してください。
用語集は、世界史の用語の意味を調べるのに非常に便利です。また、資料集には、年表や写真などが掲載されているため、歴史の流れを理解したり、記憶を定着させたりするのに役立ちます。
「教科書の文字だけではイメージがわかない…」と感じる人は、ぜひ資料集を活用してみてみましょう。より詳しい情報については、以下の記事をご覧ください。
世界史の単語については、以下の記事で解説しています。
ステップ3:問題演習で総仕上げ
歴史の流れを把握し、穴埋め形式で基本的な単語を覚えたら、いよいよ実践的な問題演習に取り組みましょう。一問一答で単語の知識を定着させながら、志望校の出題傾向に合わせた対策を進めていきます。
志望校によって、出題される問題の種類は大きく異なります。「選択式の問題」「単語を記述する問題」「論述問題」など、さまざまな形式の問題が出題されるため、志望校の傾向を分析し、必要な分野の演習を重点的に行うことが重要です。
大学入試の世界史の問題は、大きく「記号・単語問題」と「論述問題」の2つに分類できます。共通テストや多くの私立大学では「記号・単語問題」が中心に出題され、国公立大学では「論述問題」が重視される傾向があります。志望校の出題形式に合わせて、適切な参考書を選択しましょう。
- 多くの私立大学・共通テスト:記号・単語のみの出題
- 国立大学・上智大・学習院大・明治大などの一部の私立大学:論述問題も出題
「記号・単語問題」は、単語の暗記はもちろんのこと、歴史の流れを理解していなければ解答できない問題も多く含まれています。さまざまな問題を解くことで、問題形式に慣れながら、歴史の流れを再確認することが重要です。
一方、「論述問題」では、「Aという単語について3行程度で説明しなさい」といった基本的な問題から、〇世紀から×世紀までのBという地域の政治体制の移り変わりを300字以内で説明せよ」といった高度な思考力を必要とする問題まで、さまざまなタイプの問題が出題されます。
大学によって出題傾向が異なるため、早めに志望校の過去問を確認し、対策を練りましょう。
論述問題は、与えられた情報をもとに、自分で解答を構成する必要があります。具体的には「問われている時代や地域を特定する」「解答に必要な要素を洗い出す」「要素を関連付けて文章を構成する」という手順で解答を作成します。
単に知識を羅列するだけでは、高得点を獲得できません。論理的な思考力と文章構成力も求められることを意識しましょう。

世界史の勉強におすすめの参考書と活用法
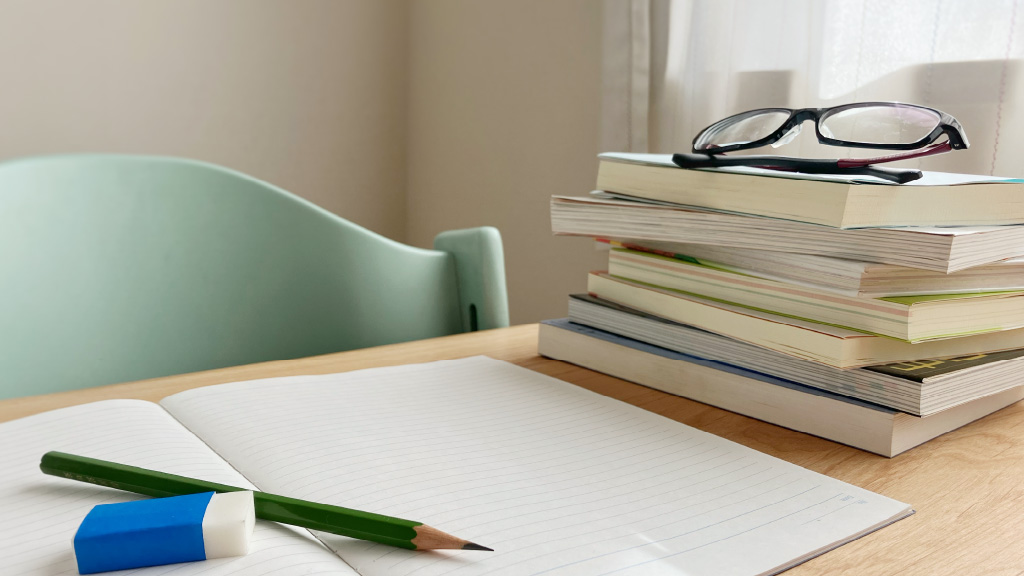
効果的な勉強法を理解したところで、次に「通史理解」「単語暗記」「問題演習」の3ステップで活用すべきおすすめの参考書を紹介します。
歴史の流れを掴む!通史学習におすすめの参考書
まずは、歴史の流れを理解するための通史学習におすすめの参考書を紹介します。
通史を学習するうえで大切なのは、最初から完璧を目指さないことです。
初めて歴史を学ぶ際は、分からない単語が多くて当然です。
すべての単語をその場で覚えようとすると、時間がかかりすぎてしまい、学習が進まなくなる可能性があります。
単語や歴史の流れを「覚える」ことは後回しにして、まずは歴史の流れを「ひととおり理解する」ことを優先しましょう。
通史のおすすめ参考書1:中高6年間の世界史が10時間でざっと学べる
『中高6年間の世界史が10時間でざっと学べる』は、中学校と高校で学習する世界史全体を、短時間で理解できるように構成されています。
説明が分かりやすく、世界史が苦手な方でも取り組みやすいでしょう。
具体的な使い方は以下のとおりです。
- STEP.1 各項目を読みながら、地図にも目を通す
- STEP.2 読んでも理解できなかった部分があれば、教科書や参考書で確認する
- STEP.3 各章でStep1とStep2を繰り返す
この参考書は、短時間で世界史の全体像を把握することを目的としているため、分からない部分に時間をかけすぎず、どんどん先に進むことを意識しましょう。
通史のおすすめ参考書2:ナビゲーター世界史
「ナビゲーター世界史」は歴史上の出来事の因果関係や流れをストーリーにして把握できるように構成された参考書です。
当塾では、映像教材「TryIT」との併用をおすすめしています。世界史の通史は、まず全体を把握することが重要です。そのため、ペース配分がしやすい映像授業を利用するとより効果的に学習を進められるでしょう。
「TryIT」は、無料で視聴できる映像授業なので、いつでも、何度でも見返せるのが大きなメリットです。
学校の授業だけでは、世界史の通史を十分に理解できないと感じる場合は、「TryIT」を活用して、積極的に学習を進めていきましょう。具体的な使い方は次のとおりです。
- Step.1 教科書や資料集、または『ナビゲーター世界史』などの参考書を用意し、該当箇所を開く
- Step.2 TryITの動画を視聴する<
- Step.3 教科書や参考書に、動画の中で解説された重要なポイントを書き込む
- Step.4 確認テストに挑戦する
動画は何度でも繰り返し視聴できるため、板書を書き写すことに時間を費やさず、授業の内容に集中するようにしましょう。
効率的な暗記をサポート!単語暗記におすすめの参考書
続いて、世界史の単語暗記におすすめの参考書をご紹介します。
単語暗記のポイントは「単語だけでなく、その周辺の知識も一緒に覚えること」と「単語を見てすぐに意味が答えられるようになるまで、繰り返し学習すること」です。
先にも述べたように、歴史の単語は流れの中で理解することが重要です。
単に単語を丸暗記するのではなく、その単語がどのような出来事と関連しているのかなど、周辺知識も合わせて覚えるようにしましょう。
また、問題を見たときに、すぐに単語の意味を答えられない場合は、記憶に定着しているとはいえません。試験本番でスムーズに解答するためには、日ごろから単語を暗記するだけでなく、知識をアウトプットする練習も行うようにしましょう。
単語暗記のおすすめ参考書1:山川詳説世界史ノート
『詳説世界史ノート』は、教科書に準拠した穴埋め形式の問題集です。
教科書に掲載されている内容を、歴史の流れに沿って、分かりやすくまとめられているので、安心して学習を開始できます。
重要な単語が空欄になっているため、歴史の流れを確認しながら、効果的に単語を暗記可能です。
一問一答形式の問題集に取り組む前に、まずはこの参考書で歴史の流れを復習することをおすすめします。使い方はシンプルで、文章を読みながら、空欄に適切な単語を書き込んでいくだけです。
- Step.1 文章中の( )に入る単語を、別のノートに書き出してテストする
- Step.2 空欄を半分以上埋められない場合は、教科書を見ながら空欄を埋める
- Step.3 答え合わせをして、間違えた単語の( )に印を付ける
- Step.4 間違えた単語の周辺にある文章を3回読み、単語と関連付けて覚える
- Step.5 1つの単元が終わるまでStep1〜Step4を繰り返す
詳しい活用方法は以下の記事で紹介しています。
単語暗記のおすすめ参考書2:山川一問一答世界史
『山川 一問一答世界史』は、教科書を発行している山川出版社の一問一答形式の問題集です。教科書に掲載されている歴史の単語を、一問一答形式で確認できます。
本書では、単語の重要度が3段階で表示されているため、志望校のレベルに合わせて、効率的に学習を進められます。使い方はシンプルなので、とにかく何度も繰り返し問題を解いていきましょう。
- Step.1 単語を隠して覚えているのかテストする
- Step.2 覚えていなかった単語に印をつけ、もう一度覚え直す
- Step.3 全ての問題をもう一度解き直す
- Step.4 全ての単語を覚えるまで、間違えた単語のみ、Step1〜Step3を繰り返す
1回目は、穴埋めノートと同様に、実際に単語を書いて確認してください。テストでの解答を意識し、漢字で正確に書けるように練習しておきましょう。
山川の『一問一答』は、単語の重要度に応じて、星の数が割り振られています。星2つは基本的な単語、星1つは標準的な単語、星なしは難易度の高い単語を示しています。
どの大学を受験するとしても、まずは星が付いている単語から優先的に覚えるようにしましょう。
志望校合格へ一直線!問題演習におすすめの参考書・問題集
単語の暗記が完了したら、いよいよ志望校の出題形式に合わせた問題演習に取り組みます。ここでは「記号問題対策」と「論述問題対策」それぞれにおすすめの参考書を1冊ずつご紹介します。志望校の出題傾向に合わせて、適切な参考書を選び、対策を進めてください。
記号問題演習のおすすめ参考書:実力をつける世界史100題
『実力をつける世界史100題』は、実際の入試問題を中心に構成された、実践形式の問題集です。解説が非常に詳しく、関連する重要用語や因果関係などを整理してくれるため、知識の定着に役立ちます。
「実際の問題を解いて知識の定着度を確認したい」「私立大学の過去問では点数が伸びない」という受験生におすすめです。
この参考書は、解説が非常に詳しいのが特徴です。問題を解き終えたら、必ず解説を丁寧に読み込むようにしましょう。
正解した問題についても、「たまたま正解した」という可能性もありますし、知らなかった単語や知識が解説されている可能性もあるため、必ず解説を確認するようにしてください。
- Step.1 問題を解く
- Step.2 間違えた問題に印をつける
- Step.3 正解した問題も含めて、解説をすべて読む
- Step.4 解説を読んで知らなかった単語や知識は覚え直し、該当箇所の教科書や資料集も確認する
この参考書の詳しい使い方については、以下の記事をご覧ください。
『実力をつける世界史100題』は世界史の問題演習にオススメ!正しい使い方や注意点なども解説
論述問題演習のおすすめ参考書:段階式世界史論述のトレーニング
『段階式 世界史論述のトレーニング』は、実際の入試問題を中心に構成された論述形式の問題集です。解答の文字数によって問題が段階分けされているため、志望校で出題される文字数に合わせて、集中的に対策を行えます。
また、段階的に文字数を増やしていくことで、論述力を効果的に高めることも可能です。
- Step.1 記述問題を解く
- Step.2 解説を読んで、記述に盛り込むべきポイントを確認する
- Step.3 解説の内容を踏まえて、もう一度論述問題に挑戦する
この参考書の詳しい使い方については、以下の記事をご覧ください。
また、論述問題は、教科書の記述なども参考になります。教科書も併せて確認することを忘れないようにしましょう。

世界史単語のNGな勉強方法

世界史の単語学習は、大学受験や資格試験において避けて通れない道です。しかし、闇雲やみくもに勉強しても効率が悪く、成果につながらないケースがあります。ここでは、多くの人が失敗しやすい、世界史単語学習におけるNGな勉強方法を3つ紹介します。
NG勉強法1:ノートに書き写すだけ
ノートに単語をひたすら書き写すだけの学習は、実は非常に非効率な方法といえます。
なぜなら、目的が「暗記すること」から「書き写すこと」に変わってしまい、記憶に定着しにくいからです。
時代背景や因果関係を含めて効率的に学習を進めましょう。
NG勉強法2:文字情報のみで学習する
教科書や参考書の文字情報だけをひたすら読み込む学習方法も、効率的な学習とはいえません。
なぜなら、人間の脳は、文字情報だけでなく、図やイラスト、写真などの視覚的な情報と組み合わせて記憶する方が、より効率的に情報を処理できるからです。
また、視覚的な情報は、記憶の想起を助けるトリガーとしても機能します。
例えば、年表や地図、人物の肖像画などを見ながら学習することで、単語と関連する情報を視覚的に結び付け、より効率的に記憶に定着させられるのです。
NG勉強法3:インプットに偏っている
単語を覚えることだけに集中し、アウトプットの機会を設けない学習は、知識を定着させるうえで非常に非効率です。
なぜなら、人間の脳は、インプットした情報をアウトプットすることで、初めて長期記憶として定着させるからです。
アウトプットとは、単語の意味を説明したり、例文を作ったり、問題を解いたり、人に教えたりする行為のことです。アウトプットすることで、自分が理解できていない部分を明確にし、より知識が定着しやすくなります。
世界史の勉強法に関するよくある質問

ここからは、世界史の勉強法に関して、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1:世界史の勉強はいつからやればいいのですか?
個別試験で世界史を利用する場合、高校3年生の夏休み前には、全範囲の学習を終えている状態を目指しましょう。そのためには、高校2年生の冬頃から少しずつ予習を始めるのが理想的です。
まずは、学校の定期テストで高得点を獲得できるように、授業内容をしっかりと理解するようにしてください。
もちろん、時間に余裕がある場合は、早い時期から学習を始めても構いません。
ただし、英語や数学、国語などの主要科目の基礎ができていない段階で、世界史の学習に時間を割きすぎるのはNGです。
世界史に比べて、英語や数学などの科目は、暗記だけでは対応できない問題も多く出題されるため、早期から計画的に学習を進める必要があります。
多くの大学では、世界史よりも英語や数学の配点が高く、合否に大きく影響するため、まずは主要科目の基礎固めを優先し、余裕があれば世界史の予習に取り組むようにしましょう。
【志望校別具体的な学習開始時期】
- 最難関大学(旧帝大・早慶クラス):高2夏から開始し、高3のGWには通史を完了
- その他個別試験で使用する場合:高2冬から開始し、高3夏休み前に通史を完了
- 共通テスト対策:高3夏休みから開始し、10月頃に通史を完了/li>
上記の目安を参考に、計画的に学習を進めてください。
Q2:世界史の文化史は勉強しないんですか?
結論から申し上げると、私立大学では、文化史の問題が出題されることが多いため対策は必須です。
具体的な学習方法としては、まず政治史や経済史をしっかりと学習します。そのうえで、文化史の用語集や参考書を使って知識を整理していくと良いでしょう。また、資料集を活用して、写真やイラストを見ながら学習すると、より記憶に残りやすくなります。
そして、文化史学習の最大のポイントは「試験直前に勉強すること」です。文化史は覚えるポイントがとにかく多いので、完璧にしようとすると時間が足りなくなってしまいます。
直前期に問題集を繰り返して覚えつつ、資料集で実物の写真やイラストも合わせて確認するようにするといいでしょう。
さいごに
世界史は「通史→単語暗記→問題演習」の順番に取り組みましょう。
世界史の学習は、何よりもまず「通史を理解する」ところから始まります。
学校の授業だけでは、入試対策が間に合わない場合もあるため、他の科目とのバランスを考慮しながら、高校2年生のうちに予習を始めるようにしましょう。
世界史は、直前まで点数を伸ばせる科目です。この記事で紹介した勉強法を参考に、計画的に学習を進め、世界史を得意科目にしてください。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。
















