*紹介している教材にはプロモーションを含みます
日本史の論述問題は、知識だけで解けるわけではないので、対策がしにくいですよね。
解けるようになるためには、学んだ知識をもとに文章を作れるようになっておく必要があります。
暗記するだけでは解けないので、日本史が苦手な人だけでなく得意な人でも、苦戦する人が多いのです。
しかし、苦手な人が多い分、日本史の論述問題を対策しておくと、入試でほかの受験生に差をつけやすくなります。
本記事では、日本史の論述問題の勉強法やおすすめの参考書を紹介します。

日本史論述の勉強法①|論述の重要性を知る
日本史の論述は、暗記しただけでは解けないため、時間をかけて論述対策をした人とそうでない人とでは、大きな差がつきます。
もちろん、記号の選択問題や用語の担当問題を、解けるように勉強をするのも重要です。しかし、そのような問題は、日本史の重要事項を暗記しておけば得点しやすいため、正解しても他の人との差はつきにくいのです。
日本史の重要事項を暗記した上で、論述の対策を行うことが、成績上位層のなかで差をつけることにつながります。
日本史論述の勉強法②|問題の形式を理解する
問題の形式は、「説明せよ」「変化を述べよ」「違いを述べよ」というような、問題の問い方で判断できます。
これらの形式を判断し、問われていることにだけ答えられることが、日本史論述を解くうえで重要です。
問われていることに正確に答えることができない受験生は多くいます。東大を志望している人でさえ、練習しなければできない人は割と多いんです。
従って、問題で問われていることにきちんと答えられているだけで、多くの受験生に差をつけられます。
ここから、よくある問題の形式ごとに、解法を説明していきます。
「説明せよ」の解法
「寛政の改革について説明せよ。」という問題を例にあげて説明します。
この場合、制限された文字数で、さまざまな面から政策を説明する必要があります。
たとえば、寛政の改革の農村政策だけしか説明できていないと、解答としては不十分です。
農村や都市、思想などのさまざまな面に視野を広げて説明をしなければなりません。
字数が多い問題の場合、改革が与えた影響まで説明するとよいでしょう。
「変化を述べよ」の解法
「江戸時代後期の農村政策の変化について述べよ。」という問題を例にあげて説明します。
この場合、何の政策や事件がきっかけで、何がどのように変化したかの説明が必要です。
その際、政策や事件の「前」と「後」を説明しないと、変化が分からないので、論述としては不完全なものとなります。
「違いを述べよ」の解法
「寛政の改革と天保の改革の違いについて述べよ。」という問題を例にあげます。
この問題で、ただ寛政の改革と天保の改革の2つの政策を説明するだけでは、解答として不十分です。
正答するには、比較する項目ごとに、違いを説明する必要があります。
比較する項目としては、「農村政策」や「改革の結果」などをピックアップして解答してください。
共通点を述べると字数が足りなくなります。聞かれているのは、「違い」なので、余分な記述はなるべく控えましょう。

日本史論述の勉強法③|文章を構成できる力をつける
論述の問題を解くには、意味の通った文章を書く必要があります。決して文章をうまく書く必要はなく、説明ができていれば正解となる文章をつくれます。
文章を構成できるようになるための、具体的な対策法は、以下の3点です。
- 主語と述語を対応させる
- 100字以上となるような長い1文を書かない
- 「比較する項目を対応させる」「時代の順番通りに説明する」ことなどにも気をつけて読みやすい文章を書く
上の内容に注意しながら、文章を組み立てる練習を行いましょう。本番での見直しの際にも、上の内容を意識することが大事です。
日本史論述の勉強法④|効率的な演習の仕方で勉強する
日本史論述の解き方を学ぶ段階では、効率的な演習をするために、以下の3点を取り入れて演習してください。
- 教科書などで調べながら解く
- 問題を解く時間は計らない
- 復習はしっかりと行う
それぞれの内容について詳しく説明します。
教科書などで調べながら解く
入試本番を想定した勉強をするとき以外は、教科書や資料集で調べながら、納得のいく解答を書く練習をしてください。
知識がないまま解いていては、「日本史論述の勉強法②」で述べたような、問われていることにだけ答える力は身につきません。
教科書で正しい内容を調べて、その内容を解答に反映できるように書く練習をすることが大事です。
また、調べながら解くと、教科書に載っている表現の記憶ができます。
教科書は、日本史の重要事項を端的に分かりやすく記載してあり、論述を書く上で参考になります。教科書の表現を覚えておくことは、日本史論述の勉強において大変重要です。
問題を解く時間は計らない
日本史の論述を演習しているときには、時間を気にせずに解いても問題ありません。納得のいく解答ができるまで考えることで実力がつきます。
また、時間をかけて完璧だと思った解答でも、添削をすると改善点が見つかります。模範解答と照らし合わせて、理解できていない部分を明らかにすることが可能です。
復習はしっかりと行う
一度解いただけでは、日本史の論述を解く力はつきにくいため、復習は大変重要です。
再度問題を解くことで、間違えやすい内容や自分にとって重要な項目などに気がつきます。
模範解答を閉じて、模範解答を再現できるかチェックする癖をつけるといいですね。
特に、問題の形式を捉え間違えていたものは、時間を空けて何度か復習して苦手な分野がないようにしましょう。
日本史論述の勉強法⑤|添削は必要
自分が書いた文章の添削は、論述の実力を伸ばすために必ず行ってください。
添削は、「先生に頼んでやってもらう」「自分で添削をする」の2種類の方法で行う必要があります。
先生に添削してもらうことで、自分の分かっていないポイントが見つかります。面倒くさがらずに先生にお願いして添削してもらいましょう。
また、自分で添削をすることで、入試本番で解答を見直す力が身につきます。
入試本番で、自分で解答をチェックできるように、添削できるようにしてください。
自分で添削をするときには、以下の4つのポイントを抑えて行いましょう。
- 問題の形式に正しく答えているか
- 歴史的に間違った内容がないか
- 誤字脱字がないか
- 文字数の制限などのルールを守って解答できているか
日本史論述の勉強法⑥|対策を始める時期を検討する
日本史論述の対策を始めるのは、高校3年生になったタイミングがベストです。
論述の力が十分につくまでには、少なくとも数か月は勉強をする必要があります。入試直前まで点数が上がらず、焦ることがないように対策を始めましょう。
また、論述の勉強を本格的に始める前でも、以下の2点に注意して日本史の勉強に取り組むと論述対策につながります。
- 教科書の内容を意識して覚える
- 共通項や違いを押さえる
日本史の勉強において、教科書を読むことは大変重要です。
教科書の表現を覚えると、論述を解くのに役立ちます。テスト前はもちろん、ふだんの予習復習時にも教科書を読むことを中心とした勉強をするようにしましょう。
その際、単語を記憶するだけでなく、文章の意味まで押さえる必要があります。
また、日本史である時代の勉強をしていると、ほかの時代にも出てきた内容に気づくことがあります。それらの内容における、共通項や違いは重要なので、比較しながら覚えていきましょう。
比較することは、論述で聞かれることが多いので、解答の際に役立ちます。
日本史論述の勉強法⑦|赤本に載っている過去問はすべて解く
赤本に載っている過去問をすべて解くことで、志望校で出題されやすい形式やテーマが分かります。
過去問は、どのような問題が出やすいのかを意識して解きましょう。
最低でも志望校の赤本に載っている分はすべて解き、可能であれば、過去の赤本も中古で入手して練習するのがおすすめです。
また、志望校以外の大学入試問題を解くのも、論述の力をつけることにつながります。
ただし、あくまで志望校の過去問の勉強が最優先です。
志望校以外の大学入試問題ばかりを勉強しすぎないようにしてください。

日本史論述のおすすめ参考書2選
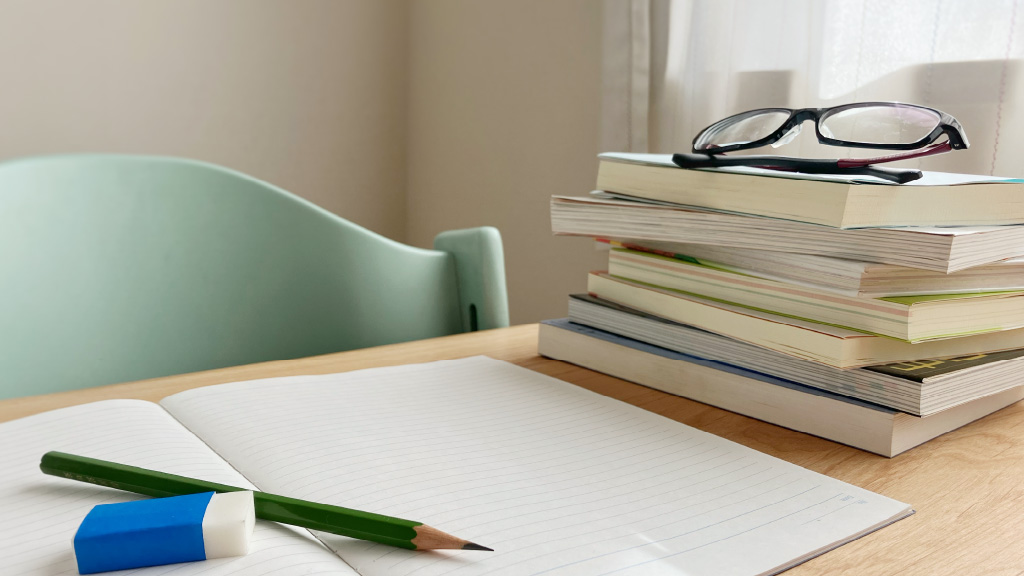
日本史論述の勉強をするのに、おすすめの参考書を2つ紹介します。
さまざまなレベルの問題に対応|段階式日本史論述トレーニング
さまざまなレベルの問題を掲載しているため、多くの受験生におすすめです。
論述の長さも、短いものから長いものまで、さまざまな論述問題を掲載しています。解いていくうちに、段階的にレベルが上がるようにつくられているため、すべて解き終わるころには、高いレベルの問題を解くことが可能です。
本記事の、日本史論述の勉強法②で述べた「問題の形式」についても詳しく解説してあります。
東大を受験する人におすすめ|東大日本史問題演習
東大を受験する人は、ぜひこの参考書を選んでください。
問題が東大の入試傾向を抑えてつくられています。
とにかく解説が詳しいのも特徴です。
日本史論述を解くためのポイント
本記事で紹介した日本史論述を解くために重要な勉強法は、以下の3つです。
- 問題の形式を考えながら解くこと
- 論述の解答は自分でも添削をすること
- 教科書の内容をひたすら読むこと
「説明せよ」「変化を述べよ」「違いを述べよ」といった問い方から、問題の形式を理解するのは重要です。何を聞かれているのかを理解し、聞かれたことにだけ答える練習をしておく必要があります。
また、問題を解いた後は、自分で添削をできるようにしておくと、入試本番で見直しをするときに役立ちます。
そして、日本史は教科書の内容が大変重要な教科です。教科書の単語だけを覚えるのではなく、表現を覚えるようにしてください。教科書は、論述を解くときには使いやすい表現が多く載っています。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。














