*紹介している教材にはプロモーションを含みます
国公立大学や難関私立大学の入試において、受験生を最も苦しめる教科の一つに世界史の論述問題が挙げられます。
世界史の論述問題について「用語を暗記するだけでも大変なのに、論述まで対策できない」と感じる人も多いでしょう。
しかし、論述問題は配点が高い傾向にあるため、いかに得点できるかが、合否を大きく左右します。この記事では、論述問題で高得点を獲得するために押さえておきたい重要なポイントを解説します。
世界史の論述問題をスムーズに解くための3ステップ
まずは、世界史の論述問題攻略のため手順を3つのステップに分けて解説します。以下の3つのステップを意識して問題を分析することで「何を書けば良いかわからない」「文章構成がバラバラになる」といった悩みを克服できるはずです。
- STEP.1 問われている時代を明確にする
- STEP.2 解答に必要な要素を整理する
- STEP.3 関係性を図で示す
今回は、2016年度の早稲田大学商学部の入試問題を題材に、3つのステップをどのように活用していくかを見ていきましょう。
【題材】アメリカ合衆国と中華人民共和国について、両国の国交正常化にいたる経緯と背景を100字以内で説明しなさい。
この問題だけを見ると、どの時代について、どんな出来事を書けば良いのかが分からず、難しく感じるかもしれません。
こういった場合こそ、3ステップを意識して考えることにより、解答の糸口をつかめるので、以下の解説をしっかりチェックしてください。
STEP1:問われている時代を絞り込む
最初に、解答に含めるべき時代を特定しましょう。論述問題の中には「1800年代後半から1900年代前半まで」のように、具体的な時代が指定されているものもあれば、今回の例題のように、何も指定されていないものもあります。
時代が指定されていない場合には「国名」「問題文の指示」に着目することで、解答の糸口が見つかることがあるので必ずチェックしましょう。
今回の例題では、国名に「中華人民共和国について」とあるため、中華人民共和国が成立した1949年以降の時代について記述する必要があると判断できます。
さらに、問題文には「国交正常化」という条件が付いています。米中の国交正常化は、ベトナム戦争やキューバ危機が終結し、日中国交正常化が進められた時期と重なり、1970年代のニクソン大統領訪中によって実現しました。
したがって、1949年以降におけるこの2ヶ国の関係のなかで、1970年代前半が大きな転換期であったと理解していれば、国名と問題文の条件から時代を絞り込めるはずです。
今回は「経緯と背景」を記述する必要があるため、国交正常化が実現する前の「1950年代から60年代にかけての両国の動きについても触れる必要がある」と解答の方針を導き出せれば正解にぐっと近づきます。
STEP2:解答に必要な要素を整理する
次に、特定した時代の中で、解答に含めるべき要素を洗い出します。このとき、必ず問題文で問われていることだけを洗い出すようにしましょう。
世界史の論述問題の文字数は、答案に記述してほしい要素の数に基づいて決められていることが多いです。大学によって差はありますが、一般的には、20字前後で1つの出来事や要素について記述するように想定されているようです。
したがって、問われていない要素を記述してしまうと「本当に必要な要素を書ききれない」という事態に陥る可能性があります。まず解答に必要となりそうなキーワードをリストアップし、問題文との関連度合いに応じて優先順位をつける練習をしておきましょう。
STEP3:図で示す
最後に、洗い出したキーワードを、歴史の流れに沿って整理します。今回の問題では「経緯と背景」が問われているため、単にキーワードを羅列するだけでは、十分な評価は得られません。
よく利用される図のパターンとしては、以下の2つが挙げられます。
- 時代順に年表形式で整理する
- 2つの国を比較しながら整理する
あとは、この図表に従って文章を作成するだけです。
【解答例】スターリン批判以降、ソ連と対立していた中華人民共和国と、ベトナム戦争の長期化により社会主義国との関係改善を目指すアメリカの思惑が一致し、ニクソン大統領の訪中や、国連代表権の交代などを経て国交正常化へと向かった。(100字)
この3つの攻略ポイントは、文字数が多くなっても応用できる点が強みです。特に、東京大学のような字数の多い論述問題や、難関国公立大学の200〜300字程度の論述問題では、問われる時代が広範囲に及ぶ場合があります。
この場合、国同士の関係性や歴史の流れを整理する必要があるため、図を用いて情報を整理し、その内容を文章化していく作業が非常に重要になります。必ず、文章を書き始める前に、これらの要素をメモとして書き出しておきましょう。

世界史論述の具体的な勉強法

論述問題を安定して解けるようになるためには、以下の2つの能力を習得する必要があります。
- 歴史の流れを整理し、設問の意図を理解する力
- 論理的な文章を作成する力
基本的には「歴史の流れを整理し、設問の意図を理解する力」を養う方が難しいといえるでしょう。いくら文章が上手でも、歴史の流れを理解し、設問の要求に応えられなければ、高得点は獲得できません。
したがって、まずはこちらの能力を重点的に鍛えるようにしましょう。それぞれの内容について、具体的に見ていきましょう。
1.通史を整理し、聞かれたことに答える力
世界史の論述演習は、文章を書かなくても行えます。1つ目の「歴史の流れを整理し、設問の意図を理解する力」を身につけるだけであれば、必ずしも文章を作成する必要はありません。
ここでは、冒頭で説明した論述問題の「3つの攻略ポイント」を意識し、解答のメモや図を作成する練習を繰り返すようにしてください。
図を作成するという訓練を繰り返すことで、論述問題で最も重要な「文章構成」をスムーズに行えるようになり「歴史の流れを整理し、設問の意図を理解する力」を身につけられるのです。
時間がない場合や、試験直前期に過去問を見直す際には、図だけを書き直すという方法でも十分な効果が得られるでしょう。
2.文章を書く力
2つめの「論理的な文章を作成する力」を鍛えるには、メモ書きの内容を、実際に文章に落とし込む練習をするしかありません。指定された文字数のなかで、過不足なく記述できるように練習を繰り返しましょう。
メモ書きを文章化する際には、日本語の文法や漢字の誤りに注意しましょう。また、一文が長くなりすぎないように意識することも大切です。
図にまとめて歴史の流れを正確に理解していても、採点者にその内容が伝わらなければ意味がありません。「書くべきことは理解できているから…」と油断せずに、作成した図の内容がきちんと伝わるかどうかを意識しながら演習に取り組みましょう。
世界史の論述学習の具体的な進め方
今回は、どのような大学の論述問題にも対応できる『段階式世界史論述のトレーニング』を例に、具体的な勉強法を見ていきましょう。
世界史の論述演習は、基本的に次のステップで進めていきます。
- Step.1論述問題をスムーズに解くための3ステップを意識して問題を解く
- Step.2解説を読んで記述に盛り込むべきポイントを押さえる
- Step.3解説の内容を意識してもう一度論述に取り組む
それぞれのステップについて、以下で詳しく解説します。
Step.1論述問題をスムーズに解くための3ステップを意識して問題を解く
問題に取り組む際には、まず「3つのステップ」を思い出し、問題文に書かれている状況に当てはめて考えます。
3つのステップを実行し、図に表せたら、実際に論述を開始してください。できれば、マス目のついたノートや、実際の解答用紙を使って演習を行い、字数を意識するようにしましょう。
Step2解説を読んで記述に盛り込むべきポイントを押さえる
論述を書き終えたら、自己採点してください。論述問題の場合、誰かに添削してもらうのが理想的ですが、毎回添削してもらうのは難しい場合もあるでしょう。
自分で採点するときは、論述で書いた部分ではなく、先に「図」を採点するようにするのがおすすめです。
また、文章だけを解答と見比べても「何が違うのか全くわからない」というケースも多いので、文章を採点するよりも、解説を参考にしながらメモ書きを採点する方が、自己採点が容易になります。具体的には、以下のようなメモ書きを残したとします。
解説に書かれている文章を見ながら、メモ書きと大きく異なっている点がないかを確認します。
- 時代は合っているか?
- 解答に必要なキーワードは含まれているか?
- 歴史の流れは、解説と同じように記述されているか?
これらのポイントを必ず確認するようにしてください。
メモ書きを採点して、解答と大きくズレていなければ、そこで初めて本文の採点に取り組みます。
反対に、メモ書きの段階で大きくズレているようであれば、無理に本文を採点する必要はありません。そして、採点が終わったら、解説を丁寧に読み込み、解答のパターンを把握しましょう。
Step.3解説の内容を意識してもう一度論述に取り組む
解答に含めるべき項目を理解できたら、解説の内容を改めて思い出しながら、その場でもう一度メモ書き・図を作成し、論述に取り組みましょう。
模範解答を隠して、自力で模範解答レベルの解答を作成できれば、その問題はクリアです。
解答や解説を読んだだけで「理解したつもり」になってしまうこともあります。実際に論述できるようになってこそ意味があるので、忘れないうちにもう一度書いてみるようにしてください。

世界史論述のインプットにおすすめの参考書3選
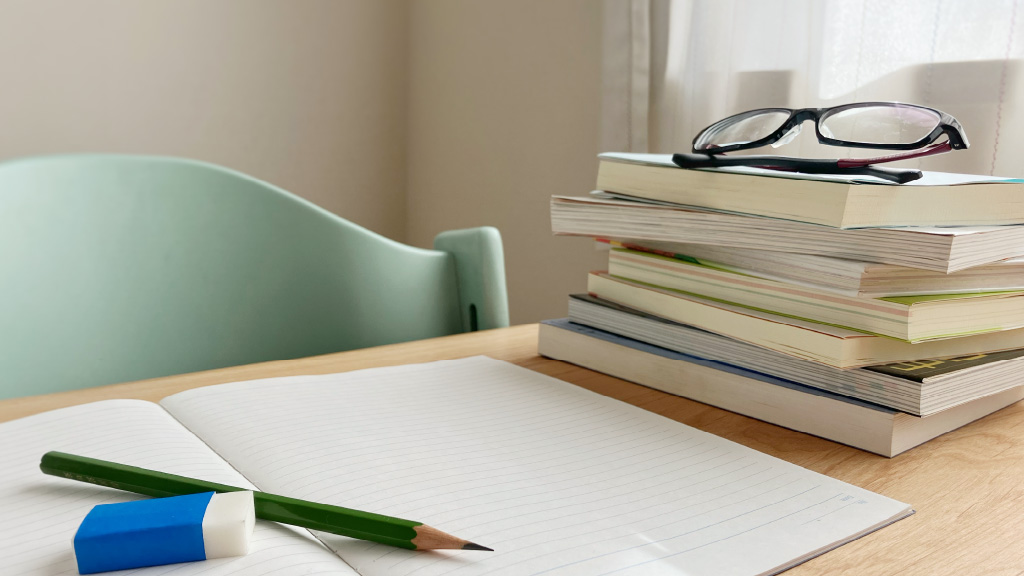
論述問題で安定して得点するには「論述で問われる知識のインプット」「メモ書きや図、文章へのアウトプット」の2つの練習が必要です。
メモ書きを作成するために必要な知識をインプットする段階と、インプットした知識をメモ書きや文章に落とし込み、得点につなげるアウトプットの段階では、それぞれ適した教材が異なります。
また、志望する大学によって出題形式や必要となる知識に差があるため、これらの点も考慮しながら、おすすめの参考書を紹介します。
【インプット】おすすめ教材1:学校配布の教科書
世界史の教科書では、山川出版社、東京書籍、帝国書院が出版している教科書が多いです。これらの教科書には、編集協力者として、大学の教授の名前が記載されています。
学校で配布される教科書は、実際に入試問題を作成している大学の先生が編集に関わっていることも多く、論述問題で問われる知識や表現がそのまま使われている場合があります。
したがって、教科書に書かれている表現を使いこなせるようにするだけでも、非常に効果的な論述対策になるのです。教科書については以下の記事で詳しく解説しています。
【インプット】おすすめ教材2:タテから見る世界史
東進ハイスクールや学研プライムゼミで人気の講師、斎藤整先生の著書です。論述問題で頻出の「地域史」や「各国史」に特化し、地域ごとの歴史をわかりやすくまとめています。
地域史に特化した参考書は少ないため「地域史が頻繁に出題される」「地域ごとの歴史をなかなか覚えられない」という悩みを抱えている人には、特におすすめの一冊です。
【インプット】おすすめ教材3:『ヨコから見る世界史』
こちらも斎藤整先生の著書で「ヨコから見る世界史」というタイトルが示すように、時代ごとに世界史をまとめた参考書です。
論述問題で頻出の「時代背景」や「各国のつながり」を教科書よりも分かりやすく理解できるでしょう。
世界史論述のアウトプットにおすすめの参考書3選
世界史の論述問題を解くためには、インプットした知識を整理し、メモを作成したり、文章に変換したりするアウトプットの練習も必要です。
志望する大学の出題傾向に合わせて、アウトプットの教材を適切に使い分けていきましょう。
【アウトプット】おすすめ教材1:みるみる論述力がつく世界史
『みるみる論述力がつく世界史』は教科書と同じ山川出版社が出している論述問題集です。解説がしっかりしているうえ、「よくある間違い」の答案も確認でき、かつ「どの要素で点数がもらえるか」がはっきり書かれているので、独学でも使いやすくなっています。
下書きを書くところから手順に沿って書かれているので、メモ書きをした後の復習や、出題パターンの理解がスムーズでしょう。
【アウトプット】おすすめ教材2:段階式世界史論述のトレーニング
段階式世界史論述のトレーニングは、勉強法の解説で取り上げた参考書です。「段階式」という名前の通り、「50字〜90字」「100字〜150字」のように、文字数ごとに問題が厳選されています。
解答例だけでなく、採点基準も詳しく解説されているので、安心して学習を進められるでしょう。オーソドックスで使いやすい問題集なので、おすすめです。
【アウトプット】おすすめ教材3:各大学の過去問題集
論述問題は、大学によって出題傾向が大きく異なるため、過去問演習が非常に有効です。受験する大学の過去問を、他の科目よりも多めに解き、出題傾向を把握に努めてください。
9月〜10月頃から、古い過去問を使って演習するのもよいでしょう。特に、東京大学や京都大学、一橋大学など、字数の多い論述問題が出題される大学では、過去問やその解説も比較的容易に入手できるため、30年分をさかのぼって過去問演習に取り組むことも珍しくありません。
志望する大学に特化した「赤本」や、予備校の講座、問題集などを活用することで、大学ごとの出題傾向を効率よく把握できるのでおすすめです。
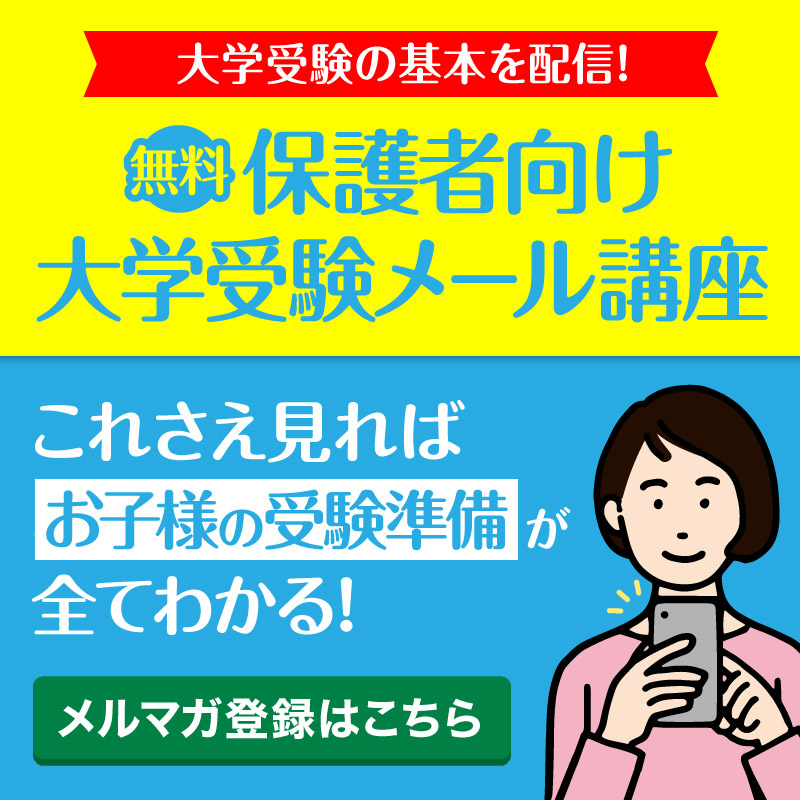
世界史論述に関するよくある質問

世界史の論述対策について、よくある質問をまとめました。同じ悩みを抱えている受験生も多いはずなので、よくある質問を参考に、疑問点を解消しておきましょう。
Q1:世界史の論述対策はいつ始めればいい?
対策を始める時期は早ければ早いほどよいですが、まずは用語の暗記や通史の理解を優先しましょう。論述対策には、高校3年生の夏休み頃から取り組み始めるのがおすすめです。
東京大学や京都大学など、難関大学を目指す場合は、もっと早い時期から対策を始めても構いませんが、まずは教科書に掲載されている基本的な用語を暗記し、通史の流れを理解することを優先しましょう。
これらの基礎ができていないと、メモ書きの段階で「何を書けば良いのか?」という状態に陥ってしまいます。以下の通史理解や暗記の記事も参考にしてください。
Q2:論述でいつも字数が余ってしまうのですがどうすればよいですか?
論述問題の文字数は、記述してほしい要素の数に基づいて決められています。したがって、字数が余ってしまうということは、解答に必要な要素が不足している可能性が高いです。
メモ書きを見返し、足りない要素がないか確認してみましょう。
Q3:論述のために対策する時間がないから、捨ててもいい?
論述問題を簡単に捨ててしまうのは得策ではありません。論述問題で必要となる力は、他の問題形式を解く上でも役立ちます。
正確に歴史の流れを理解していれば、少ない字数でも部分点を獲得できる可能性があるため、できる限りの対策を講じましょう。
特に、国公立大学の入試では、大半の大学で論述問題が出題されます。そのため、「論述を捨てる」という選択肢はありません。
対策する時間が取れない場合でも、特別な対策をしなくても部分点を狙うことは可能なので、背景や因果関係の理解など、論述対策を意識して勉強を進めましょう。
さいごに
この記事で最も重要なポイントは、冒頭で解説した「世界史論述3つの攻略ポイント」です。いきなり文章を書き始めるのではなく、まずメモ書きで思いつく限りの要素を書き出し、解答に必要な要素を過不足なく洗い出すようにしましょう。
そして、洗い出した要素を、メモや図で整理し、問題文の要求に沿った解答を作成することを心掛けてください。
これらの攻略ポイントを意識して、「メモを取り、図で示す」練習を繰り返すだけでも、論述問題の得点力は飛躍的に向上するはずです。
論述問題は、世界史学習における最難関といえますが、この記事で解説した論述対策のスキルを身につければ、「何を書けば良いのだろう?」と悩むことはなくなるはずです。自信を持って勉強を進めてください。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。














