*紹介している教材にはプロモーションを含みます
「日本史の文化史で得点が取れない」
「文化史はどうやって勉強すればいいのか分からない」
日本史の文化史は、高校の授業でも取り扱われることが少ないので、対策がしづらいですよね。
共通テストでは、毎年必ず文化史の問題が出題されており、対策は必須です。
本記事では、大学入試における日本史の文化史の勉強法を紹介します。
共通テスト日本史の2割は文化史から出題!対策は必須

共通テスト日本史のなかで、毎年2割の問題は文化史に関して出題されており、対策は必須です。
また、ほとんどの大学の場合、文化史は教科書に載っている内容からしか出題されません。
従って、勉強をしておけば対策をしていない受験生との差をつけやすい分野です。
ここから、文化史を得点源にするための勉強法を紹介します。
文化史の勉強①|勉強はいつからやればいい?
文化史の勉強は、以下の2点を参考に自分の状況に合ったタイミングで行ってください。
- 受験まで時間がある高校1・2年生は、定期テストのたびに勉強をする
- 高校3年生であまり時間がない人は、通史を終えた後に勉強する
文化史は、定期テストの直前に勉強することをおすすめします。
文化史は、覚える内容が多いため、一気に覚えるのは難しい分野です。テストの1週間前から勉強を始めて、試験範囲の文化史をマスターしてください。
定期テストのたびに文化史を勉強しておけば、積み重ねで忘れにくくなっていきます。試験のたびに繰り返し学習しましょう。
また、高校3年生で、今まで文化史を勉強してこなかった人は、通史の勉強を1周分終わらせてから対策してください。
通史とまとめて勉強してしまうと、内容が多くなり過ぎて、対策しきれません。
以下の通りに、勉強スケジュールを組むのをおすすめします。
- Step.1 通史の勉強を終わらせる
- Step.2 文化史単体で勉強する(文化史1周目)
- Step.3 文化史を通史と一緒に勉強する(文化史2周目)
通史の勉強が1周分終わった後に、文化史を1周勉強してください。その後、通史と合わせて文化史の2周目の勉強をしましょう。
日本史の通史と合わせて覚えることで、文化を時代ごとに整理して覚えられるので、記憶に定着しやすくなります。
とくに、早慶レベル以上の高難易度の大学を志望する場合、通史と文化史の知識を組み合わせて解く問題が多くなるので、同時に勉強するのをおすすめします。
文化史の勉強②|何を覚えればいい?
文化史は、教科書レベルの内容をすべて覚えるようにしてください。
教科書レベルをすべて暗記できれば、合格点を取れるレベルになります。
- 作品名と作者名
- 仏像、建造物などの特徴
- 文学、絵画の派閥
- 宗教史
上記4点は、出題されやすい内容です。ここから1つずつ解説していきます。
作品名と作者名
作品の名称と一緒に、作者名を覚えていきましょう。
たとえば、「唐獅子図屏風」の名前を言われたら、作者が狩野永徳であることを答えられるようにしてください。
また、作品名に対して作者名が、教科書に書かれていない作品は、作者名を覚える必要はありません。
教科書に作者名が載っていなくても、単語帳や一問一答などの参考書には、記載されていることがあります。しかし、教科書に載っていないことであれば、覚える必要はありません。
難関大学なら、珍しいものも出てくる可能性がありますが、何年かに一度しか出てこないため、教科書に載っているものを覚えるだけで十分合格点に達します。
仏像、建造物などの特徴
仏像や建造物は、特徴までセットで覚えましょう。
たとえば、天平文化の仏像は「乾漆像」と「塑像」があることや、弘仁・貞観文化の彫刻は「一木造」と「翻羽式」があることなどです。
文学、絵画の派閥
文学や絵画には、派閥まで書かれていることがあります。明治・大正時代の文学は、ほぼ必ず派閥まで書かれています。
たとえば、武者小路実篤は白樺派、永井荷風は耽美派という派閥です。
派閥は、文学・絵画の特徴だと考えると、暗記しやすくなります。
宗教史
宗教史は、時代ごとに意識して覚えるようにしてください。時代ごとに、仏教以外の宗教がでてくることがあります。
教科書で出てくるレベルのものは、必ず覚えてください。
文化史の勉強③|どんな方法で勉強すればいい?
文化史は、次の3つの手順で勉強してください。
- 理解する
- 暗記する
- 演習する
それぞれの手順について説明します。
理解する
「誰がどのような目的でつくったか」「作品がつくられた時代の時代背景」などを理解してください。
作品には、必ずつくられた理由や時代背景があります。
たとえば、弘仁・貞観文化の作品がつくられた目的や時代背景は、以下の通りです。
| 天台・真言両宗が盛んになると、神秘的な「密教芸術」が新たに発展した。建築では、寺院お同党が山間の地において、以前のような形式にとらわれない伽藍配置でつくられた。「室生寺の金堂」などは、その代表である。彫刻では、密教と関わりのある「如意輪観音」や「不動明王」などの仏教が多くつくられた。これらの仏像は「一木造」で神秘的な表現を持つものが多い。 |
上記のように、時代背景やストーリーを理解しながら覚えると、暗記しやすくなります。
単語だけを暗記しようとすると、記憶に定着しにくいので、理解しながら覚えていく必要があります。
理解することについては、スタディサプリを使った勉強法がおすすめです。
暗記する
ストーリーをつくって理解したら、記憶に定着させるために暗記していきます。
暗記には、「一問一答」の参考書を使うのがおすすめです。
「一問一答」を使って単語を暗記するコツは、覚えた単語を思い出す練習をすることです。
暗記したら、紙に書いて思い出すようにしてください。
思い出せなかった単語は、ノートに書き出すことで、単語を効率よく覚えられます。
演習する
暗記した知識を使って問題を解くことで、記憶により定着させられます。
また、暗記した知識を使って問題を解かなければ、試験問題が解けるようになりません。
知識を使って得点するため、「演習する」ことが大事です。

文化史のおすすめ参考書|攻略日本史 テーマ・文化史 整理と入試実戦
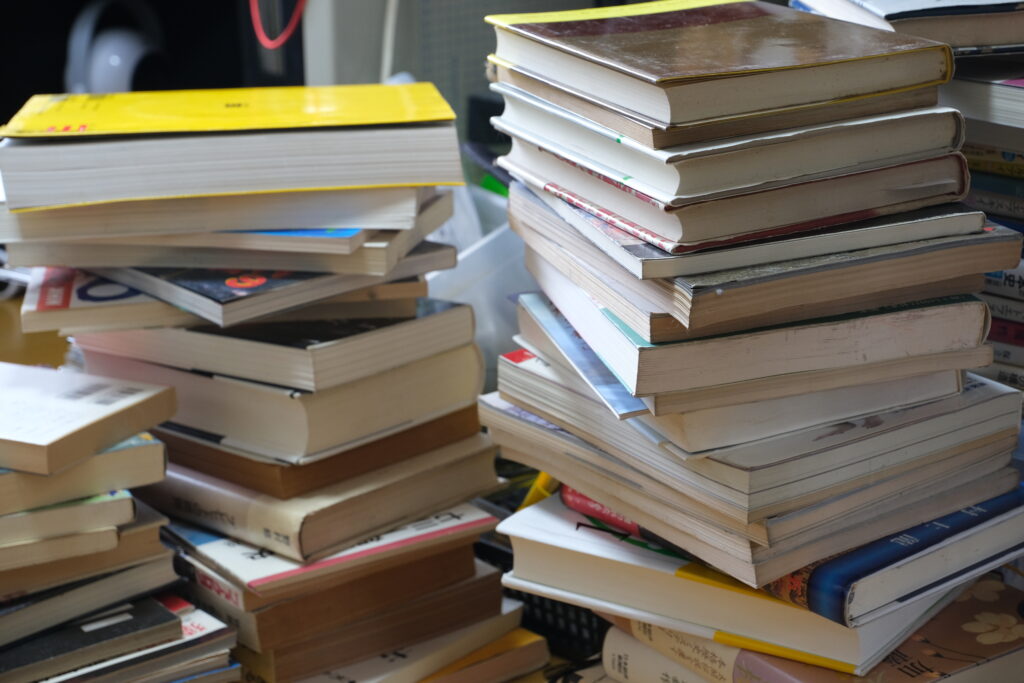
「攻略日本史 テーマ・文化史 整理と入試実戦」は、文化史における重要なポイントとそのポイントに関する演習問題がセットで記載されている参考書です。
文化史の問題が多く掲載されており、詳しい解説がついています。
論述問題も出題されているので、論述対策にもおすすめです。
文化史を得点源にして他の受験生に差をつけよう
文化史は、共通テストの日本史で毎年出題される重要な内容です。
対策ができていない人が多いので、勉強をしておくことで他の受験生に差が付けられます。
文化史は、教科書レベルを覚えておくだけで十分合格点が狙える分野です。
しっかり対策をして、日本史の成績アップにつなげましょう。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。











