*紹介している教材にはプロモーションを含みます
地理が苦手な生徒がはじめに取り組むべき勉強とは?
「主要教科の勉強があって地理の勉強ができてない…」
「地理の勉強はバッチリ。毎日バリバリ勉強しています!」
あなたはどちらにあてはまりますか?
実は、どちらも勉強法としてはおすすめできません。なぜなら、正しい勉強法を実践すれば地理の勉強に時間を割かなくても点数がとれるからです。
今回は、勉強時間をほとんどかけなくても地理で点数がとれる勉強法について解説します。

系統地理と地誌どちらを先に勉強したらいい?

地理は系統地理を中心に勉強をすれば、短期間で高得点が狙えます。ここでは、系統地理と地誌の違いや系統地理を先に勉強した方がよい理由について解説します。
系統地理と地誌の違いは?
受験地理は、系統地理と地誌の二つの分野に分かれています。
- 系統地理:テーマ別に学習していく地理分野
- 地誌:地域別に学習していく地理分野
系統地理は「気候」・「農業」・「人口」・「交通」などテーマ別に学習していきます。
一方、地誌は、地域別に学習していきます。
系統地理から勉強した方がよい理由
系統地理から勉強した方が良い理由は、系統地理をしっかり理解していれば、地誌を勉強していなくてもほとんどの問題が解けるからです。地誌は、系統地理で習ったことを地域ごとに詳しく見ていく分野であるため、系統地理の知識が身についていれば十分高得点が狙えます。
少しわかりにくいかもしれませんので、ここで具体例を挙げていきます。
例えば、地誌で以下について習ったとします。
タロイモ・ヤムイモ・キャッサバの生産量は、ナイジェリアが世界1位。
系統地理の内容があまり身についていない生徒が覚えようとすると、
「ナイジェリアはイモ類の生産が盛ん?タロイモ…ヤムイモ…キャッサバ…タロイモ…ヤムイモ…キャッサバ…??」
のように丸暗記せざるを得なくなります。覚えるだけの勉強法では暗記が多い地誌を勉強するのは大変です。
しかし、系統地理の内容が頭に入っている生徒であれば、ナイジェリアは世界最大のタロイモ・ヤムイモ・キャッサバの生産国であることが分かり内容を理解して覚えられます。
「気候」から考えれば、ナイジェリアは熱帯系の気候区分だろう。熱帯系の気候なら土壌はやせたラトソル(※土の名前)と考えられる。「農業」的にはイモ類の生産が盛んなはず。さらに「人口」の観点から見ればナイジェリアはアフリカで最大の人口であることから、食物の生産量が多いはず。当然、タロイモ・ヤムイモ・キャッサバの生産量は多いだろう。
このように、系統地理の内容が分かっていれば、統計データを知らなくても推測して答えを導けます。
つまり、系統地理をしっかり勉強して内容を理解していれば、地誌で暗記に苦しむことがなくなります。系統地理を身につけることが、早く楽に地理を得点源にするためのコツと言えるでしょう。

系統地理の具体的な勉強
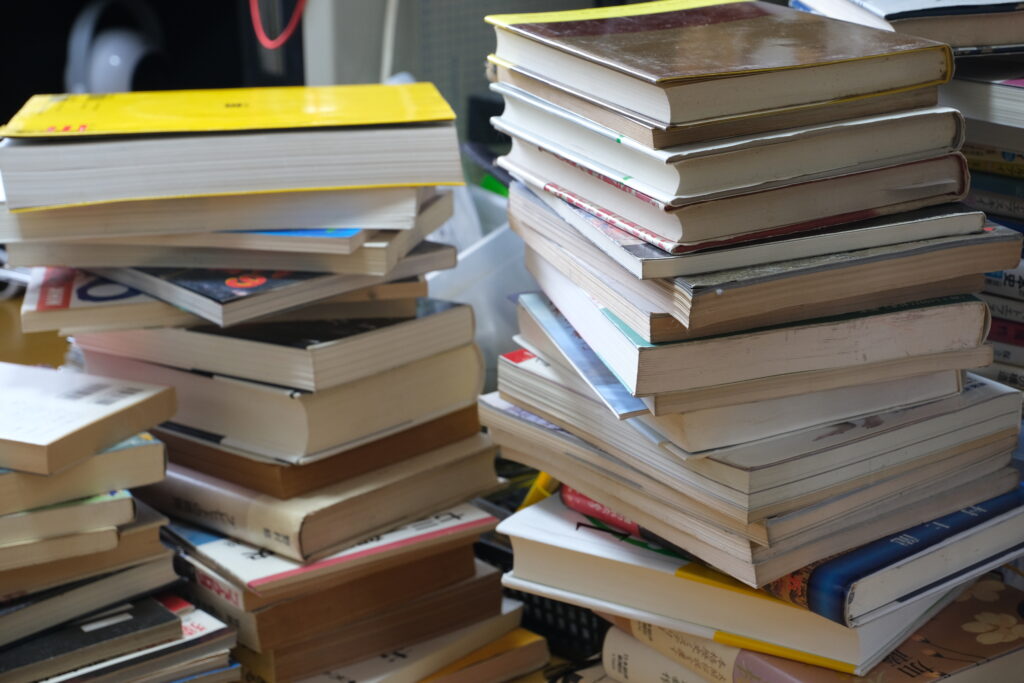
地理を得意教科にするには系統地理の勉強が欠かせません。ここでは、系統地理の具体的な勉強法について解説します。
系統地理の勉強法のコツは「なぜ?」を考えること
系統地理の内容を身につけるうえで最も大切なポイントは、因果関係をとらえることです。もっと分かりやすく言うと「なぜ?」を考えながら学習を進めていくことが大切です。
- 「なぜアフリカには砂漠や熱帯雨林があるの?」
- 「なぜ東アジアでは稲作が盛んなの?」
- 「なぜアメリカ合衆国では、移動するのに電車は使わないの?」
などの疑問を持ちながら、解決に向けて学習を進めていきましょう。考えながら学習すると、単なる暗記ではなく理解しながら知識を身につけられます。
また、「なぜ」を考えることで試験で問題を解く際の思考力にもつながります。
系統地理のベストな学習ペースは?
系統地理のベストな学習ペースは以下の通りです。
- 時期:高2がベスト(遅くとも高3の夏休み~)
- 期間:3ヶ月
- 一回の勉強時間:2時間
- ペース:1週間に2回
系統地理の勉強を始める時期は、高校2年生がベストです。早い時期に系統地理の勉強を始めても、暗記ではなく理解することをメインにおけば忘れることはないです。さらに、高校3年生でしっかり地誌の学習や過去問を解く時間も残せます。
たとえ高校3年生になっていたとしても間に合わせることは十分可能です。しかし、遅くとも高校3年生から系統地理に力を入れて勉強するようにしましょう。
系統地理の勉強期間は、急いで学習を進めたとしても3か月はかかります。
高校3年生から始めた生徒にとっては、地理の学習にあてられる時間はそれほど多くありません。がんばれば1か月以内に終わらせることもできますが、大体3か月を目標に学習を進めていくとよいでしょう。
他の教科との兼ね合いもあるので、一回の勉強で2時間、週2回のペースで進めていくのがおすすめです。

系統地理を勉強するときに気をつけたいポイント
系統地理を学習するうえで気を付けたいポイントは以下の3つです。
- 単語を全て覚えなくてもよい
- 単語を全て覚えなくてもよい
- 地図帳や資料集を活用する
それぞれ解説していきます。
単語を全て覚えなくてもよい
系統地理だけでなく地誌にも共通して言えるのは、単語を全て覚えなくても大丈夫ということです。
例えば、「EU」の正式名称を覚えたり、一部の主要な国を除けば、世界の国の首都を全て覚えたりする必要はないのです。
地理は、日本史や世界史と異なり単語を答える問題はほぼありません。
そのため、地理を得点源にするためのポイントは、単語を全て正確に答えられることよりも、その単語に関連して覚えるべき事柄をおさえておくことです。
例えば、EUの正式名称は分からなくても、EUができるまでの変遷や、なぜ欧州がEUのような組織を作ろうとしたのかなど関連事項は覚えておく必要があります。
統計データも全部覚えなくてもよい
また、統計資料のデータも必要最低限が頭に入っていれば問題ありません。
具体的には、教科書や資料集に掲載されているものに関して、トップ5の国をおさえておけば十分です。トップ5の中でも順位まで正確に覚える必要はなく、トップ1・2位あたりをおさえておけば十分でしょう。個別の生産額などは覚えなくても問題ありません。
ただし、統計データは必ず最新のものを使って覚えるように注意してください。統計データの多くは毎年更新されており、順位に変動がある場合もあります。データは常に最新のものを確認しましょう。
地図帳や資料集を活用する
教科書を使って勉強している生徒は多いでしょう。しかし、地理の教科書は、日本史や世界史の教科書に比べて分かりやすい文章で構成されている反面、網羅性に欠けています。
そのため、地理の全体像をつかむには、学校や予備校の授業を活用したり、市販の参考書を軸に勉強を進めたりするのがおすすめです。市販の参考書は、系統地理の内容をわかりやすく体系立てて説明されており、効率的に勉強を進められるでしょう。
また、地理の勉強では、地図帳で位置関係を確認したり、資料集を使って理解を深めたりすることが重要です。教科書や参考書だけでなく、必ず地図帳や資料集を使って確認しましょう。ただし、地図帳や資料集で調べたことを全て暗記する必要はありません。。大切なのは調べたことを暗記することではなく理解することです。
さらに、教科書を辞書として使うのが効果的です。教科書の大きな魅力は、参考書などに比べて因果関係がしっかり記述されていることです。参考書や授業で学習したことをより深く理解するために教科書を読み込みましょう。
以下は、系統地理の学習で暗記するべきものと、暗記しなくていいものの具体例です。
下記の例を参考にしながら、覚えるべき事項を取捨選択して勉強しましょう。
| 覚えるべきこと | 覚えなくてもよいこと |
|---|---|
| 石油生産額上位5カ国で、大量の石油が採取できる理由 | 石油の生産額の上位10カ国 |
| 東・東南アジアの国々の人口が多い理由 | 世界各国の人口 |
| ヨーロッパにおいて、旅客輸送における鉄道が高い割合を占める理由 | ヨーロッパの旅客輸送において、鉄道が占める割合 |
| EUが作られた理由 | EUの正式名称 |
まとめ
地理は、系統地理の内容がしっかり身についていれば十分高得点が狙えます。
系統地理の勉強する時には、丸暗記ではなく「なぜ?」を考えながら理解を深めていきます。また、系統地理の勉強は、他の主要教科の兼ね合いを考えながら短期間で取り組むのがベストです。
正しい勉強法を実践して短期間で実力を身につけていきましょう。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。












