*紹介している教材にはプロモーションを含みます
- 共通テスト数学の対策を始めたいけど、どの参考書がおすすめなのか分からない…
- 予想問題集や過去問はいつから取り組んだらいいの?
こんな疑問はありませんか?
本記事では共通テスト数学の対策におすすめの予想問題集や参考書はもちろん、取り組み方や予想問題集に取り組むべき時期まで解説します。
この記事を読めば共通テスト数学の対策で「何をすべきか」を理解でき、志望校合格に大きな一歩を踏み出すことができます。
それでは順番に見ていきましょう。
共通テストの予想問題・過去問に取り組むべき時期
共通テストの予想問題や過去問には、高3の夏のおわり〜秋ごろには徐々に取り掛かるようにしましょう。
なぜならあまりに早く取り組んでも点数が思うように取れずに落ち込んでしまったり、本番まで時間が空くため「中だるみ」してしまったりする可能性があるためです。
それまでは参考書を活用して基礎知識や自分の苦手分野の克服を中心におこない、秋ごろから徐々に共通テストの過去問や予想問題に取り組み、12月頃には共通テストに集中して勉強に取り組むのがおすすめです。

共通テスト数学対策:おすすめの予想問題集&参考書5選
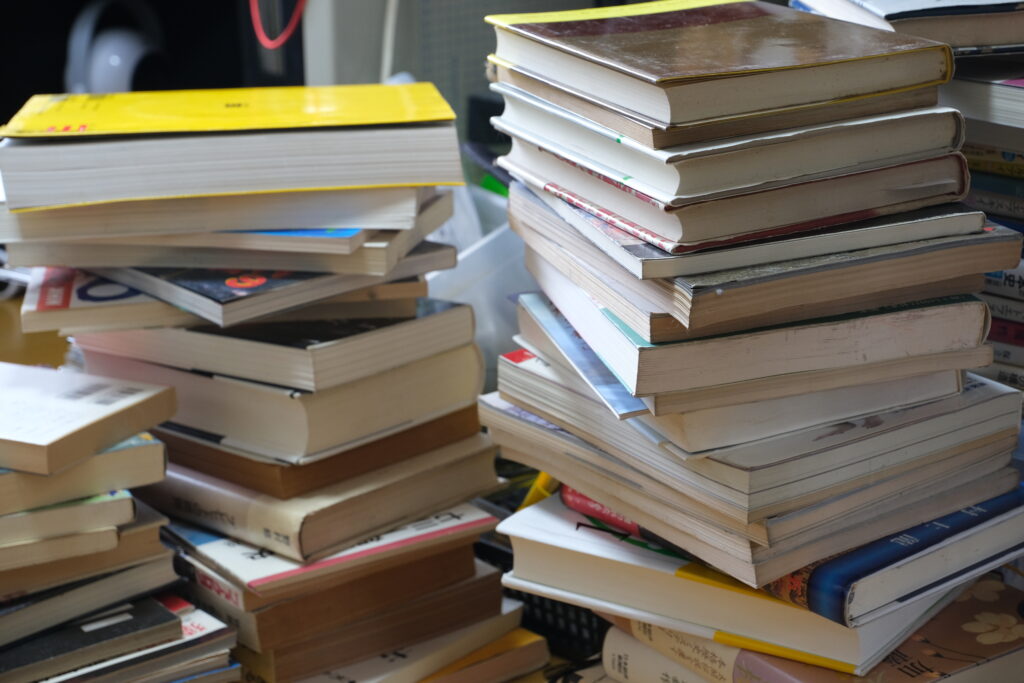
ここからは「共通テスト数学対策:おすすめの予想問題集&参考書5選」を紹介します。
先ほど解説したように高3の夏後半〜秋には予想問題集に取りかかり、それまでは参考書で基礎力をアップさせましょう。
本章では以下の5つの予想問題集と参考書を紹介します。
- Z会 共通テスト実戦模試数学
- 駿台 大学入学共通テスト実戦問題集 数学
- 青チャート
- 緑チャート
- 合格る計算1A2B
自分の状態や時期を考慮して、予想問題集または参考書のどちらかに取り組むようにしましょう。
それではひとつずつ見ていきます。
1.Z会 共通テスト実戦模試数学
「共通テスト実践模試」はZ会オリジナルの模擬試験と過去の本試験・追試験を掲載している予想問題集です。
流れとしては、オリジナルの模擬試験で実践力をつけた後、過去の本試験・追試験で実力をチェックすることをおすすめしています。
またこの問題集の最大の特徴は「スマートフォンで採点ができる」こと。
付属のマークシートに回答して、そのマークシートをスマートフォンで撮影すると自動採点が可能。
また志望大学別に自分のランキングも見ることができます。
そこで「同じ大学受験希望者がどのくらいの点数を現在取れているのか」「自分は今どの位置にいるのか」を客観的に把握できます。
2.駿台 大学入学共通テスト実戦問題集 数学
「駿台大学入学共通テスト実戦問題集」は、駿台オリジナル問題5回分と共通テスト本試験の過去問3年分を加えたボリュームある問題集です。
先ほど紹介した「Z会共通テスト実戦模試」を終わらせ、「もっとたくさん類似問題を解きたい」と感じた方におすすめです。
解説は別冊で詳しくされているため、不明点があってもそのままにせず、しっかりとチェックすることができます。
また重要事項だけをぎゅっとまとめた「直前チェック総整理」もあるため、共通テスト直前まで活用できます。
この実践問題集を終わらせた後に、下記の「共通テスト予想パック」も解くと共通テスト対策はバッチリでしょう。
3.青チャート・緑チャート
青チャートは基礎から応用まで、幅広く網羅されたさまざまなレベルの方におすすめの参考書です。
「共通テストまで時間がある方」「特に理系でまだ試験まで時間があり基礎をしっかり固めたい方」にはおすすめです。
もし取り組んでみて「自分には難しい」と感じたら白チャート・黄チャート、「もっと難問にチャレンジしたい」と感じたら赤チャートにチャレンジしてみましょう。
チャートシリーズは難易度別に4種類の参考書があるため、まずは青チャートから取り組んでみて自分の数学の実力を見定めるのも良いでしょう。
また文系で「あまり数学の対策に時間をかけたくない」という方は、大学入学共通テスト専用の「緑チャート」があります。
そちらに取り組んでみるのもおすすめですが、緑チャートだけで共通テストレベルをすべてカバーするのは時間がかかります。
普段から青チャートで基礎を積み重ね、その上で直前に緑チャートや予想問題にチャレンジ
することがベストです。
4.合格る計算1A2B
『合格る計算1A2B』は計算力に特化した問題集です。
そのため「共通テスト予想問題に取り組んでみたけど計算ミスが多くて取りこぼしている方」「とにかく計算問題が苦手で演習に取り組みたい方」におすすめです。
また「解法を理解しているけど計算が遅くて時間内に解き終わらない方」にも、ぜひ取り組んでいただきたい一冊です。
ただしこの参考書だけで数学を理解できるわけではないので、補助的に他の参考書と一緒に活用しながら取り組むと良いでしょう。

予想問題のおすすめの使い方

予想問題集は本番に近い内容・レベルの問題を扱っているため、出来るだけ本番を意識して取り組むことがおすすめです。
具体的な使い方は以下の通りです。
- 時間を計って過去問や予想問題を1年分解いてみる
- 採点をする
- 解説を見て間違えた部分を確認する
- 目標点まで上げるためのアクションを起こす
それぞれ解説していきます。
STEP1:時間を計って過去問や予想問題を1年分解いてみる
1つ目のステップは「時間を計って過去問や予想問題を1年分解いてみる」ことです。
まず何事も対策をするには「相手を知ること」「自分を知ること」です。
共通テストではどんな試験内容がどのように出題されるのか、本番同様に時間を計って解いてみましょう。
出来るだけ備え付けの回答用紙を使い、参考書なども見ずに解いてみましょう。
そうすることで今の自分の実力や得意・苦手分野を理解でき、対策を立てやすくなります。
ここでポイントは「時間がなくて解ききれなかった箇所や選択問題で選ばなかった問題もペンの色を変えて解いてみる」ことです。
そうすることで「解法をわかっていたのに解けなかった」のか「解法をわかっていなくて解けなかったのか」、きちんと理由を明らかにできます。
もし「解法をわかっていたのに解けなかった」のであれば、その問題にたどり着くまでの時間配分や、計算スピード・解く順番などを見直す必要があります。
一方で「解法をわかっておらず解けなかった」のであれば、もう一度参考書や解説を読み、基本に立ち返るべきでしょう。
このように予想問題・過去問を解くことでわかることがあるため、まずは1年分解いてみましょう。
STEP2:採点をする
2つ目のステップは「自己採点」です。
この際に「色を変えて回答した箇所」は点数に含まないようにしましょう。
STEP3:解説を見て間違えた部分を確認する
3つ目のステップは「解説を見て間違えた部分を確認する」です。
間違えた箇所は「なぜ間違えのか」を明らかにするため、解説を読みましょう。
理解できたら解説を横に置いて、一度自分で解いてみましょう。
こうすることで解説を理解し、自分に定着をさせます。
しかし解説を読んだ直後だと理解できていなくてもなんとなく解けてしまうかもしれません。
そのため間違えた問題はチェックを入れて、数日後にもう一度解いてみましょう。
STEP4:採点結果と目標結果を埋める具体的な行動を決める
4つ目のステップは「採点結果と目標結果を埋める具体的な行動を決める」です。
ここまでで自分の今の実力と、目標との差を理解できたかと思います。
次にやるべきことは、その差をどのようにして埋めるかです。
例えば計算ミスが多いのであれば計算ミスをなくせるように問題集に取り組む、解法が分からなくて解けない箇所が多いのであれば参考書を復習しましょう。
自分のミスに応じてやるべきことを洗い出し、もう一度過去問・予想問題を繰り返し解いてみましょう。
ゴールA:全年度の過去問を解き終わる前に目標点を達成できた場合
過去問・予想問題を繰り返し、目標点を無事達成できた場合は本番に向けて自分が間違えた箇所を復習しましょう。
またテスト直前に予想問題または過去問をもう一度解き、本番に慣らすようにもしておくと良いです。
ゴールB:全年度の過去問を解いても目標点に達しなかった場合
目標点に到達できないまま1冊の過去問・予想問題集を終えた場合は、参考書や問題集に取りかかりましょう。
過去問や予想問題に取り組み、目標点数に達しなかった場合でも自分にとって苦手な箇所・伸ばせる箇所は理解できたのではないでしょうか。
そこを補える参考書・問題集の取りかかりましょう。
その際には下記関連記事を参考にしてみてください。
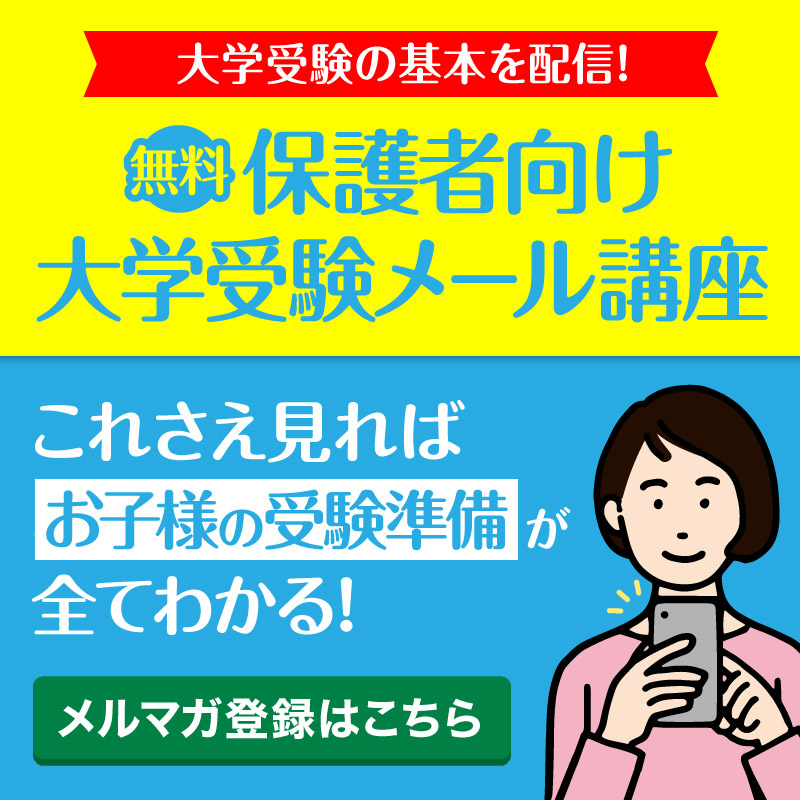
予想問題を解く際の注意点

最後に予想問題を解く上での注意点を解説します。
- 共通テスト当日までに全部終わらせる
- 制限時間を延長しない
- しっかり復習してから次に行く
順番に見ていきましょう。
注意点その1「共通テストまでに全部終わらせる」
1つ目は「共通テストまでに終わらせる」ことです。
せっかく予想問題を買っても、すべて終わらないと効果は出づらいです。
試験までの残り日数と予想問題のボリュームを考慮し「何日に1回は予想問題を解く」と決めるようにしましょう。
注意点その2「制限時間を延長しない」
2つ目は「制限時間を延長しない」ことです。
先ほど解説したように「ペンの色を変えて解ききれなかった問題を解く」のはよいですが、「本番ではないし延長しよう」とするのは控えましょう。
あくまで本番の時間制限でどれだけ解答ができたのかをチェックしましょう。
注意点その3「しっかり復習してから次に行く」
3つ目は「しっかり復習してから次に行く」ことです。
予想問題は今までの共通テストの傾向を反映し、練られている良問ばかりです。
全く同じ問題は出ないかもしれませんが、似たような問題・数字を入れ替えただけの問題が出る可能性はあります。
1問ずつ分からなかった問題は復習し、次は解けるようにしましょう。
まとめ
本記事では以下を解説しました。
- 過去問や予想問題に取り組むべき時期
- おすすめ予想問題集&参考書4選
- おすすめの予想問題の使い方
この記事を読んで共通テスト対策を理解でき、今の自分が何をすべきか定められた方も多いのではないでしょうか。
ぜひ当記事を参考に、数学の共通テスト対策に取り組んでみてください!
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。



















