*紹介している教材にはプロモーションを含みます
数学の参考書は数多くあるため「どれを選んだら良いのだろう」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
本記事では「自分にあっている参考書で数学の成績を上げて志望校に合格したい方」に向けて以下の内容を解説します。
本記事では、自分にぴったりな参考書の選び方や使い方のコツ、おすすめの数学の参考書5選を紹介します。この記事を読めば自分にぴったりな参考書を見つけられ、今日から数学の成績アップに向けて走り出せます。
では順番に見ていきましょう。
自分にピッタリの数学参考書を選ぶのが成績アップのコツ!

成績アップするために1番重要なことは「自分に合う参考書」を選ぶことです。
なぜなら自分にあった参考書を使わないと、
- 数学を勉強するどころか、参考書を開くことすら嫌になってしまう
- いくら参考書を活用しても成績が上がらない
- 数学を嫌いになってしまう
こういった事象が起きてしまうからです。
では、自分に合う参考書を選ぶにはどんなポイントを押さえたら良いのでしょうか。
以下の3つのポイントをチェックして選ぶことで、ミスマッチを防ぎ、自分にぴったりな参考書を選べます。
- 今の自分には「参考書」が必要なのか、それとも「問題集」が必要なのか
- 問題や解説の量は自分にとって適切か
- 「大きさ」「色」「デザイン」「イラスト量」は自分にあっているか
人によって数学における課題はさまざまです。
まずは手にとって中身を見て、上記ポイントをチェックしてみましょう。

数学参考書おすすめ5選
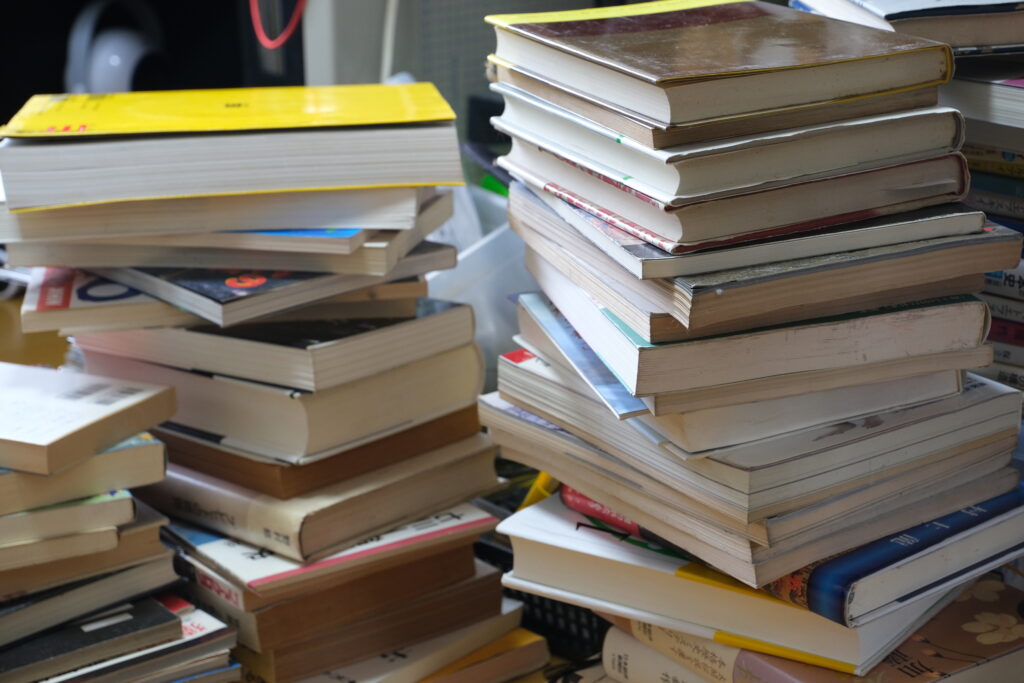
では数学の参考書のおすすめを5つ紹介します。
おすすめ数学参考書その1:「入門問題精講」
レベル:教科書や学校の授業についていけていない方
この参考書は「数学が苦手」「学校の授業も理解できていないところがある」、そんな方におすすめの参考書です。
数学が苦手な人でも取り組みやすい難易度の問題や、丁寧な解説があるため「入門書」として最適です。
この参考書を終えて「もう少し数学に取り組みたい」と感じたら、「基礎問題精講」「標準問題精講」「上級問題精講」「分野別標準問題精講」にもチャレンジしてみましょう。
おすすめ数学参考書その2:「青チャート」
レベル:共通テストで9割目指したい方、基礎はある程度習得できている方
青チャートは基礎から応用まで、幅広く網羅されたさまざまなレベルの方におすすめの参考書です。
しかし問題量が多いため、とくにおすすめは「共通テストで9割取りたい方」「国公立2次対策をしたい方」です。
もし取り組んでみて「自分には難しい」と感じたら白チャート・黄チャート、「もっと難問にチャレンジしたい」と感じたら赤チャートにチャレンジしてみましょう。
チャートシリーズは難易度別に4種類の参考書があるため、まずは青チャートから取り組んでみて自分の数学の実力を見定めるのも良いでしょう。
おすすめ数学参考書その3:「文系数学の良問プラチカ数学1A2B」
レベル:共通テストで8割取れる方、国公立の2次対策に取り組みたい方
「文系数学の良問プラチカ数学1A2B」は、「青チャートをある程度解けるようになった方」「共通テストで高得点を獲得したい方」におすすめの参考書です。
難関大学の過去問から選りすぐりの良問を集めているため、頻出の良問を何度も演習できることが良い点です。
一方で難易度は少し高めのため、数学の基礎がないと合わない可能性があります。
まずは先程紹介した2つの参考書に取り組んでから、この参考書に取り組むと効果的でしょう。
おすすめ数学参考書その4:「数学上級問題精講」
レベル:旧帝大・早慶が志望校の方
「数学上級問題精講」は、基礎はもちろん、ある程度の応用力も身についており、難関志望校に向けて本格的な演習をしたい方に向けておすすめの参考書です。
駿台予備校に長年勤めてきた著者が、難関国立大レベルの良問・頻出問題を集め、丁寧に解説をしています。
青チャートは完璧に解け、さらに発展的な問題にチャレンジしたいと思ったら、この参考書に取り組むと良いでしょう。
「おすすめ数学参考書その5:「はじめから始める数学」シリーズ
レベル:高校1・2年生
「はじめから始める数学シリーズ」は数学が苦手な方や、まだ受験まで時間がある高校1・2年生におすすめの参考書です。
解説が丁寧・「話し言葉」で書かれているため、すっと頭に入ってきやすい良書です。
ただしページ数と比較して問題演習量は少ないため「とにかく問題演習をしたい人」ではなく、「分からない箇所が多いのでしっかり解説を読み込んで理解したい人」により合った参考書です。
「数学が嫌い・苦手」「学校で習っていることがいまいちよく分からない」そんな方にもおすすめの「入門編」とも言える参考書です。
数学参考書の使い方のコツ

数学の参考書は数多くありますが、基本的な使い方のコツには共通したポイントがあります。
それは「同じ参考書を繰り返し活用すること」です。
詳しく見ていきましょう。
使い方のポイントは「同じ参考書を繰り返し活用すること」!
数学の参考書を効果的に使いこなすためには「繰り返し同じ参考書を使う」ことが重要です。
「一度学習したから次の参考書に手をつけよう」
「この問題はできるようになったから次の問題に取り掛かろう」
このように「一度できたら次の参考書に移る方」が多いのですが、人間は以下の4ステップで物事を習得すると言われています。
- 知る
- 分かる
- 出来る
- 教えられる
多くの方は「分かる」でやめてしまいますが、最低でも「出来る」まで到達できると良いでしょう。
なぜならテスト本番ではまったく同じ問題が出ることが非常に少なく「学んだことを応用する力」つまり「完璧に基礎を理解し活用できること」が求められるからです。
また人間は多くの出来事を「1日後には74%程度忘れている」と言われています。
つまりその場では「わかった」「できた」と思っていても、時間が経つと忘れてしまうことがほとんどです。
そのため繰り返し同じ参考書を解き、しっかりと定着させることが重要です。

まとめ
本記事では以下の内容を解説しました。
- 自分に最適な参考書を選んで数学の成績をアップさせよう!
- 成績アップするために1番重要なことは「自分に合う参考書」を選ぶこと
- 使い方のポイントは「同じ参考書を繰り返し活用すること」
- 数学が苦手な方には「入門問題精講」「はじめから始める数学」、シリーズ基礎はできている方には「青チャート」、応用や志望校に向けた演習がしたい方は「数学上級問題精講」「良問プラチカ」
本記事を参考に自分にあった参考書を選び、数学の成績をアップさせ、志望校合格を目指しましょう!
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。























