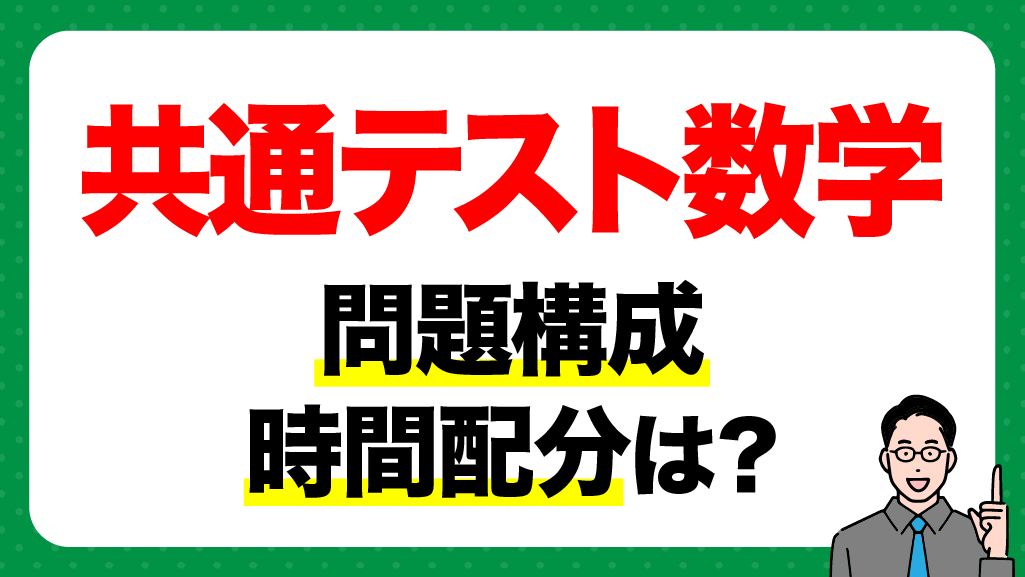
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
2025年の共通テストは2022年度の学習指導要領の変更に伴い、いくつかの変更がありました。
これらの変更点を押さえておきたいのはもちろんのこと「共通テストの数学のそもそもの全体概要を理解したい」「何から勉強を始めたら良いのか知りたい」という学生も多いのではないでしょうか。
本記事では共通テストの数学勉強法・問題構成などを徹底解説します。
本記事を読めば共通テスト数学の勉強法や問題構成、時間配分などを理解でき、効果的な対策をすることで点数アップに繋がります。
ぜひ志望校合格に向けて、最後までお読みください。

【共通テストの概要を理解しよう】設問・構成・特徴・配点を解説

まずは「共通テストの数学の概要」を理解することからはじめましょう。
共通テストに限らず、テストで高得点を取るためには試験全体の概要を理解することが大切です。
相手を知ることで、効果的な対策をおこなうことができます。
数学①・② それぞれの出題範囲・点数配分・2025年の変更点を解説
共通テストの数学は以下のように「数学①」「数学②」の2つの試験に分かれています。
- 数学①:「数学1」「数学1・A」のいずれか
- 数学②:数学2・B・C
数学①は、「数学1」のみからの出題と、「数学1・A」両方からの出題の2パターンが選べますが、「数学1・A」を選ぶ受験生が多いため、本記事では数学①に関しては「数学1・A」について解説します。
数学①・②の問題構成・点数配分は以下のとおりです。
| 試験 | 問題構成・点数配分 |
|---|---|
| 数学① | 第1問(30点):数学1 数と式・図形と計量 第2問(30点):数学1 二次関数・データの分析 第3問(20点):数学A 図形の性質 第4問(20点):数学A 場合の数と確率 |
| 数学② | 第1問(15点):数学2 三角関数 第2問(15点):数学2 指数関数・対数関数 第3問(22点):数学2 微分・積分の考え 第4問(16点):数学B・C 数列 第5問(16点):数学B・C 統計的な推測 第6問(16点):数学B・C ベクトル 第7問(16点):数学B・C 平面上の曲線と複素数平面 ※第4問〜第7問は選択問題(3問選択) |
数学①に関してはほとんどの分野から満遍なく出題され、全ての問題に解答しなければいけません。そのため出来るだけ苦手分野を克服し、どの大問でも点数が取れるようにする対策が必要です。
一方数学②は数学B・Cの範囲は選択問題で大問4問中3問を選択しなければいけません。数学Cの「平面上の曲線と複素数平面」は理系しか習わない学校が多いため、それ以外を文系受験者は選択する人が多いです。
数学①・②共通の注意ポイントは「すべてマーク形式での解答」であることです。
カタカナで空欄に順番が振ってあり、数字または記号を1つずついれて解答します。
そのため、マークミス・解答ズレがないように毎回答えを記入するときにチェックしましょう。
また、2025年の共通テストの変更点は以下の4つです。
- 数学①の問題形式:第3問〜第5問から2つ選ぶ形式から、第3問・4問両方解答する形式への変更
- 数学②の出題範囲:「数学2・B」または「数学2」どちらかを選ぶのではなく「数学2・B・C」の1つに統一
- 数学②の問題数:大問の数が2つ増加
- 数学②の試験時間:60分から70分に変更
これまでの過去問で十分に試験対策は可能ですが、時間や問題数の変化から「実際の試験を意識したシミュレーション」は難しくなります。
自分で問題を組み合わせたり、予想問題・模擬試験などを多く解き、練習を重ねましょう。

共通テスト数学の特徴2点

共通テストの数学には特徴が2点あります
- 特徴1 日常的な物事を数学的に考える問題
- 特徴2 2人の生徒の会話形式から考え方を読み取る問題
特徴1 日常的な物事を数学的に考える問題
1つ目の共通テストの特徴は「日常的な物事を数学的に考える問題が多い」ことです。
具体的には、一見数学とは関係のなさそうな説明部分があることです。
そのため数学の問題の本質を読み取ることが難しく、しっかり問題文の意図を理解することが大切です。
代表例として、過去出題された問題を見てみましょう。
試行調査30年1A第1問[3]から引用
普段あまり見ることがない出題形式のため「共通テスト対策」として何度も過去問を解き、慣れておくようにしましょう。
特徴2 2人の生徒の会話形式から考え方を読み取る問題
2つ目の共通テストの特徴は「2人の生徒の会話形式から考え方を読み取る問題」です。
具体的には、2人の生徒が会話をしていて、そこからそれぞれの生徒の考え方を読み取る形式です。
過去問を見て、詳しく解説します。
試行調査30年1A第2問[2]引用
このように、2人の人物が会話をしつつ、数学の問題を考えている問題が出題されます。
こちらも普段あまり解き慣れていない問題形式のため、事前に過去問で練習しておくことが大切です。
共通テスト数学の試験時間と時間配分・目安時間
試験時間は数学①・②ともに70分です。
2025年度の変化として、数学②では問題数が2つ増え、制限時間が10分増えました。
いままでの旧課程でも時間が足りない受験生が多い印象でしたが、より問題数も増え、さらに時間配分の戦略が重要です。
そこで当記事は以下の時間配分で解くことをオススメします。
| 試験 | 時間配分 |
|---|---|
| 数学① | 第1問:21分第2問:21分第3問:14分第4問:14分 |
| 数学② | 第1問:10分第2問:10分第3問:18分第4問〜第7問(うち3問):11分×3 |
ただし人によって苦手分野・時間がかかる大問は異なります。
この時間配分をベースに、自分にとって「ベストな時間配分」を探っていきましょう。
センター試験・新課程の共通テスト数学の違いを解説

2025年から大きく共通テスト数学の出題範囲や形式が変更になりました。
先ほど「数学①・② それぞれの出題範囲・点数配分・2025年の変更点を解説」にて2025年入試の変更点についてお伝えしましたが、本章では「センター試験」と「共通テスト」の違いを解説します。
センター試験と共通テスト数学の違い
センター試験と共通テストの大きな違いは「試験時間」です。
センター試験では60分だったのに対し、共通テストでは数学①・②ともに70分に変更されました。
また「出題形式」にも大きな変化がありました。
先ほど解説した「共通テスト数学の特徴2点」の問題形式は、センター試験時代にはあまり出題されていませんでした。
一般的な問題集で見かける淡泊な形式の問題が出題されていたセンター試験とは異なり、共通テストでは、やや文章を読み込まないといけない問題が増えています。
この2つが大きなセンター試験・共通テストの違いと言えるでしょう。

共通テスト数学で高得点を取る方法2選
次に共通テスト数学で高得点を取る方法を2つ解説します。
- 方法1.公式の理解・暗記を徹底する
- 方法2.直前期に本番を意識した過去問・予想問題演習をする
順番に見ていきましょう。
方法1.公式の理解・暗記を徹底する
まず1つ目の方法は「公式の理解・暗記を徹底すること」です。
科目に関わらず基本をマスターすることで、共通テストでも十分点数を取ることができます。
公式を理解・暗記する際は、以下の4段階を意識すると良いでしょう。
- 公式・定石を理解する
- 公式・定石を暗記する
- 暗記したものを使えるように問題演習をする
- 過去問演習で定着させる
日々の学校の授業や講義形式になっている参考書・映像授業を活用して公式を理解したあとは、問題集を使って実際に使ってみましょう。
そして最後に仕上げとして過去問や予想問題集に取り組み、公式を自分のものとして定着させましょう。
方法2.直前期に本番を意識した過去問・予想問題演習をする
2つ目の方法は「直前期に本番を意識した過去問・予想問題演習をすること」です。
先ほどの「方法1.公式の理解・暗記を徹底する」でも過去問の大切さをお伝えしましたが、共通テスト独自の出題形式に慣れるためにも過去問・予想問題をしっかり解きましょう。
その際には以下のステップで取り組むと、本番を意識した演習ができます。
- 時間を測って解く
- 時間を超過したら解けそうな問題は、別の色のペンで解く
- 選ばなかった選択問題があれば、別途時間を確保してすべて解く
- 正解した問題も含めて、解説を読む
- 解答を閉じて、不正解だった問題を再度解く
- 間違った問題の類題にもチャレンジする
- 新たな過去問を解く
- 点数の推移を記録し、順調に伸ばせるようにする
この際に大事なことは「出来るだけ本番を意識して取り組むこと」です。
そのため時間を測ったり、本番同様の解答用紙を用意して解いたり、本番同様の環境で取り組んでみましょう。

共通テスト数学で試験時間内に【正確に】【速く】解くコツ3選
最後に、共通テストの数学で試験時間内に「速く」「正確に」問題を解くためのコツを3つお伝えします。
- 問題後半を見て何の問題かを意識してから問題に取り組む
- 証明問題は選択肢を実際に入れてみる
- 具体的な値を入れてみる
順番に見ていきましょう。
コツ1 問題後半を見て何の問題かを意識してから問題に取り組む
日常生活に根付いた数学から出題されることが共通テストの特徴のため、一見状況説明を含めた問題文が長いことがあります。
問題の後半の方に「何を問いたいのか」が書かれていることが多いため、まず問題の最後の1文をチェックしましょう。
具体的な例をみていきます。
引用:30年試行調査1A 第4問
この状況説明の後半にハッキリと「整数解」という言葉が登場しているため、「整数解」に関する問題であると理解できます。
そして聞かれていることが理解できた上で、具体的な問いをみていきましょう。
引用:30年試行調査1A 第4問
コツ2 証明問題は選択肢を実際に入れてみる
共通テストでは、証明問題は穴抜き問題であることが多いです。
そのため選択肢を実際に入れてみると、明らかに間違っているもの・正しいものをはっきりと見極めることができます。
悩んだら実際に選択肢を入れて、考えてみると良いでしょう。
コツ3 具体的な値を入れてみる
コツ2と似ていますが、答えがわからない時は具体的な値を入れて考えるのも良い方法です。
引用:試行調査30年度1A第1問[2]
この問題では操作Aを考えるためにp=1、q=-1、と固定して、aを1、2、3と動かしてみると、問題が解きやすくなります。
共通テスト数学の勉強法まとめ
本記事では以下の内容を解説しました。
- 2025年の共通テストの問題形式・出題範囲・点数配分
- 共通テスト数学の特徴2点
- センター試験・新課程の共通テスト数学の違い
- 共通テスト数学で高得点を取る方法2選
- 共通テスト数学で試験時間内に正確に速く解くコツ3選
本記事を参考に共通テスト数学を理解し、ここで解説した対策やコツを取り入れて勉強してみてください。
きっと志望校合格にぐっと近くなるはずです。
あなたの志望校合格を応援しています!
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。












