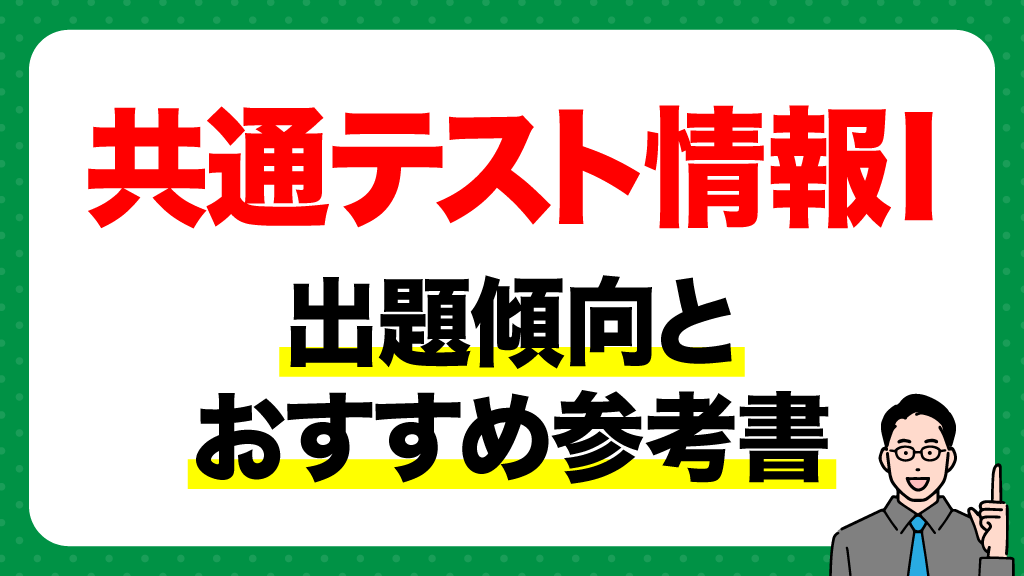
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
共通テストの「情報Ⅰ」は、国立大学を志望している人のほとんどが大学受験で必須の科目です。
多くの人は「情報Ⅰ」を高1のうちに習い終えて、それからしばらくノータッチという状況かと思います。
ですが「本当に受験直前まで触れなくても大丈夫なのか」、そして「勉強するとしたら、どんな教材でどうやって勉強すればいいのか」など気になりますよね。
本記事では、共通テストに追加された2025年度の情報Ⅰの問題の概要や、情報Ⅰの勉強法を紹介します。
「情報Ⅰ」はどんな科目?

「情報Ⅰ」は、2022年入学の高校生から新しい学習指導要領で指導され始めて、その高校生が3年生になった2025年度の共通テストから出題されるようになりました。
2022年からの「情報Ⅰ」は、それまでの「社会と情報」「情報の科学」という2教科が再編集されて必修化されています。
「情報Ⅰ」で習う単元は、以下のようなものです。
| 単元 | 内容 |
|---|---|
| 情報社会の問題解決 | メディアの特性・著作権やプライバシーについてなどの情報リテラシーにまつわる内容 |
| コミュニケーションと情報デザイン | コミュニケーション手段やデジタル表現についてなどの情報デザインに関する内容 |
| コンピュータとプログラミング | コンピュータの仕組み、プログラミング・アルゴリズムについての内容 |
| 情報通信ネットワークとデータの活用 | インターネットの仕組み、データの形式やデータモデル、分析と利用についての内容 |
授業では、これらの単元を教科書で習うだけではなく、パソコンを使ってプログラミングやデータ分析を実践します。
情報Iが共通テストに追加された理由
情報化社会における基本知識を学ぶ必要があるとして「情報Ⅰ」が重要視されるようになりました。
現在、AIの発達やIoT(モノをインターネットとつなぎ、制御されること)の普及により、情報化が急速に進んでいます。今後の社会で活用していく知識の基本として、高校では「情報Ⅰ」が必修化されています。
高校教育で必修化されたことや、大学に進学した際に必要となる学部もあることから、「情報Ⅰ」が共通テストにも追加されることとなりました。
2025年度共通テスト「情報Ⅰ」の出題内容について

2025年度の共通テストで出題された「情報Ⅰ」の設問構成や配点、大問ごとの出題内容について説明します。
「情報Ⅰ」は、2025年度共通テストから共通テストから出題されるようになりました。共通テストの最新情報をお伝えします。
共通テスト「情報Ⅰ」の大問別出題内容と配点
2025年の共通テストの「情報Ⅰ」は、以下の表のような出題内容と配点でした。
| 大問 | 内容 | 設問数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小問集合 | 8 | 20 |
| 2 | 領域複合 | 11 | 30 |
| 3 | コンピュータとプログラミング | 12 | 25 |
| 4 | 情報通信ネットワークとデータの活用 | 9 | 25 |
大問1・2は、領域を問わず出題されています。大問3の「コンピュータとプログラミング」と大問4の「情報通信ネットワークとデータの活用」は、共通テスト前に発表されていた試作問題と同じ範囲からの出題です。
いずれにせよ、大問1・2では、さまざまな範囲から出題されるため、情報Ⅰの内容はすべておさえておく必要があります。
ここから、大問別の詳しい出題内容を説明します。
大問1|小問集合
2025年度共通テストの小問集合では、以下の内容が出題されました。
- 問1…デジタル署名の目的と128ビットIPアドレス導入の目的
- 問2…7セグメントLEDの表示について
- 問3…チェックディジット
- 問4…パソコンのマウスカーソルの移動
問1は基本的な知識を問う問題、問2以降は問題文をしっかり読んで理解してから解答する必要がある問題が出題されました。
難易度は易しいものが多く、問題文を読んで理解すれば解けます。問題文を「速く」「正確に」読み解く練習をしておきましょう。
大問2|領域複合
大問2は、大問1と同じくさまざまな領域から複合した問題が出題されました。大問1とは異なり、大きい設定が置かれていて、問題を読みとく読解力がより必要な問題です。
大問2は、AとBにわかれており、出題領域は以下の通りでした。
- A…情報通信ネットワークとデータの活用
- B…モデル化とシミュレーション
Aは、会話文とレシートが設定として置かれました。レシートの内容を読み取り、解答する必要があります。
Bは、スーパーマーケットの買い物という身近なシチュエーションを題材に、システムの理解やデータの活用方法などを問う問題でした。複数回行うシミュレーションでは、結果にばらつきがあることなどを理解して解く必要があり、文章を読み取る力が求められます。
AとBともに、難易度は高くありませんでした。しかし、知識があるだけでは解くことができないので、知識を活用して問題にあてはめて解く必要があります。
問題演習を重ね、問題文を読み取る力をしっかりとつけておけば、本番でも問題なく解けるでしょう。
大問3|コンピュータとプログラミング
大問3は、「プログラミング」に関する問題が出題されました。
問1は、情報を整理し、場面設定を理解する問題です。問2は単純なプログラミング、問3はやや複雑なプログラミングの問題が出題されました。
問3まで、問1の場面設定を理解しておかなければ解けない問題が続きます。
コードやスクリプトを知っておくだけでなく、プログラムをつくるまでの考え方が問われており、プログラミングが得意でも手間取ってしまう問題がふくまれています。
共通テスト「情報Ⅰ」のなかでは、大問3が最も難問です。プログラミングを重点的に対策する必要があります。
大問4|情報通信ネットワークとデータの活用
大問4は、地方や都道府県ごとの旅行者数に関するさまざまなデータを読み取る問題です。
表やグラフを読み取る力が求められます。
全体を通して、さまざまなデータをもとに、分析をする問題が出題されています。
数学で学習する散布図や箱ひげ図の知識が必要です。データ解析の問題は、数学でも出題されるため、数学の学習ができている人なら解きやすい問題です。
実際のデータを見ながら、情報を整理していく練習をしておく必要があります。
難易度は、標準レベルでした。
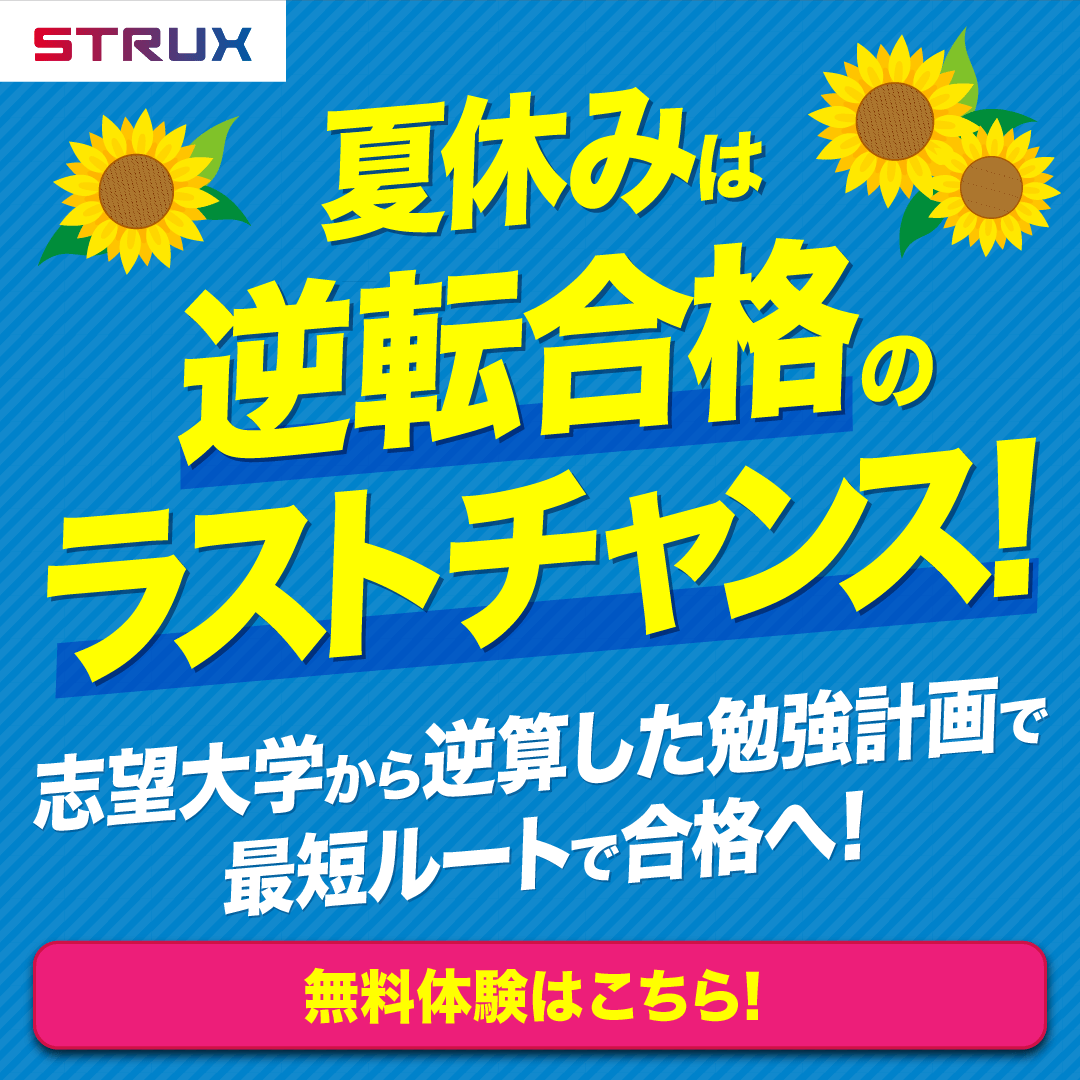
2025年度の問題は簡単だったが今後も簡単とは限らない
2025年度の共通テストで「情報Ⅰ」が、はじめて出題されたこともあり、受験生からは「簡単だった」という意見が多くありました。
問題も難問が少なく、全体を通して解きやすいものでした。
しかし、2026年度入試でも同じように易しい問題となるとは限りません。
初年度ということもあり、2025年度入試だけ易しかった可能性も考えられるため、しっかりと対策を進めてください。
共通テストに向けた勉強の進め方

ここでは、共通テスト「情報Ⅰ」の勉強を始める時期や、勉強の進め方を説明します。
共通テストで出題されるようになって時間が経っていないため、出版されている参考書は少なめです。現状、「とりあえず出版している」という内容の浅い参考書も少なくないので、共通テスト対策につながる参考書を見極める必要があります。そのなかでおすすめの参考書を紹介します。
高3の夏休みごろから対策をはじめるのがベスト!それより遅くても問題ない
「情報Ⅰ」が共通テストで出題されるようになって、間もないということで不安になる人も多いと思いますが、対策は高3の夏休みからでも十分です。
「情報Ⅰ」は共通テストでしか出題されない上、入試全体の配点のうち5%以下の大学が多いため、重要度は低いといえます。
英語や数学の対策をして、点数を伸ばしていく方が受験において遥かにいい戦略です。
インプットからはじめて問題演習をしていく
「情報Ⅰ」の勉強は、まずインプットからはじめて、それから問題演習を進めましょう。
映像授業や参考書で基礎的な内容をインプットします。
問題演習をすると、インプットした内容を記憶に定着させ、テストで点数を取れるようになります。
インプット用のおすすめ教材3選
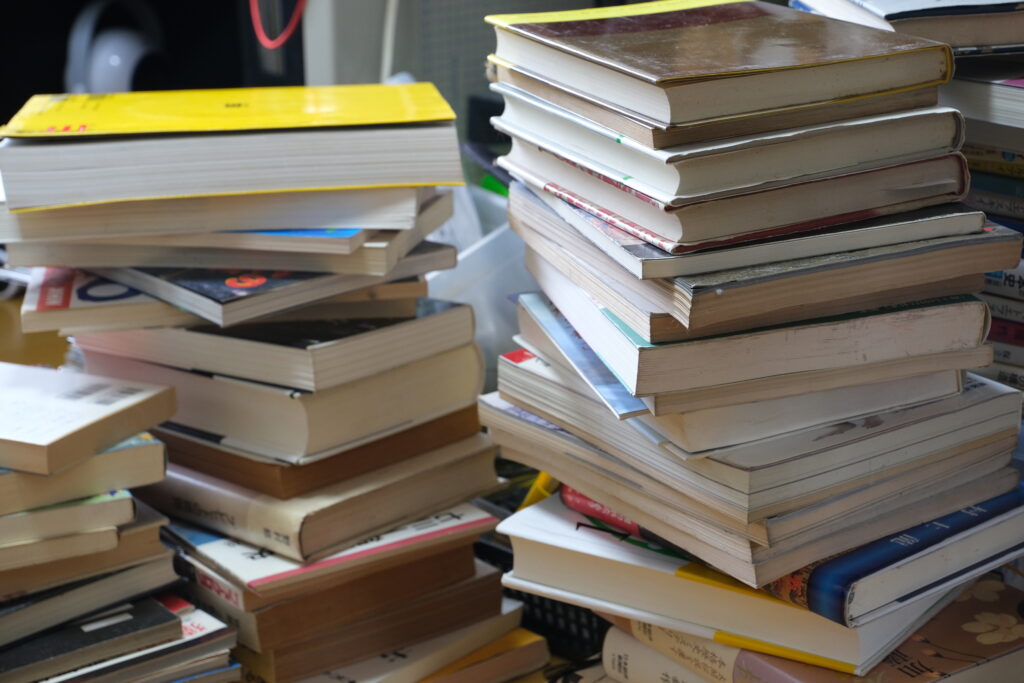
インプットの勉強には、映像授業を使う方法と参考書を使う方法の2種類があります。
映像授業のおすすめ教材1つと、参考書のおすすめ教材を2冊紹介します。
- インプットにおすすめの映像授業|スタディサプリ
- インプットにおすすめの参考書|ゼロから始める情報Ⅰ
- 理系科目が苦手な人におすすめの参考書|高校の情報Ⅰが1冊でしっかりわかる本
紹介した教材のなかで、手軽に全範囲を網羅できる「スタディサプリ」を使った勉強法がとくにおすすめです。
インプットにおすすめの映像授業|スタディサプリ
スタディサプリの「ベーシックレベル情報Ⅰ」は、約15時間という短い時間で、全範囲の授業を受講できるため基本的な内容を短期間で網羅したい人におすすめです。
スタディサプリを使った勉強の手順は以下の通りです。
- テキストを印刷する
- コピーしたテキストに重要なことを書き込みながら映像授業を受ける
- 受講後、問題を解く
- 間違えた問題の動画を再度視聴する
スタディサプリを使った勉強では、「動画を見た直後に問題を解く」「わからないところで悩まない」ことを意識してください。動画を見た後に問題を解くことで、動画で習った内容が頭に入っているか確認することが重要です。また、インプットの勉強なので、悩む問題があったら飛ばして、「とりあえず終わらせる」意識で進めてください。
インプットにおすすめの参考書|ゼロから始める情報Ⅰ
授業を聞いて内容を理解するのが苦手という人は、「ゼロから始める情報Ⅰ」を使って基本の内容を理解してください。1日30分の勉強で10ページずつ進めると、約30日間で終わります。
「ゼロから始める情報Ⅰ」1冊で「情報Ⅰ」の全範囲をインプットできるのでおすすめです。
理系科目が苦手な人におすすめの参考書|高校の情報Ⅰが1冊でしっかりわかる本
数学などの理系科目が苦手な人は、「高校の情報Ⅰが1冊でしっかりわかる本」を使って基本の内容を理解してください。1日30分の勉強で10ページずつ進めると、約14日間で終わります。
「高校の情報Ⅰが1冊でしっかりわかる本」では「情報Ⅰ」の基礎的な問題を勉強できるのでおすすめです。
ただし、簡単な内容しか掲載されていないため、1冊すべて終わらせてもインプットは不十分だと考えておいてください。
問題演習用おすすめ問題集2選
インプットが終わったら、アウトプットをして内容を定着させましょう。
全範囲の問題をひと通り掲載|ベストフィット情報Ⅰ
「ベストフィット情報Ⅰ」は、問題演習をしてアウトプットをするのにおすすめの問題集です。
問題数は多いですが、「情報Ⅰ」で高い点数を取っておきたい場合は、ひと通り終わらせておくことをおすすめします。
全範囲の問題をひと通り掲載|マーク式基礎問題集、共通テスト総合問題集
「ベストフィット情報Ⅰ」が終わったら、河合塾の「マーク式基礎問題集情報Ⅰ」や「共通テスト総合問題集情報Ⅰ」を解いてください。
とくに、「共通テスト総合問題集」は、共通テストの問題に慣れておくために解いておくことをおすすめします。
「ベストフィット情報Ⅰ」が終わった時期が、12月ごろで入試まで時間がなければ、「共通テスト総合問題集情報Ⅰ」だけでも解いておいてください。
解いていてわからない分野があれば、適宜「ベストフィット情報Ⅰ」に戻って勉強しなおしましょう。

時間がない人向け最短での勉強法
「入試まで時間がない」や「情報Ⅰは60点取れれば問題ない」という人に向けて2~3か月でできる最短ルートでの勉強法を説明します。
最短ルートでの勉強法は、インプットとアウトプットで、2冊の参考書に取り組んでください。
インプットは「きめる!共通テスト情報Ⅰ」を使います。
「きめる!共通テスト情報Ⅰ」は、今売られている参考書のなかでは解説が丁寧に書かれていてわかりやすいのが特徴です。短期間で最低限の内容をインプットするのに最適です。
アウトプットは入試直前期に、「共通テスト総合問題集」を解いておきましょう。
浪人生も「情報Ⅰ」の勉強は必要
浪人生も現役生と同じく、「情報Ⅰ」を受験する必要があります。
2025年度の受験で「情報Ⅰ」を受けた浪人生は、そのまま勉強を続けてください。
また、2025年度の受験では、移行措置問題として、旧課程の範囲の問題が用意されていましたが、2026年度からはありません。
2025年度に移行措置問題を受けた受験生は、新たに「情報Ⅰ」の対策が必要です。2024年以前の卒業生は、授業でも習っていない内容が「情報Ⅰ」で出題されます。
塾での勉強では足りないようなら、「スタディサプリ」で、教科書理解の勉強から始めるのをおすすめします。
「情報Ⅰ」は3年生の夏休みからの対策で十分
共通テストの「情報Ⅰ」は、配点が低いこともあり、他の教科に比べて重要視しなくても問題ありません。
対策は、3年生の夏休みからで十分です。
共通テストに追加されたばかりで、販売されている参考書は多くありません。
今販売されている参考書のなかから、インプット用の参考書と問題演習用の問題集を選んで勉強を進めてください。
「60点を取れればいい」という人は、インプット用と問題演習用で1冊ずつ対策をすれば最低限の力は身につきます。
しかし、問題演習の量が足りない場合があるので、問題演習だけでも2冊以上勉強しておくことをおすすめします。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。
















