*紹介している教材にはプロモーションを含みます
医学部受験の合否を分ける科目である物理。そんな物理は多くの受験生が選択する科目ですが、その難易度の高さや特有の出題傾向から、対策に悩む方も多いでしょう。
この記事では、医学部物理で高得点を獲得するための勉強法を、基礎固めから応用力強化、過去問対策まで段階的に解説します。
さらに、学習効果を高めるためのおすすめ参考書も3冊厳選して紹介します。医学部合格を目指す受験生が物理を得点源とするための具体的な戦略を提供するので、ぜひ最後までご覧ください。

医学部物理の難易度と特徴

医学部物理の攻略には、まず難易度と特徴を正確に把握する必要があります。他学部の受験と比較してどのような点が異なり、どのような分野が頻出するのでしょうか。そして、大学ごとにみられる傾向の違いについて解説します。
医学部物理の一般的な難易度と他学部との違い
医学部の理科は、個別試験において、2科目を受験する必要があります。物理を選択する場合は、物理のほかに化学の対策が必要です。
物理の問題は、化学に比べて短時間で解答できる問題が多いため、化学の解答時間を確保するためにも、正確かつ迅速に解答していく必要があるので理解しておきましょう。
<h3>医学部物理特有の出題傾向や頻出分野とは</h3>
医学部の物理では、基礎から応用にいたるまで、幅広い難易度の問題が出題されます。さらに、問題設定が複雑であったり、複数の分野の知識を融合させて解く必要があったりするため、総合的な実力が問われるでしょう。
したがって、医学部物理を攻略するには、表面的な理解にとどまらず、物理の本質を深く理解し、それをさまざまな状況に対応できる力を養う必要があります。
<h3>大学ごとの出題傾向の違い</h3>
医学部の物理といっても、大学ごとに出題傾向は異なります。標準的な問題を素早く正確に解く計算力が重視される場合もあれば、思考力や応用力が試されるケースもあります。
また、特定の分野を重視する大学や、論述問題・描図問題を好んで出題する大学も存在するなどさまざまです。したがって、高得点を狙うためには、早い段階から志望校の過去問を分析し、志望校特有の出題傾向を把握したうえで、的を絞って対策する必要があります。

<h2>医学部物理の勉強法</h2>

医学部物理で高得点を獲得するためには、戦略的に学習を進める必要があります。基礎力の徹底的な強化、応用力・実践力の養成、最終的には試験本番で実力を最大限に発揮するための対策へと、段階的に学習を進めていきましょう。
ここでは、それぞれのステップにおける具体的な勉強法を解説します。また、以下の記事で、物理の特徴や全体像を紹介しているので、あわせてご覧ください。
入試を解くための基本!物理の特徴や全体像、具体的な勉強ステップなどを解説!
<h3>基礎力強化</h3>
医学部の物理を攻略するために、まずは物理の基礎知識を盤石にしましょう。じつは、応用問題や複雑な問題も基本的な物理法則や公式の組み合わせで成り立っている場合がほとんどです。基礎が曖昧なままでは、応用問題に対応できなくなってしまいます。
医学部の物理で高得点を目指すためには、高校2年のうちに全範囲の学習を終えるようにしましょう。そのうえで、各公式の暗記や、各実験の実施意図の理解を進めてください。
基礎的な学習を進める際は、学校で配布される「セミナー」「リードα」や「物理のエッセンス」などがおすすめです。
このように、基礎概念の深い理解と、基本的な問題パターンの定着こそが、その後の応用力養成への土台になります。「教科書の内容だけでは不安」「自主学習でどんどん先に進みたい」そのように考えている受験生には、リクルートが提供するオンライン学習サービス「スタディサプリ」がおすすめです。
以下の記事で、おすすめのポイントを紹介しているので、ぜひチェックしてください。
『スタディサプリ「高3スタンダードレベル物理」』は物理の基礎を固めるのにオススメ!正しい使い方や注意点なども解説
<h3>応用力・実践力強化</h3>
基礎力が固まったら、次に応用力・実践力を強化する段階に進みます。医学部の入試では、単なる知識の確認にとどまらず、初見の問題に対する対応力や複数の知識を組み合わせて解答を導き出す力が求められます。
まずは「名問の森」「重要問題集」などを活用し、演習問題を自力で解けるかチェックしてみましょう。
問題を解く際は、必ず自分で計算するクセを付けてください。また、問題を解き終えた後は、解説を熟読し、自分の考え方と合っているか確認しましょう。特に、複数の分野にまたがる融合問題や、設定が複雑な問題に積極的に挑戦してください。
<h3>試験本番を想定した対策</h3>
さいごに、試験本番で実力を最大限に発揮するために、試験を想定した対策を実施します。
物理の試験は「小問1の結果を用いて、小問2を解く」といった形式が多いため、最初の小問でミスをすると、その大問が全問不正解になってしまいます。
途中の計算はみやすいように残しておき、大問の途中で違和感があれば、すぐに前の小問に戻れるように、普段の演習から意識しておきましょう。さらに、本番同様の環境で時間を計って問題を解く練習を定期的に行い、プレッシャーに慣れておく必要があります。
時間管理能力、ミス防止策、そしてプレッシャー耐性を高める訓練を積めば、入試本番で持てる力をしっかりと発揮できるはずです。

<h2>医学部物理の過去問分析</h2>
医学部合格のためには、志望校の過去問分析が欠かせません。過去問は、大学が受験生に求める能力や知識レベルを具体的に示してくれる最も信頼性の高い資料です。ここでは、過去問から頻出分野とその対策を読み解き、過去問演習を効果的に進めるための注意点を解説します。
<h3>過去問からみる頻出分野と対策</h3>
過去問を分析すれば、志望校における物理の頻出分野や出題形式を具体的に把握できます。大問3問構成の出題形式を採用している大学であれば「力学」から1問「電磁気」から1問、残りの単元から1問の構成になっているケースが多いです。
また、大問5問構成の場合は「原子」の単元からも問題が出題されるでしょう。志望大学が、どのような出題形式を採用しているかを確認し、頻出分野を中心に対策してください。
したがって、過去問の詳細な分析に基づき、自分の学習計画を最適化し、志望校の傾向に合わせたピンポイントの対策こそが、合格への近道となるのです。
<h3>過去問を解く際の注意点</h3>
過去問演習は、単に問題を解いて答え合わせをするだけでは十分な効果が得られません。
目的は、時間配分、難易度、出題形式への順応、弱点の特定や克服にあるからです。
過去問を解く際は、必ず本番と同じ制限時間を設けて取り組みましょう。これにより、時間内に解き切るペース配分や、問題の取捨選択の判断力を養えます。解き終わった後は、採点だけでなく「なぜ間違えたのか」「どうすれば解けたのか」を徹底的に分析しましょう。
解答プロセスを振り返り、知識不足、思考力不足、計算ミスなど、ミスの原因を特定し、ミスの原因を排除するための具体的なアクションプランを立ててください。また、古い過去問だけでなく、最新の傾向をつかむために、できるだけ直近の数年分は必ず解くようにしましょう。
このように、時間を意識した実践的な演習と、解きっぱなしにしない徹底的な復習・分析が過去問演習の効果を最大化するポイントです。
<h2>医学部物理におすすめの参考書</h2>
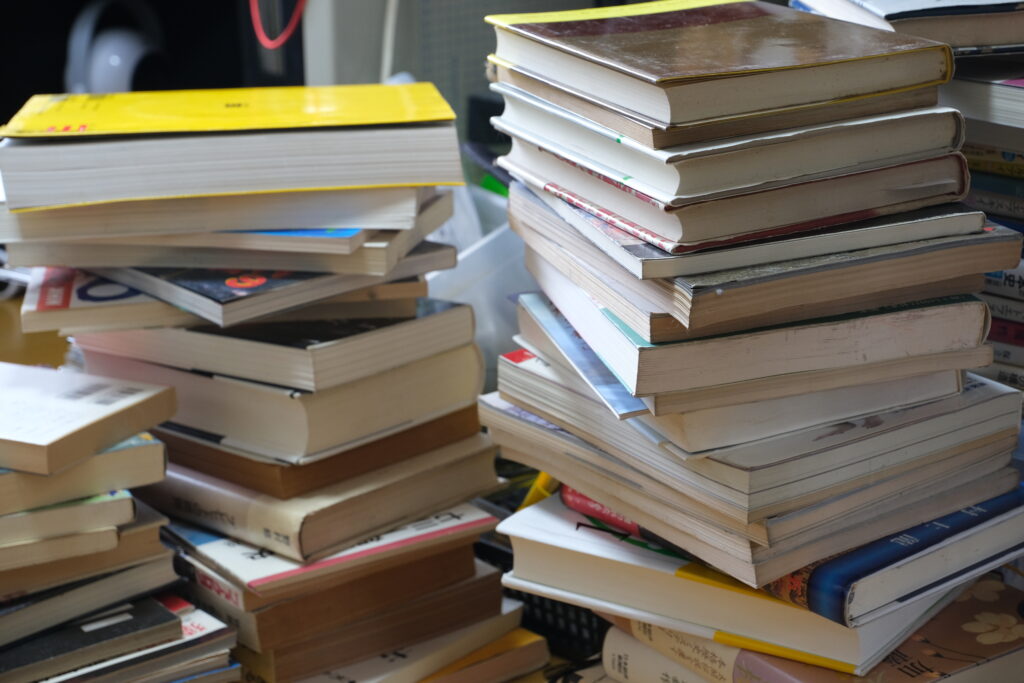
医学部物理の学習を進めるうえで、適切な参考書選びは非常に重要です。自分のレベルや目的に合った参考書を使用すれば、学習効率は格段に向上します。ここでは、基礎固めから応用力養成まで、医学部受験生に広く支持されているおすすめの参考書を3冊紹介します。
<h3>おすすめ参考書1:『物理のエッセンス』(河合出版)</h3>
『物理のエッセンス』は、医学部物理の基礎固めに最適な参考書として、多くの受験生に支持されています。物理現象の本質を初学者にもわかりやすい言葉で解説しており、公式の丸暗記ではなく、根本的な理解を促す構成になっているため、おすすめです。
また、図やイラストも豊富で、視覚的に理解しやすい工夫がされています。各項目には基本的な確認問題が付いており、学んだ知識をすぐにアウトプットできるため、効率的に知識の定着が可能です。
医学部物理で求められる深い理解の土台を作るために、まずこの参考書を徹底的に読み込み、内容を完全にマスターしましょう。
<h3>おすすめ参考書2:『名問の森 物理』(河合出版)</h3>
『名問の森物理』は、基礎が固まった後に、応用力・実践力を養成するための問題集として非常に評価が高い一冊です。
医学部入試で実際に出題されるレベルに近い、基礎問題や応用問題が豊富に収録されており、問題解決能力を鍛えるのに適しています。
力学・熱・波動I編と波動II・電磁気・原子編の2冊構成で『物理のエッセンス』で培った基礎知識を、実際の入試問題でどのように活用するのかを理解できます。このように、基礎学習を終え、さらなるレベルアップを目指す受験生にとって、最適な問題集といえるでしょう。
<h3>おすすめ参考書3:『重要問題集物理』(数研出版)</h3>
『重要問題集物理』は、幅広いレベルの問題を網羅しており、基礎から応用への橋渡し、そして実践的な演習までを1冊でカバーしたい受験生におすすめです。
全国の大学入試問題から、重要度が高く、学習効果の高い問題が厳選されており、物理の総合力を高められます。それぞれの問題は、難度別に分けされているため、自分の実力に合わせて問題を選び、段階的にステップアップできます。
したがって、基礎事項の確認から入試レベルの実践演習まで、腰を据えてじっくりと取り組みたい受験生や、さまざまな大学の入試問題に触れておきたい受験生にとって、非常に頼りになる一冊といえるでしょう。

<h2>生物と物理の選択はどちらがオススメ?</h2>
医学部受験において、理科の選択科目として生物と物理のどちらを選ぶべきかは、多くの受験生が悩むポイントであり、一概にどちらが有利とは言えません。物理、生物のメリット、デメリットは以下のとおりです。
| 科目 | メリット | デメリット |
| 物理 | ・理解すれば応用が効く・暗記量が少ない・高得点を狙いやすい | ・小問で間違うと大問すべて不正解に なるリスクがある。 |
| 生物 | ・暗記が得意であれば得点しやすい・入学後の勉強に役立つ | ・暗記が多い・思考力や考察力が問われる |
最終的には、自分の学力特性、興味関心、志望校の入試科目と過去問の傾向を考慮して、自分にとって最も得点しやすいと判断できる科目を選択するのがよいでしょう。
<h2>まとめ</h2>
医学部物理で高得点を取るためには、以下のポイントが重要です。
- 医学部物理の難易度把握
- 出題傾向の理解
- 段階的な勉強法の実践
- 過去問分析を通じた志望校対策の充実
特に、高校での学習範囲の早期完成、そして大学ごとの傾向に合わせた対策が合否を分けます。この記事で紹介した勉強法や参考書を参考に、戦略的に学習を進め、医学部合格をつかみ取ってください。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。



















