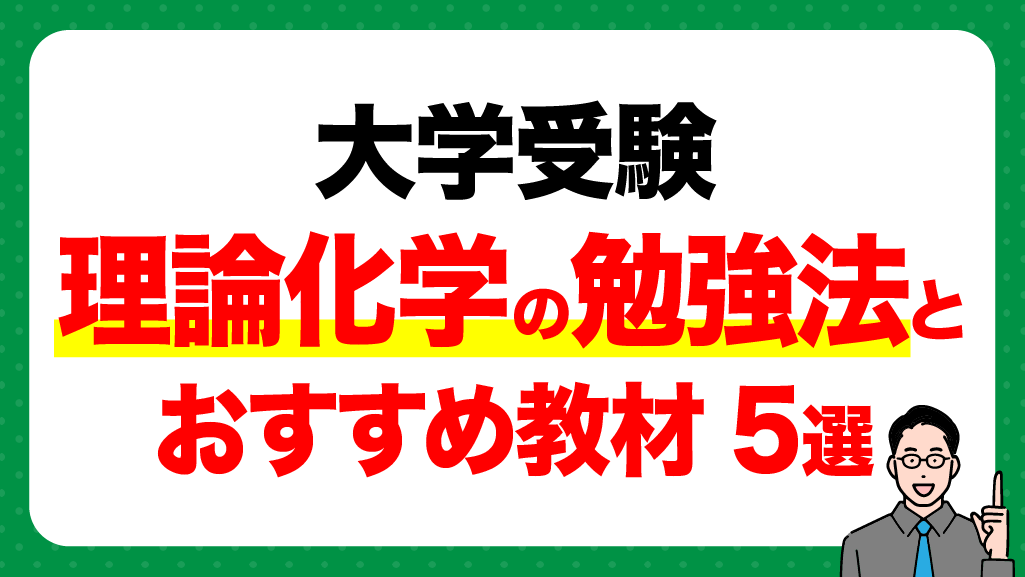
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
高校化学において、理論分野は多くの受験生が難しいと思う単元です。「化学が不得意だ」という意識を持つ受験生のなかには、この理論分野でつまずいた経験がある方も多いはず。
しかし、理論分野を乗り越えられれば、無機化学や有機化学といった他の分野の学習が非常にスムーズに進みます。理論分野は化学全体の基礎を形成する要素が多いため、まずはこの分野の確実な理解を目指しましょう。
この記事では、化学学習における理論分野の重要性や、学習を進める上でのポイントを詳しく解説します。

大学受験における理論化学の特徴

大学受験の理論化学は、物質の構造、状態、変化を支配する法則や原理を深く掘り下げます。原子構造、化学結合、熱化学、化学平衡、反応速度などが主な範囲です。
最大の特徴は、法則や定義の正確な理解を前提とした計算問題が多い点にあります。単なる公式暗記では対応できず「なぜそうなるのか」という現象の根本原理を理解し、応用する思考力が強く求められます。
このように、理論化学は、無機化学・有機化学の基礎となる重要な分野であり、基礎知識の定着と問題演習による計算力・応用力の養成が求められる分野です。
大学受験における化学の理論分野が重要な理由

高校化学は大きく「理論」「無機」「有機」の3分野に分類されますが、なかでも理論分野が特に重要視される理由は次の2点です。
- 理論分野の知識が、無機・有機分野の理解と深く関連しているため
- 大学入試において、理論分野からの出題が多く、配点比率が高い傾向にあるため
上記の理由について、以下で詳しく解説します。
理由1:理論分野は無機や有機に関連する単元を含むから
理論分野には「無機化学や有機化学に直結する基礎的な単元」と「理論分野として独立して扱われることが多い応用的な単元」が存在します。
特に重要となるのが前者、すなわち「無機・有機の問題にも直接関係する基本的な単元」です。具体的には以下の項目が挙げられます。
- 濃度の概念と計算
- 中和反応の原理と量的関係
- 酸化還元反応の原理と量的関係
これらの単元に対する理解が不足していると、無機化学や有機化学の分野でつまずいてしまう原因になってしまいます。
例えば、無機化学で登場する「金属の精錬」プロセスは、酸化還元反応の知識を前提としています。また「一定量の鉄鉱石からどれだけの鉄が得られるか」といった量的計算も頻繁に求められるのが特徴です。
このように、理論分野の計算問題は、無機・有機の両分野で応用されるスキルであり、理論化学の範囲で習得する内容なのです。高校化学をスムーズにマスターするためには、まずは、理論分野をしっかり押さえておきましょう。
理由2:入試では理論分野の配点が高いケースが多いから
大学入試問題における化学の問題では、理論分野が出題の中心となり、配点が高く設定されている傾向にあります。例として、2023年度の大学入学共通テスト(化学)の配点構成を見てみましょう。
- 第1問:理論(20点)
- 第2問:理論(20点)
- 第3問:無機(20点)
- 第4問:有機(20点)
- 第5問:理論&無機(20点)
この配点からも、理論分野に関連する問題が全体の半分近くを占めていることがわかります。なぜ理論分野の出題比重が大きくなるのでしょうか。
その理由は理論分野が単元ごとに難易度のバリエーションを持たせやすい分野であることや各単元がある程度独立している点にあります。そのため、問題作成者は多様な形式・難易度の問題を構築しやすいのです。
例えば、以下のように難易度に応じて、独立した大問を設定可能です。
- 基礎レベル: 原子構造、分子の電子配置
- 標準レベル: 中和計算、酸化還元計算
- 応用レベル: 化学平衡(平衡定数、移動原理)
これに対し、無機分野はテーマによる難易度の差が比較的小さく、無機知識のみで難度の高い大問の作成が困難です。難度を上げるには理論分野の知識と融合させる必要があるため、結果的に理論分野の比重が高まります。
また、有機分野では、その性質的に基礎的な知識を問う問題の作成が困難という事情もあります。これらの事情から、必然的に理論分野からの出題が豊富になり、配点も高くなる傾向が見られるのです。
理論化学をマスターするための勉強法!

理論分野は高校化学の根幹を成すため、苦手意識を持ったまま放置しないようにしましょう。理論分野を得意科目にできれば、模試や本番の入試で安定した得点が期待できます。具体的な勉強法は以下のとおりです。
- 教科書レベルの完全理解
- 基本問題による演習
- 応用・発展レベルの問題演習
- 過去問を用いた総合演習
それぞれのステップを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
ステップ1:教科書レベルの完全理解
まず、教科書や授業で扱われる基本的な概念、法則、公式を深く理解するところから始めましょう。基礎を理解せず、表面的な暗記に頼ると、問題集の解説が理解できなかったり、入試で少しひねられた問題に対応できなくなったりします。
学校の授業だけでは理解が難しい場合は「スタディサプリ」のような映像教材を活用するのも効果的なので、ぜひ試してみてください。教科書理解の具体的な勉強法については、以下の記事でも解説しています!
ステップ2:基本問題による演習
基礎知識をマスターしたら「セミナー化学」や「リードα」といった、教科書傍用問題集を用いて、基本的な問題演習に取り組みます。理論分野は計算問題が多いため、実際に自分の手を動かして解くようにしましょう。自ら計算すれば、知識が定着しやすく、実践的な計算力が養われます。
ステップ3:応用・発展レベルの問題演習
基本問題がスムーズに解けるようになれば、MARCHや関関同立レベルの大学であれば、過去問でもある程度の得点が見込めます。旧帝大や早慶など、さらに難度が高い大学を目指す場合は「化学重要問題集」のような、より難易度の高い問題集に挑戦し、応用力を磨きましょう。
問題演習の具体的な勉強法については、以下の記事でも解説しているのでチェックしてください。
ステップ4:過去問を用いた総合演習
ひととおりの問題演習が終わったら、志望校の過去問演習に入ります。ただし、入試問題は理論・無機・有機が組み合わされているケースも多いため、過去問演習は無機化学と有機化学の学習もひととおり終えてから着手するのが効果的です。理論分野だけを切り出して過去問演習を行うのは、非効率なので注意しましょう。
理論化学攻略におすすめの教材5選
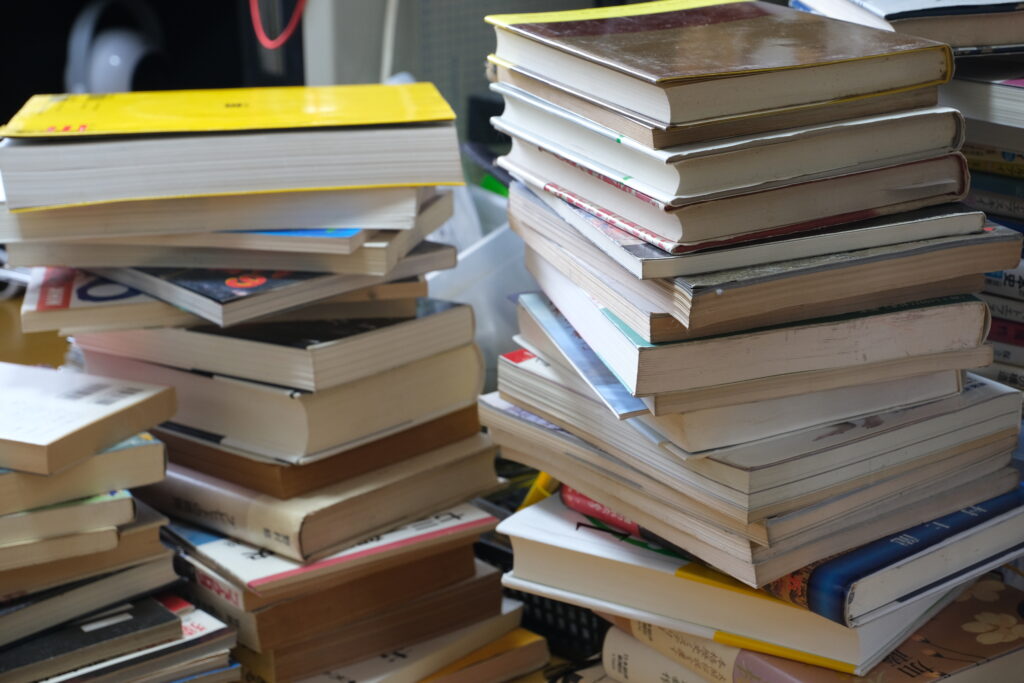
理論化学を攻略するには、段階を踏んで学習を進める必要があります。ここでは、それぞれの学習段階や目的に合わせて効果を発揮する、おすすめの教材を5つピックアップして紹介します。動画教材から講義系参考書、問題集まで幅広く取り上げるので、ぜひご覧ください。
おすすめ教材1:スタディサプリ
スタディサプリは「学校の授業だけでは理解が追いつかない」「学校の授業に先がけて予習したい」と感じている受験生におすすめしたい動画学習サービスです。
プロ講師の分かりやすい解説により、理論化学の基礎を効率的かつ深く理解できるでしょう。スタディサプリのおすすめポイントは以下の記事で詳しく解説しています。
おすすめ教材2:「セミナー化学」「リードα」(教科書傍用問題集)
「セミナー化学」や「リードα」といった教科書傍用問題集は、学校の授業で学んだ知識を定着させるために最適な教材です。これらの教材は、教科書レベルの基本的な問題から標準的な入試問題まで幅広く網羅しており、日々の学習や定期テスト対策に欠かせません。
学校の授業の内容を押さえつつ、疑問点があれば「スタディサプリ」で復習するというサイクルがおすすめです。「セミナー化学」や「リードα」は、理論化学の基礎を固めたい受験生にとって、必須といえるでしょう。
おすすめ教材3:橋爪のゼロから劇的にわかる理論化学の授業 改訂版
「橋爪のゼロから劇的にわかる理論化学の授業」は、理論化学に強い苦手意識を持っている受験生にとって、救世主となり得る講義形式の参考書です。この参考書の最大の魅力は、著者の橋爪先生が親しみやすい口調で解説を進めてくれる点にあります。
抽象的で難解に感じがちな理論化学の概念も、豊富な図解や身近な例え話を交えながら解説しているので、直感的にイメージしやすく、知識が定着しやすいでしょう。「橋爪のゼロから劇的にわかる理論化学の授業」は、苦手克服のための再入門書として、頼りになる一冊です。
おすすめ教材4:鎌田の理論化学の講義 三訂版
「鎌田の理論化学の講義」は、大学受験における化学対策の定番参考書です。理論化学の基礎から応用、そして発展的な内容までを網羅した、非常に信頼性の高い講義系参考書といえるでしょう。
こちらの参考書は、理論化学の各分野が体系的に整理され、非常に詳しく丁寧に解説されています。本書で学習を進めていけば、各分野の関連性や、理論化学の本質を深く理解できるでしょう。ある程度の基礎力があり、より深い理解と応用力を身につけたい受験生に最適です。
おすすめ教材5:化学重要問題集
「化学重要問題集」は、入試標準レベルから応用・発展レベルまでの良質な問題を豊富に収録しています。基礎的な参考書や教科書傍用問題集をひととおり終えた受験生は、こちらの参考書を用いて入試本番に向けてアウトプット能力を高めるのに最適です。
まとめ
大学受験における化学の基礎となる理論分野。そんな理論分野に対して「とっつきづらい」と感じている人も多いでしょう。しかし、理論分野で学ぶ知識は、無機化学や有機化学を理解するための基礎となるため、避けては通れない重要なセクションです。
加えて、入試における配点が高い傾向にあるため、得点源とするためにしっかりと知識を習得しておく必要があります。学習を進めるにあたっては、本記事で紹介したステップを意識し、段階的にマスターしていきましょう。本記事が、受験生のみなさんの一助となれば幸いです。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。

















