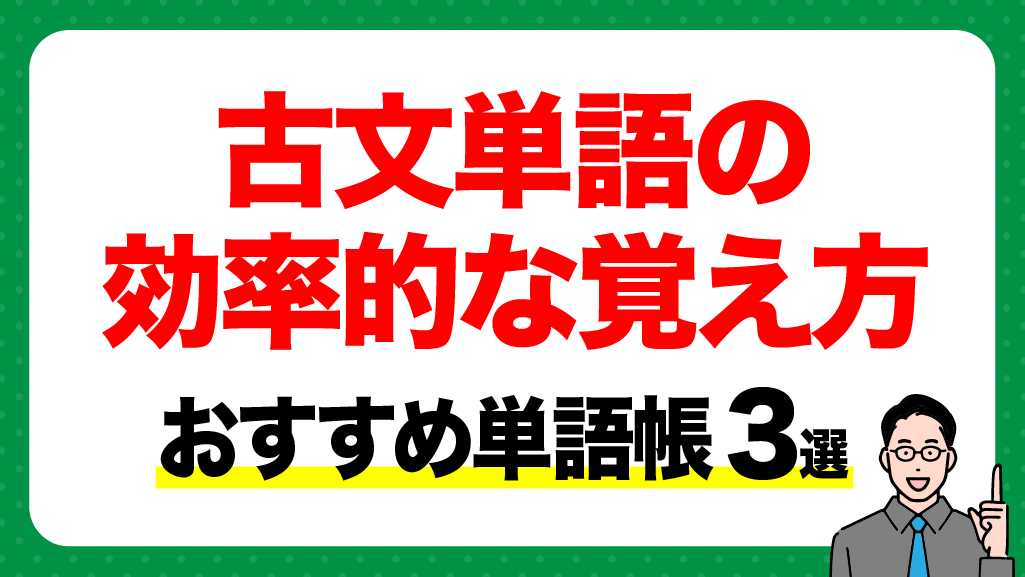
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
古典の勉強において避けられないのが単語の勉強です。単語の習熟度が古文の出来を左右しているといっても過言ではありません。
しかし「どうやって覚えたらいいの?」「どれくらい覚えればいいの?」という悩みを抱えている人も多いでしょう。
この記事では古文の単語知識ゼロから早慶や東大レベルの実力にまで持っていくための勉強法をご紹介します。誰にでもできる暗記のコツを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
こちらの動画もぜひご覧ください。

古文単語の覚え方|効率的な暗記方法
とっつきにくいイメージがある古文単語。しかし、英単語のように2000単語も覚える必要はなく、300単語程度の暗記である程度の文章は読めてしまいます。難関大を目指す場合でも、最大600単語を暗記すれば、十分高得点が狙えるでしょう。
現代語と似ている意味の言葉や、現代の言葉の語源になっている単語も多いため、英単語よりも暗記のハードルは低いのです。とにかく、単語帳1冊をきちんと覚えきるという意識を持って頑張りましょう。

古文単語の効率的な勉強方法3選|暗記を楽にするテクニック

ここでは、古文単語を覚えるための勉強方法を紹介します。紹介するポイントは以下の3つです。
- 赤字の意味を徹底的に覚える
- 同じ単語帳のみをを徹底的に繰り返す
- 単語以外のバランスも考えるなら学習塾を利用する
『重要古文単語315』を使って具体的な勉強法を解説します。
本書は関連語や例文が豊富に掲載されており、古文に自信のない受験生にはうってつけの参考書です。各単語と現代語訳がセットになっているため、赤シートで隠して学習できるため、古文の基礎がなくても勉強を進めやすいでしょう。
ただし、学校から指定されている単語帳がある場合は、そちらを活用してOKです。
勉強法1:赤字の意味を徹底的に覚える
まずは古文の単語帳をみてください。1つの単語について、いくつもの意味が書かれているでしょう。もちろん、最終的には全部覚えないと、和訳の際に間違って訳してしまったり、文脈を正しくつかめなかったりしてしまいます。ですが、まずは単語の赤字の意味を積極的に覚えましょう。
最初から全てを覚えようとすると、なかなかモチベーションが続かず、最後まで進める前にドロップアウトしてしまう可能性が高くなるからですね。まずは、覚える部分を絞ってもいいので、最後まで進めることを意識しましょう。
勉強法2:同じ単語帳のみを徹底的に繰り返す
暗記するのが苦手だという人に実践してほしいのが「同じ参考書をたくさん繰り返す」勉強法です。繰り返し学習することで、脳が「大事な情報」として認識し、より効率よく記憶に定着させられます。具体的にどういう流れでやればいいのかをみていきましょう。
1周目~3周目:赤字の意味を定着させる
- Step1.1ページずつ見出しの単語を見て訳(赤字)を覚える
- Step2.赤シートを使って訳を思い出せるかテストする
- Step3.間違えた単語の訳をもう1度覚える
- Step4.再度テストする
- Step5.step3〜4を完璧になるまで繰り返す
1周目では、1ページずつ見出しの単語を見て現代語訳を覚えてください。古文単語は各単語の解説が詳しいものが多いため、必ず一回は解説を読むようにしましょう。
「覚えてはテストする」をくり返して30単語ずつくらいをひとまとまりにして、どんどん先に進めてください。
4周目~:赤字+別の意味を定着させる
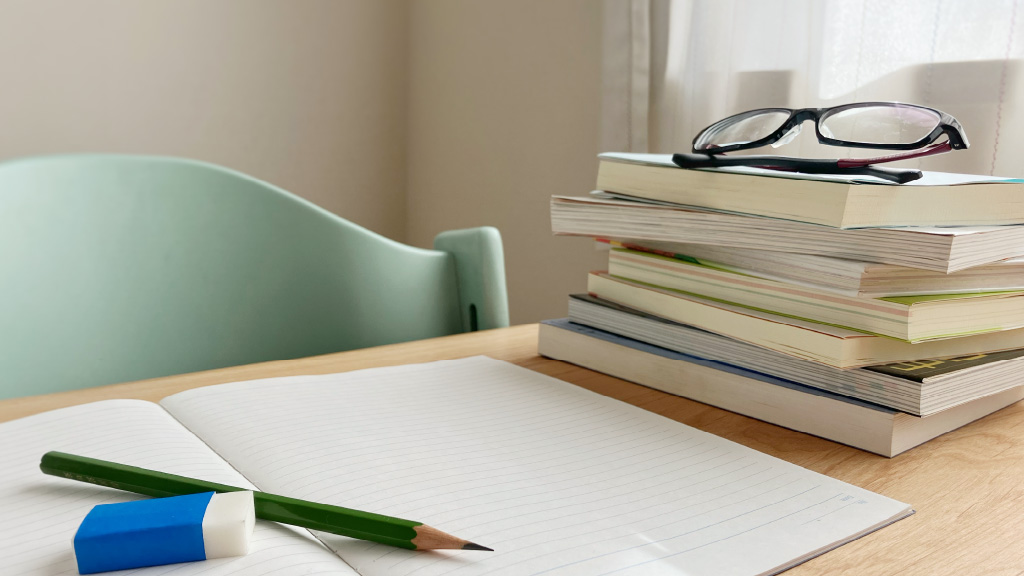
3周目までやっても記憶に定着しない箇所や赤字以外の要素をテストでチェックしながら覚えていきましょう。
覚えるときは「見るだけ・読むだけ」でもいいですが、必ず赤シートを使って覚えるようにしてください。古文の単語帳の多くは、各単語についての詳しい解説が書かれています。その単語の語源や使い方が書かれているため、解説を読むだけで、現代語訳を覚えるのに役立ちます。
また、古文では「単語から現代語訳」が理解できていれば十分です。ほとんどの問題では現代語に訳す力が求められるので、現代語から古文単語に直す練習は必要はないでしょう。
4周目以降は単語の関連要素に目を向けてください。関連知識が深まれば、古文の問題で困ることは少なくなるでしょう。関連語の多くはメインの現代語訳から派生した言葉であるため、メインの現代語訳がわかっていれば意味が推測できるものがほとんどです。
「Aの単語とBの単語は同じ意味だったんだな」「CとDは同じ意味だけどニュアンスが全然違う」などがわかると思います 。
ここで大事なのは、メインの現代語訳です。メインの現代語ができていれば古文が読めるようになれますし、4周目以降の関連語を覚えることもメインの現代語訳を覚えてなければ始まりません。
そうはいっても人間なので、いつかは忘れていってしまうもの。なのでそういう時は「チェックが付いているものの再チェック」を行いましょう。通学時間などの隙間時間に実施するだけでも効果的であるため、継続して実施してください。
勉強法3:単語以外のバランスも考えるなら学習塾を利用する

本記事を読んでいる受験生は、古文単語の勉強のハードルは比較的低いことが理解できたでしょう。とはいうものの、受験勉強は古文だけではありません。他の教科の勉強を効率的にこなすのが苦手な人も多いでしょう。
そこでおすすめなのが、コーチング型の学習塾を利用する方法です。コーチング型の学習塾では、通常の学習塾と異なり、志望校や受験日程から逆算して勉強計画を作成してくれます。
「他の教科と平行して効率的に勉強する自信がない」という受験生は利用を検討してみましょう。以下の記事でおすすめのコーチング塾を紹介しているため、参考にしてください。

古文単語を覚える際の3つの注意点

ここからは、古文単語を勉強する際の注意点を紹介します。注意点は以下の3つです。
- 現代語訳を丸暗記しようとするのはNG
- 日本語だと思わないこと
- 語呂合わせに頼りすぎるのはNG
では、それぞれについて解説していきます。
注意点1:現代語訳を丸暗記しようとするのはNG
古文を勉強する際は、現代語訳を丸暗記する方法は避けましょう。
古文の現代語訳は曖昧なものも多く、丸暗記してしまうと応用が効かなくなってしまう可能性があります。
違う文章や文脈で単語が登場した場合、理解できないことがあるでしょう。単語ごとにしっかりと暗記し、応用力を高めてください。
また、元となった「漢字」なども一緒に覚えれば、応用が効きやすくなります。こちらについては、後で詳しく説明します
注意点2:日本語だと思わないこと
古文単語を覚える際は「別の言語を覚える」という意識を持ちましょう。なぜなら、現代の日本語での意味が暗記を邪魔してしまうからです。
古文には、現代の日本語でも全く違う意味を持っている単語がたくさんあります。現代の日本語と同じ感覚で古文を読んでしまうと意味が混同してしまうでしょう。このような事態を避けるために、別の言語だという意識で勉強するようにしてください。
注意点3:語呂合わせに頼りすぎるのはNG
古文単語を暗記する際は、語呂合わせに頼りすぎるのは危険です。覚える量は英単語より少ないとはいえ、約600単語を語呂合わせで覚えるのは非効率でしょう。一周目の取っ掛かりや繰り返し単語帳を練習して、どうしても頭に入らないものを語呂合わせで覚えるようにしましょう。
古文単語の覚え方のコツ

続いて、知っていると古文単語を覚えるのが楽になる覚え方のコツを3つ紹介します。
- 単語のイメージを掴む
- 漢字で覚える
- 現代語と違う意味を意識する
それぞれについて詳しく解説します。
古文単語の覚え方のコツ①:単語のイメージを掴む
古文単語を覚えるコツはズバリ「単語のイメージを掴む」ことです。例えば「おどろく」という古文単語がありますが、この単語には「驚く」「目を覚ます」という2つの意味があります。
普通に覚えようとすると、「驚く」の方はすぐに覚えられても、もうひとつの「目を覚ます」はなかなか覚えられなさそうですよね。
そんな時に有効なのが単語のイメージです。「おどろく」という単語のイメージは「衝撃によってハッとする」というものであるため、現代語と同じように、ただ「驚く」という意味以外にも「(眠っている状況から)目を覚ます」という意味があるのです。
このように単語のイメージを最初に掴んでおくと、バラバラに「驚く」「目を覚ます」という2つの意味を覚えるよりも、簡単に覚えられるでしょう。
古文単語の覚え方のコツ②:漢字で覚える
2つ目のコツは「漢字で覚える」というものです。例えば「めづ」という単語には「愛する」という意味がありますが、これは「めづ=愛づ」という漢字を当てることを知っていれば、一瞬で覚えられます。
このように、古文単語の中には漢字を当てて簡単に覚えられるものがいくつもあります。そのため、単語の意味を覚える前にその単語を漢字で書けないかを確認しましょう。
古文単語の覚え方のコツ③:現代語と違う意味を意識する
覚え方の3つ目のコツが「現代語と違う意味を意識する」方法です。例えば、コツ①で解説した「おどろく」が「驚く」ではないと思っておくと、イメージしやすいでしょう。
反対に、現代語と同じ意味の単語は覚えなくてもOKです。だいたいの単語は現代語と同じ意味でも使えるので、まず和訳して、しっくりこなければ現代語の意味で答えましょう。

あなたにぴったりの参考書はこれ!古文単語を覚えるためのレベル別単語帳
古典単語の覚え方がわかったところで、これから新しく参考書を買うあなたのために、オススメの参考書を3つ紹介します。
古文単語を覚えるための参考書 ①:『マドンナ古文単語230』
『マドンナ古文単語230』は、古典単語の勉強をこれからはじめる人に最適な1冊です。収録単語数は230語と少なめですが、重要単語はきっちり網羅されているため心配ないでしょう。重要な単語順にまとめてあり、解説も丁寧でわかりやすいため、初心者でも学びやすい1冊です。
また、『マドンナ古文単語230』は解説がとても丁寧なのでしっかり読みましょう。1周目に取り組む前に解説を2回読みましょう。わかりやすく書かれているのでサクサク読めると思います。
古文単語を覚えるための参考書 ②:『重要古文単語315』
『重要古文単語315』は品詞がカテゴリー分けされており、苦手な単語を集中して勉強できます。慣用句や和歌などの情報もたくさん載っているため、一石二鳥の参考書といえるでしょう。
付録の章や解説などは隙間時間に読んでみましょう。古典を得点源にしたい人にはオススメです。この参考書の詳しい使い方はこちらをチェック!
古文単語を覚えるための参考書③:『新・ゴロゴ古文単語』
『新・ゴロゴ古文単語』は、最も有名な単語帳の一つです。『新・ゴロゴ古文単語』は名前のとおり、ゴロを活用して単語の意味を覚えられます。ゴロやイラストが印象的なので、古典嫌いな人でも古典単語を楽しみながら覚えられるでしょう。
大事なポイントがまとまっているため、どんどん進めて問題ありません。ただし、内容は他の参考書よりも充実していないため、国公立志望だと物足りないでしょう。そのため「ゴロで覚えるのが好きな人」「どうしても覚えられない苦手な単語がある人」にオススメです。
まとめ

古文単語を勉強する際のポイントは以下のとおりです。再度確認し、勉強に活かしましょう。
- 単語帳一冊をきちんと覚えきる!
- 単語と赤字の意味だけを覚える!
- なるべくたくさん繰り返す!
- かならずテストをする!
暗記の鉄則は「何回も繰り返す」「必ずテストで確認する」ことです。1周目で全てを暗記するのではなく、参考書を何周もして、少しずつ定着させていきましょう。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。















