*紹介している教材にはプロモーションを含みます
医学部受験において、多くの大学で必須または選択科目として課される化学。その出来栄えによって、医学部の合否を左右するといっても過言ではありません。しかし「化学のどこから手をつければ良いかわからない」「効率的な勉強法が知りたい」と悩む受験生も多いでしょう。
この記事では、医学部受験における化学の重要性、他の理科科目との比較、効果的な勉強法、そして頻出分野とその対策について、具体的なステップを交えながら詳しく解説します。この記事を読めば、医学部合格に向けた化学の学習戦略が明確になり、自信を持って対策を進められるようになるでしょう。

医学部受験における化学の重要性

医学部受験において化学は非常に重要な科目であるのはもちろん、入学後の学びに直結するという側面を持っています。
化学を得意科目にすれば、医学部合格や入学後の学習において、大きなアドバンテージとなるでしょう。ここでは、なぜ化学が医学部受験で重要視されるのか、その理由を掘り下げて解説します。
入学後の学習の基礎になる
医学部受験で学ぶ化学は、入学後の専門科目を理解するための重要な基礎となります。医学部では、生化学、薬理学、生理学など、化学の知識を前提とする科目が多く、これらの科目では、体内で起こる化学反応、薬の作用、病態の化学的理解などが求められます。
高校化学で学ぶ物質の構造、反応、エネルギーに関する知識は、これらの高度な内容を学ぶために必要な基礎知識となるでしょう。したがって、化学は医師になるための専門知識を効果的に習得するために極めて重要であるといえます。受験のためだけでなく、将来を意識した学習として化学に取り組むようにしてください。
「化学」は差がつく科目
医学部受験において化学は、他の受験生と差をつけられる重要な科目です。化学は「理論化学」「無機化学」「有機化学」と分野が多岐にわたり、それぞれで要求される能力が異なります。
理論化学では計算力と思考力、無機化学では知識の整理と体系的な理解、有機化学では構造の理解と反応の暗記・応用力がそれぞれ求められます。これらの分野で高得点を取るには、単なる暗記だけでなく、深い理解と応用力、そして効率的な学習戦略が必要です。苦手分野を作らず、得意分野を伸ばすことで、ライバルに差をつけましょう。

他の理科科目との比較
医学部受験では、多くの場合、理科2科目の選択が必要です。それぞれの科目の特性を理解し、自分の得意・不得意や志望校の傾向に合わせて選択科目を選びましょう。ここでは、物理、生物、化学の特徴を紹介します。
科目1:物理
物理は論理的思考力と数学的処理能力が求められます。なぜなら、物理の基本法則を理解し、それをさまざまな状況に応用して問題を解決したり、問題文から適切な法則を選択して立式、計算したりする一連の思考プロセスが重要だからです。
少ない原理原則から多くの事象を説明できる体系的な学問である一方、応用力や数学的なセンスが問われる場面も多いでしょう。したがって、物理は、数学が得意で、物事の原理原則を突き詰めて考えるのが好きな受験生に向いている科目といえます。
科目2:生物
生物はさまざまな知識の暗記と、それに基づく考察力・読解力が求められる科目です。
膨大な用語、構造、機能、分類などの暗記に加えて、実験結果のデータ分析や、文章による説明・論述問題なども増加傾向にあり、読解力や考察力、表現力も重要視されています。
生物は、地道な暗記作業が得意で、複雑な情報を整理・関連付けて理解するのが好きな受験生に向いています。計算問題は少ないため、知識の引き出しの多さと正確さ、そして情報を読み解き考察する力が試される科目といえるでしょう。
科目3:化学
化学は理論・計算、知識の暗記、といった力がバランスよく求められる科目です。化学は「理論化学」「無機化学」「有機化学」という性質の異なる分野から構成されており、それぞれの分野で求められる能力が異なります。
化学は、計算力、暗記力、論理的思考力といった多様な能力をバランスよく活用できる受験生に向いています。物理と生物の中間的な性質を持ち、幅広い能力が試されるため、総合的な学力が反映されやすい科目といえるでしょう。
医学部化学の効果的な勉強法

医学部入試の化学で高得点を取るためには、段階的かつ効率的な学習が必要です。ここでは、着実に実力を積み上げていくための勉強法を解説します。
基礎知識の理解
医学部化学攻略の第一歩として、教科書レベルの基礎知識を完璧に理解し、定着させるところから始めましょう。なぜなら、医学部入試で出題される応用問題や複雑な問題といえど、すべて基礎的な概念、法則、用語の組み合わせで構成されているからです。
基礎が曖昧なまま応用問題に取り組んでも、少し問題をひねられただけで対応できなくなってしまうでしょう。
「早く応用問題をマスターしなければ」と焦って問題演習に入る前に、まずは教科書や参考書を用いて、基本的な概念や用語、公式、反応式などを徹底的に理解し、確実に暗記するようにしてください。基礎知識を盤石にすることで、後の学習効率が高まるでしょう。
基本問題演習
基礎知識をインプットした後は、基本的な問題を繰り返し演習し、知識の定着と応用力を高めましょう。
教科書を読んだだけでは、知識が本当に身についているか、実際に問題で使えるかを確認できないので、基本問題を通じて「学んだ知識をどのように使うのか」「どのような計算が必要なのか」を把握してください。
基本問題を演習する際は、その都度、解答解説を確認し、なぜ間違えたのか、どの知識が不足していたのかを分析しましょう。知識の定着状況を確認し、基本的な解法パターンを習得しておけば、次のステップである入試レベル演習へのスムーズに移行できるはずです。
入試レベル演習
基礎が固まったら、次に入試標準レベルの問題集に取り組み、応用力と思考力を養成しましょう。医学部入試の問題は、難度が高い場合も多く、基礎知識を組み合わせたり、複雑な問題を読み解いたりする応用力が求められます。
思考力や多角的な視点を必要とする問題に対応できる力を養うためには、より難度の高い問題に挑戦し、試行錯誤を繰り返す必要があるでしょう。以下の記事で勉強法やおすすめの参考書を紹介しているので、ぜひご覧ください。
【化学勉強法】理論・有機・無機化学全部ばっちり!苦手克服の3ステップ
より複雑で思考力を要する入試レベルの問題に挑戦し、医学部入試で要求されるレベルを理解したうえで対策を進めましょう。
過去問演習
医学部入試における化学学習の仕上げとして、志望校の過去問を徹底的に演習し、出題傾向を把握してください。大学ごとに、出題分野の傾向、問題形式、難易など、化学の出題傾向はさまざまであるため、志望校に特化した対策が必要です。
過去問演習の際は、最低でも5年分、できれば10年分程度の過去問を、本番と同じ条件で解いてみましょう。過去問演習は、志望校合格に向けた最終調整のプロセスです。問題を繰り返し解き、合格に必要な知識と応用力、さらに、解法のテクニックを身につけましょう。

医学部受験における化学の頻出分野と対策
医学部入試の化学では、大学によって多少の濃淡はあるものの、おおむね「理論化学」「無機化学」「有機化学」「高分子」の各分野からバランスよく出題される傾向があります。ここでは、主要分野ごとの頻出テーマと対策法を解説します。
理論化学
理論化学の分野では、原子・分子、化学結合、物質の状態、溶液、化学反応とエネルギー、反応速度と化学平衡などが出題されます。さらに、計算問題、グラフ問題の対策も必要なので、押さえておきましょう。
理論化学は化学の土台であり、計算問題が多く出題されるため、原理の理解と計算力を高める必要があります。演習の際は、面倒な計算でもできるだけ電卓を使わずに自力で解くクセをつけましょう。理論化学は、地道な努力が最も報われやすい分野なので、地道に演習を積み重ねてください。
無機化学
無機化学からは、典型元素、遷移元素、イオン反応などが出題されます。無機化学の分野では、系統的な暗記と反応式の理解が重要です。
暗記事項が多く、暗記作業に時間をかける受験生が多いですが、重要事項を80%程度暗記していれば対応できる問題が多いため、暗記作業と演習をバランスよく実施するとよいでしょう。
暗記の際は、なぜそのような性質や反応が起こるのかを、電子配置や電気陰性度など理論的な側面から考える癖をつけると、記憶に定着しやすいのでおすすめです。
有機化学
有機化学からは、脂肪族化合物、芳香族化合物、官能基、異性体、高分子化合物などが出題されます。基礎知識を身につけた後は、問題集を解きながら、覚えていなかった所を逐一覚えていく方針で勉強を進めましょう。
また、大学によっては難問である「構造決定問題」が出題される場合があります。構造決定問題は、ひたすら問題集や過去問で数をこなすほかないので、出題される可能性がある大学を受験する方は、しっかりと対策しておきましょう。
高分子
医学部入試では頻出である高分子分野。高校化学最後の単元であるため、対策が不十分な現役生も多いです。しかし、浪人生はしっかりと対策しているので、高分子分野で差が開かないように問題演習を充実させてください。
とっつきにくい印象を持っている受験生が多いかもしれませんが、問題の難度は高くないので、しっかりと対策しておきましょう。
医学部受験における化学攻略におすすめの教材6選
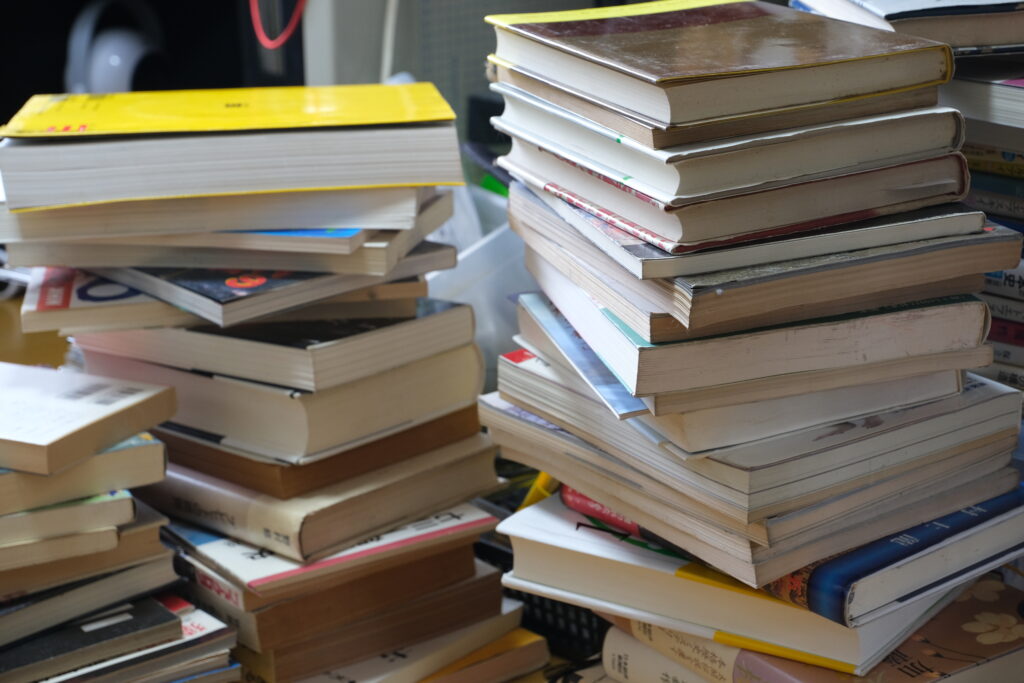
医学部入試の化学では、単なる知識の暗記だけでなく、思考力や計算力、応用力が問われます。そのため、自分の現在の学力レベルと目標とする大学のレベルを見極め、最適な教材を選択する必要があります。
ここでは、数ある化学教材のなかから、多くの医学部受験生から支持されているおすすめ教材を6つピックアップし、それぞれの特徴や効果的な使い方を詳しく解説します。
おすすめ教材1:「スタディサプリ」
スタディサプリは、化学の学習を始めたばかりの初学者や、参考書だけでは理解が難しいと感じる医学部受験生におすすめの教材です。
化学には、分子の構造、反応メカニズム、平衡の移動など、文字だけではイメージしにくい抽象的な概念が多く存在します。スタディサプリの動画講義は、これらの概念をCGやアニメーション、講師の丁寧な解説によって具体的かつ分かりやすく視覚化してくれます。
これにより、教科書や参考書を読むだけでは得られない直感的な理解が促され、学習初期のつまずきを防ぎ、知的好奇心を引き出す効果が期待できます。医学部受験の化学で求められる盤石な基礎を築くうえで、この「わかる」体験は非常に重要です。
スタディサプリについては、以下の記事でさらに詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
おすすめ教材2:大学受験Doシリーズ
大学受験Doシリーズは、講義形式の丁寧な解説を通じて、化学の原理を深く理解したい医学部受験生に最適な参考書です。このシリーズが優れている理由は、単なる知識の羅列や問題の解法を示すだけでなく「なぜそうなるのか?」という背景や理由に重点的に解説している点にあります。
化学の法則や反応には必ず理由があります。丸暗記から脱却し、効率的に得点するためには、その本質を理解する必要があります。医学部入試では、初見の問題や複雑な設定の問題が出題されるケースがよくあります。
本書を活用し、化学原理の根本をしっかりと理解しましょう。以下の記事で「大学受験Doシリーズ」のなかでも有名な「福間の無機化学の講義」を紹介しているので、あわせてチェックしてください。
初心者でも暗記に苦しまなくなる!『福間の無機化学の講義』の正しい使い方&勉強法!
おすすめ教材3:「セミナー化学」
セミナー化学は、教科書レベルの基礎から入試標準レベルまでを網羅的に学習している問題集です。豊富な問題演習を通じて知識を定着させたい医学部受験生にとって、心強いパートナーとなるでしょう。
この教材が多くの医学部受験生に利用される理由は、圧倒的な網羅性と段階的なレベル構成にあります。化学の学習においては、まず基礎知識をインプットし、それを問題演習によってアウトプットする必要があります。
セミナー化学は、教科書で扱われるほぼすべての項目をカバーしており、徐々に難度が上がっていく構成になっています。これにより、受験生は、自分のレベルに合わせて無理なく学習を進め、基礎知識の確認から標準的な入試問題への橋渡しまで、一冊で幅広く対応できるでしょう。
おすすめ教材4:「化学の新標準演習」
化学の新標準演習は、化学の基礎固めを終え、より実戦的な応用力を養い、国公立大学医学部や難関私立大学医学部レベルの問題に対応できる実力をつけたい受験生におすすめの問題集です。
この問題集の特徴は、セミナー化学よりも一段階難度が高く、思考力を要する良問が多く収録されている点です。医学部入試の化学では、単に知識を知っているだけでなく、それらを組み合わせて考察したり、複雑な条件設定のなかから必要な情報を見抜いたりする能力が求められます。
化学の新標準演習は、入試で差がつくレベルの問題に焦点を当てており、基礎知識を実際の入試問題でどのように活用するのかを学ぶのに適しています。解説も丁寧で、その問題の背景にある化学的な考え方や着眼点まで踏み込んで説明されているのが特徴です。
おすすめ教材5:「重要問題集化学」
重要問題集化学は、全国の大学入試問題から頻出かつ質の高い問題を厳選して収録しており、入試標準レベルから応用レベルまで、幅広い問題を効率的に演習したい医学部受験生におすすめです。
この問題集が多くの医学部受験生に支持される理由は、重要問題と応用問題という明確なレベル分けと、入試頻出パターンの網羅性にあります。この段階的な構成により、自分の実力に合わせて計画的に学習を進められるでしょう。また、洗練された問題選定により、入試で問われるポイントを効率的に学習できる点も大きな魅力です。
おすすめ教材6:「化学の新演習」
化学の新演習は、現時点で出版されている化学の問題集のなかで最高レベルの難度を誇ります。旧帝大医学部や難関私立医大など、最難関の医学部を目指す受験生が、他の受験生に差をつけるためのハイレベルな教材です。
この問題集は、問題の質と難度が高く、標準的な問題集をマスターしたうえで、さらに深い思考力、複雑な計算処理能力、そして初見の問題に対する応用力を高めたい受験生を対象としています。
志望校の過去問を演習し「想像以上に化学の難度が高い」と感じる場合は、本書を使用して演習するとよいでしょう。

試験直前のチェックポイント

入試本番が近づくにつれて、新たな知識を詰め込むよりも、これまで学習してきた内容の最終確認と、本番で実力を最大限に発揮するための準備が重要です。ここでは、効率的に最終調整を行うためのチェックポイントを解説します。
公式や反応式の再確認
試験直前期には、これまで学習した重要な公式、定義、反応式などを総復習し、記憶を再確認・定着させてください。試験本番では、緊張や焦りから、普段なら思い出せるはずの基本的な知識が抜け落ちてしまう可能性があります。
また、直前に重要項目を見直しておくことで、知識の抜け漏れがないか最終チェックするよい機会にもなるでしょう。したがって、試験直前の数日間は、新しい問題に手を出すよりも、これまで蓄積してきた知識の総復習に時間を充て、基本的な知識の最終確認をしてください。
時間配分のシミュレーション
試験直前期には、過去問や模試を用いて、本番と同じ時間設定で問題を解くシミュレーションを行い、最適な時間配分戦略を確立しておきましょう。
医学部入試の化学は、限られた時間内に多くの問題を解く必要があるため、時間配分の失敗は命取りになります。事前に時間配分の感覚をつかんでおけば、本番で焦らずに自分のペースで問題を解き進められるでしょう。
本番を想定した時間配分のシミュレーションを繰り返し、解答時間のペース配分を身体に覚え込ませてください。
まとめ
化学は理論・無機・有機・高分子と分野が多岐にわたり、それぞれで計算力、暗記力、思考力、応用力といった異なる能力が求められるため、総合的な学力が試される科目です。
本記事で紹介した学習法を実践し、段階的にレベルを上げ、化学を得意科目に変えましょう。また、試験直前には公式や反応式の再確認と時間配分のシミュレーションを行い、万全の状態で本番に臨むことが大切です。
この記事で紹介した勉強法、頻出分野対策、直前チェックポイントなどを参考に、自分なりの学習計画を立て、粘り強く努力を続けてください。化学を得点源とし、医学部合格をつかみとりましょう。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。


















