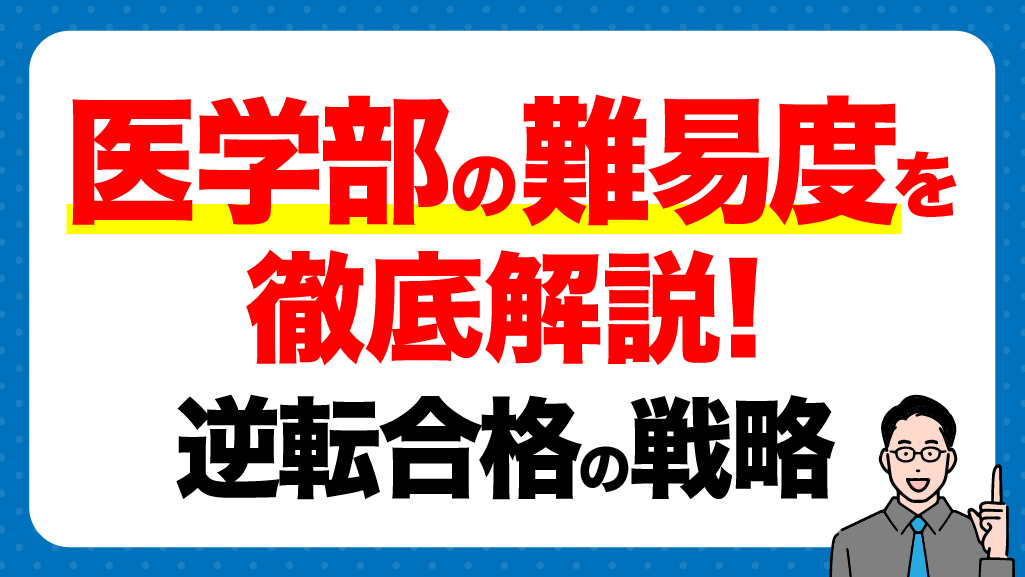
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
大学受験の最難関として知られている医学部受験。しかし、医学部受験の難易度を具体的に理解している受験生は少ないでしょう。
偏差値が高いことはもちろんですが、医学部合格の壁はそれだけではありません。求められる学習量の膨大さ、問題の質の高さ、そして極めて高いレベルでの競争が、受験生に重くのしかかります。
この記事では、最新情報に基づき、医学部の偏差値ランキングから、医学部の実質的な難易度まで、医学部の「本当の難しさ」を徹底解説。さらに、逆転合格を可能にするための具体的な学習戦略についても詳しく紹介します。

【一覧表】国公立・私立大学医学部の偏差値ランキングTOP10
医学部を目指す上で、まず把握しておきたいのが各大学の偏差値です。ここでは、2025年最新のデータを基に、医学部偏差値ランキングTOP10を紹介します。
| 順位 | 大学名 | 偏差値 | 国公立・私立 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 76.8 | 国公立 |
| 2 | 慶応義塾大学 | 75.8 | 私立 |
| 3 | 京都大学 | 75.3 | 国公立 |
| 4 | 大阪大学 | 73.7 | 国公立 |
| 5 | 東京科学大学(旧東京医科歯科大学) | 73.3 | 国公立 |
| 6 | 山梨大学(後期のみ) | 72.0 | 国公立 |
| 7 | 東京慈恵会医科大学 | 71.7 | 私立 |
| 8 | 順天堂大学 | 71.0 | 私立 |
| 9 | 日本医科大学 | 70.3 | 私立 |
| 9 | 千葉大学 | 70.3 | 国公立 |
偏差値は大学の難易度を示す一つの指標であり、志望校選定の参考材料となります。ただし、偏差値は予備校や模試によって変動する可能性があるため、あくまで目安として捉えるようにしましょう。
【2025年最新】医学部の難易度を徹底解説

医学部の難易度は、単に偏差値の高さだけで測れるものではありません。国公立と私立では入試制度が大きく異なり、それぞれに特有の「壁」が存在します。
国公立大学を目指すのであれば、大学入学共通テストで高得点を獲得することが絶対条件です。一方で、私立大学では、公表されている倍率の数字だけでは見えない「実質的な難易度」を理解しておく必要があるでしょう。ここでは、医学部入試の難しさを深掘りし、合格に必要な具体的な指標を紹介します。
共通テストで何割必要?国公立医学部のボーダーライン
国公立大学医学部の合格を勝ち取るためには、第一次選抜である大学入学共通テストで高得点が求められます。
ボーダーラインは、多くの大学で85%以上に設定されており、難関大学では90%を超えることも珍しくありません。地方の国公立大学であっても、決して難易度が低いわけではなく、最低でも80%以上の得点率は必要です。
共通テストは科目数が多く、総合的な学力が問われます。苦手科目を作らず、全科目で安定して高得点を取るための徹底した対策が必要です。特に個別試験でも問われる英語・数学・理科2科目は共通テストでは全て満点を狙うくらいの学力が必要になると覚えておくといいでしょう。
倍率だけでは分からない!私立医学部の実質的な難易度
私立医学部の倍率をチェックする際は「志願倍率」ではなく「実質倍率」に注目しましょう。私立大学医学部は併願が可能であるため、一人の受験生が複数の大学に出願し、見かけ上の倍率が高くなる傾向にあります。
しかし、私立医学部では正規合格者に加えて、多くの「繰り上げ合格者」を出すのが一般的です。このため、実質的な競争率は志願倍率よりも低くなると言えるでしょう。とは言え、多くの大学で10倍を超える厳しい入試であることには変わりはないので、入念に対策を行いましょう。

なぜ医学部はこれほどまで難しい?偏差値だけでは語れない5つの理由

医学部が難しい理由は、偏差値の高さだけではありません。医学部受験には、受験生が乗り越えなければならない、質・量ともに桁違いの「5つの壁」が存在します。これらの壁の存在を理解することで、医学部合格に必要なものが見えてくるでしょう。
理由1:圧倒的な学習量と科目数という「量の壁」
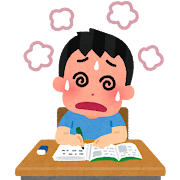
医学部入試では、圧倒的な学習量が求められます。国公立大学の場合、共通テストで6教科8科目が課されます。さらに大学別の二次試験では多くの場合、英語、数学、理科2科目(物理・化学・生物から選択)が必須です。
他の理系学部と比較しても科目数が多く、すべての科目で高いレベルの学力が要求されます。特に数学3が必須なこと、理科が2科目必ず必要になること、そしてそれらの難易度が高いことは医学部の特徴です。
高校3年間の学習範囲を網羅し、かつ応用レベルまで習熟するには、膨大な学習時間の確保が必要です。苦手科目を作ることは許されず、全方位にわたる計画的かつ効率的な学習が求められます。
理由2:思考力・記述力が問われる「問題の質の壁」
次にクリアすべきは、単なる暗記では太刀打ちできない「問題の質の壁」です。医学部の二次試験では、知識の多さだけでなく、知識をいかに活用できるかを問う問題が多く出題されます。
例えば、数学では複雑な設定の問題を解決する論理的思考力、理科では初見の実験データや長文を読み解き考察する深い思考力や記述力が求められます。
これらの能力は一朝一夕には身につきません。日ごろから問題の本質を理解しようと努め、自分の考えを論理的に説明する訓練を積み重ねる必要があるでしょう。
理由3:1つのミスが命取りになる「高得点勝負の壁」
医学部入試において「高得点勝負」は避けられません。合格最低点が非常に高く設定されているため、ケアレスミス一つが合否を分ける致命傷になります。特に地方国公立大学では、他の学部と同じ問題を使うことも多いため、個別試験でも7割以上の得点率が必要になることも多いのです。
ライバルとなる受験生のレベルも高く、基礎的な問題ではほとんど失点しないと考えておきましょう。厳しい戦いの中で合格を勝ち取るには、普段の学習から、計算ミスや誤字脱字をしない丁寧さを徹底する必要があります。
また、本番の緊張状態でも実力を最大限に発揮できるよう、時間を意識しながら問題を解くなど、実戦を想定した演習を繰り返しましょう。
理由4:ライバルのレベルが高い「競争環境の壁」
医学部受験における4つ目の壁は、全国トップレベルの優秀な受験生たちとしのぎを削る「競争環境の壁」です。医学部を志す受験生は、学力はもちろんのこと、学習意欲や目標達成への意識が非常に高いです。
他の理系学部と違って、早い時期から医学に興味を持って、早い時期から受験勉強を始める人が多いのも医学部の特徴です。他の学部では、高3になってから学部を決める人も珍しくはないので、それとはかなり対照的と言えるでしょう。
ハイレベルな競争環境の中で勝ち抜くためには、自分の現在地を客観的に把握し、慢心せずに努力を続ける姿勢が求められます。全国模試などを通じてライバルたちの実力を肌で感じ、競争意識を持つことが、自らをさらに高いレベルへと引き上げる原動力となるでしょう。
理由5:長期戦を戦い抜く「精神力・モチベーションの壁」

最後の壁は、1年以上にわたる厳しい受験勉強を乗り越えるための「精神力・モチベーションの壁」です。医学部合格という高い目標に向かう道のりは厳しく、成績が伸び悩んだり、模試の結果に一喜一憂したりと、精神的に辛い時期が訪れます。
長期戦を最後まで戦い抜くためには、強靭な精神力と、高いモチベーションを維持し続ける工夫が欠かせません。適度な休息や気分転換を取り入れながら、長期戦を乗り越えましょう。

【重要】医学部の高い壁を乗り越えるためには「学習管理」が重要

医学部受験の高い壁を乗り越えるための方法は学習管理です。学習管理とは、単に勉強時間を記録することではありません。学習管理では以下のポイントを押さえましょう。
- 現在地とゴールの明確化
- 「年間・月間・週間計画」の立て方
- 全科目のバランスを取る「科目別学習戦略」
学習管理を徹底することこそが、膨大な学習量を効率的にこなし、ライバルとの競争に打ち勝つための効果的な戦略と言えるでしょう。
現在地とゴールの明確化

最初に取り組むべきは「現在地とゴールの明確化」です。まずは、志望校の過去問や全国模試の結果を徹底的に分析し、合格に必要な学力と自分自身の現状とのギャップを正確に把握しましょう。
現状分析が曖昧なままでは、効果的な学習計画は立てられません。ゴール(合格)と現在地の距離を客観的なデータに基づいて明らかにすることで、これから何をすべきかが見えてきます。
「年間・月間・週間計画」の立て方
現在地とゴールが明確になったら、次はそのギャップを埋めるための具体的な「年間・月間・週間計画」を作成します。
まず、入試本番までの残り期間から逆算して、年間の大まかなスケジュールを設定しましょう。「夏までに基礎を完成させる」「秋からは過去問演習に入る」といった大きな目標を立てます。
次に、設定した年間計画を達成するために、月間、週間単位でやるべきことを細分化します。この際、実現不可能な計画を立てるのではなく、自分の可処分時間を考慮した計画にすることが継続のポイントです。計画は定期的に見直し、進捗状況に合わせて柔軟に修正しましょう。
全科目のバランスを取る「科目別学習戦略」
医学部入試では、全科目で高得点を獲得するための「科目別学習戦略」が不可欠です。各科目の配点や目標得点を考慮し、学習時間の配分を戦略的に決定しましょう。
苦手科目の克服や得意科目の強化など、教科ごとのバランスが重要です。例えば、英語と数学は早期に着手し、理科や社会は夏以降に集中して完成度を高めるなど、科目特性に応じた学習計画を立てることが効率的です。科目のバランスを意識し、総合力を高めましょう。
モチベーションを維持し、走り続けるための仕組み作り
一年以上に及ぶ医学部受験は、学力だけでなく精神力も大きく問われます。高いモチベーションを維持し、最後まで走り続けるための「仕組み作り」は、作成した学習計画を遂行する上で非常に重要です。
例えば、短期的な目標を設定し、達成できたら自分にご褒美を与える、週に一度は完全に休む日を作る、といったルールを設定しましょう。
また、信頼できる友人や予備校の先生など、悩みを相談できる相手を見つけておくこともモチベーション維持につながります。一人で抱え込まず、周囲のサポートも活用しながら、心身ともに健康な状態で受験を乗り越えましょう。

医学部の難易度に関するよくある質問

医学部の難易度については、多くの受験生が様々な疑問や不安を抱えています。ここでは、特に多く寄せられる質問に対して、最新の情報に基づいて分かりやすくお答えします。
Q1.地方の国公立医学部は入りやすい?
一部の地方国公立大学は都市部の難関校よりも偏差値が低くなることがあります。しかし、地方の国公立医学部といっても、偏差値65.0を下回ることはほとんどなく、最難関レベルであると言えるでしょう。
「地方だから簡単」と安易に考えるのではなく、各大学の入試科目や配点、地域枠の有無などを総合的に分析し、自分に合った大学を選ぶことが大切です。
Q2.多浪すると不利になりますか?
多浪しても受験で不利になることはありません。過去に一部の大学で年齢による不適切な扱いがあったことは事実ですが、現在は是正されています。
しかし、面接試験では浪人期間中の過ごし方や学習への取り組みについて問われることがあるでしょう。なぜ多浪したのか、その経験から何を学んだのかを前向きに説明できるよう、しっかりと自己分析しておくことが求められます。浪人期間を無駄にせず、学力面でも人間的にも成長したことをアピールしましょう。
Q3.高1・高2から始めるべき対策はありますか?
医学部現役合格を目指すのであれば、早期からの対策が欠かせません。高1・高2の段階で優先すべきは、英語と数学の基礎を盤石にすることです。
この2科目は積み重ねが重要なため、早期から取り組むことで、高3になってから理科、国語、社会などの他科目に時間を割く余裕が生まれます。毎日コツコツと勉強する習慣を身につけておくことが、本格的な受験勉強が始まった際の大きなアドバンテージとなるでしょう。
まとめ:医学部の難易度を正しく理解し、合格への一歩を踏み出そう
この記事では、2025年最新の医学部難易度について、偏差値ランキングから共通テストのボーダーライン、さらには偏差値だけでは測れない「5つの壁」に至るまで、多角的に解説しました。
医学部合格が難度の高い試験であることは事実ですが、試験の本質を正しく理解し、適切な戦略を立てて努力を継続すれば、合格を大きく手繰り寄せられるでしょう。
しかし、膨大な学習量、全科目のバランス、そして長期戦を乗り切るモチベーションの維持をすべて自力で完璧に実行し続けるのは、至難の業です。多くの受験生がここで挫折し、時間を浪費しています。
そこで必要なのが、あなたのための「受験のパーソナルトレーナー」です。
学習塾STRUXでは、あなたの現状と志望校から逆算し、「何を・何時間・何ページ」まで毎日の勉強を具体的かつ徹底的に指定します。

戦略や計画はすべてプロに任せて、あなたは「あとは言われた通りに勉強するだけ」。勉強法に迷う時間をゼロにし、最短距離で医学部の高い壁を乗り越えましょう。
なぜSTRUXがあなたの逆転合格を可能にするのか? 「勉強したのに不合格」をなくすその全貌は、こちらからご覧ください。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。












