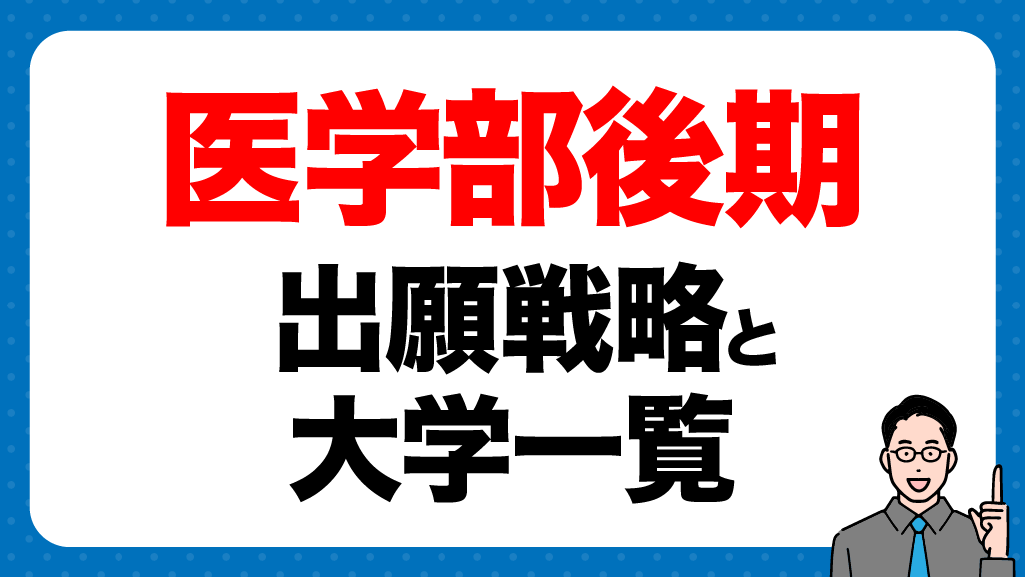
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
熾烈な争いが繰り広げられる医学部入試。国公立大学の出願は前期と後期を同時に行うため、前期日程の戦略と同時に後期日程の戦略を練ることが、医学部合格の可能性を最大化するための欠かせないステップです。
しかし、前期日程の対策に追われる中で「後期日程のことまで考える余裕がない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2026年度入試に向けた国公立医学部後期日程の実施大学一覧から、後悔しないための戦略的な出願ポートフォリオの組み方、そして後期特有の小論文・面接対策まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、後期日程に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って出願計画を立てられるようになるでしょう。

【2026年度最新】国公立医学部後期日程実施大学一覧

まずは、2026年度入試で後期日程を実施する可能性がある国公立大学医学部を確認しましょう。
| 大学名 | 合格者数 | 倍率 | ボーダー得点率 |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 8名 | 3.8倍 | 87% |
| 山形大学 | 22名 | 4.1倍 | 88% |
| 秋田大学 | 29名 | 2.2倍 | 86% |
| 千葉大学 | 20名 | 7.7倍 | 91% |
| 東京科学大学 | 11名 | 2.8倍 | 95% |
| 山梨大学 | 90名 | 3.2倍 | 88% |
| 福井大学 | 29名 | 3.2倍 | 88% |
| 浜松医科大学 | 14名 | 3.7倍 | 88% |
| 名古屋大学 | 5名 | 3.6倍 | 89% |
| 三重大学 | 12名 | 5.1倍 | 86% |
| 奈良県立医科大学 | 63名 | 4.8倍 | 88% |
| 山口大学 | 11名 | 3.9倍 | 87% |
| 佐賀大学 | 4名 | 8.3倍 | 86% |
| 宮崎大学 | 18名 | 4.6倍 | 82% |
| 鹿児島大学 | 24名 | 2.6倍 | 86% |
| 琉球大学 | 30名 | 2.1倍 | 86% |
近年、後期日程は縮小・廃止の傾向にあり、募集枠は限られています。そのため、正確な情報をいち早く入手することが肝心です。2026年度の募集要項は必ず各大学の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。

国公立医学部入試において前期出願と同時に後期戦略を固めるべき理由

国公立大学の出願手続きは、前期日程と後期日程を同時に行います。同時出願のルールこそが、早期に後期戦略を固めるべき最大の理由です。
前期試験が終わってから「後期はどうしようか」と考える時間はないので注意しましょう。以下で前期出願と同時に後期戦略を固めるべき理由を詳しく解説します。
不安材料を消し、前期の勉強に集中するため
出願を終えてから前期試験までの約1ヶ月間は、二次試験対策の総仕上げをする大切な時期です。
「もし前期試験がうまくいかなかったら…」という不安は、誰にでもあるでしょう。しかし、その時点で「自分には後期日程という次の一手がある」と確信できていれば、心理的な負担は大きく軽減されます。
事前に後期出願校を吟味し、納得のいく形で出願を済ませておくことは、迫りくる前期試験への集中力を高めるための、効果的な作戦と言えるでしょう。
後期日程は「保険」ではなく重要な「次の一手」
後期日程の位置づけは保険ではなく、医学部合格に向けた「次の一手」です。
後期日程を単なる「前期が不合格だった場合の保険」と捉えてはなりません。後期日程は募集人数が非常に少なく、倍率も難易度も高くなる傾向にあります。安易な気持ちで出願しても、合格を勝ち取るのは容易ではありません。
だからこそ、後期日程は医学部合格へのチャンスを最大化するための、戦略的な「次の一手」という意識を持つことが重要です。配点や試験科目を徹底的に分析して試験に臨みましょう。
国公立医学部における前期・後期の戦略的併願2パターン

ここでは、受験生の状況に応じた前期・後期の戦略的な併願ポートフォリオを3つのパターンに分けて紹介します。どちらのパターンが自分に合っているか、自己分析と照らし合わせながら考えてみましょう。
パターンA:【挑戦✕堅実】前期チャレンジ校+後期安全校
共通テストで予想以上の高得点を獲得できた受験生や、二次試験の記述力に絶対的な自信があり、より上位の大学を狙いたい受験生におすすめのパターンです。
前期日程では、自分の実力より少し上の「チャレンジ校」に出願し、積極的に挑戦します。後期日程では共通テストの配点比率が高い大学や、ボーダーラインに対して自分の得点に余裕がある「安全校」を選び、確実に合格を確保する戦略です。この組み合わせにより、思い切った挑戦と精神的な安定の両立を目指せるでしょう。
パターンB:【専門性重視】前期・後期ともに「やりたい研究」で選ぶ
特定の研究分野に強い関心があり、大学入学後のビジョンが明確な受験生向けのパターンです。この戦略は、入学後の学習意欲にも直結し、面接試験などで志望動機を具体的に語れるというメリットもあります。
偏差値や難易度、所在地といった要素だけでなく「その大学でしか学べないこと」を軸に出願校を決定します。前期・後期ともに、自分の興味がある研究室やプログラムを持つ大学を選ぶと良いでしょう。

後悔しない出願先を選ぶ!データに基づいた大学選定の3ステップ

ここでは、客観的なデータに基づいて最適な出願ポートフォリオを組むための3つのステップを解説します。
- STEP1:自己分析を徹底する
- STEP2:志望校の配点・試験科目を徹底的にリサーチする
- STEP3:自分だけのポートフォリオを作成する
感覚だけで出願校を決めるのではなく、順序立てて論理的に検討しましょう。
STEP1:自己分析を徹底する
まずは、自己分析を徹底し、自分の立ち位置を把握しましょう。注目すべきは、模試における自分の順位や、得点分布です。
合格者平均点と自分の得点を比較したり、ボーダーライン付近にどれだけの受験生がひしめいているかを確認したりすることで、より客観的に自分の立ち位置を把握できます。この詳細な分析が、現実的な出願校選定の第一歩です。
STEP2:志望校の配点・試験科目を徹底的にリサーチする
次に、出願を検討している大学の入試情報を徹底的に分析します。特に後期日程では、大学ごとに配点や試験科目が大きく異なるため、注意しましょう。
チェックすべきポイントは「共通テストと二次試験の配点比率」と「二次試験の科目」です。共通テストで高得点を取れた受験生は共通テスト重視の大学が有利になります。一方で、二次試験での逆転を狙うなら二次試験の配点が高い大学が向いています。
また、後期日程の二次試験は「小論文と面接のみ」という大学も多いため、学力試験以外の対策の必要性も頭に入れておきましょう。
STEP3:自分だけのポートフォリオを作成する
最後にSTEP1の自己分析とSTEP2の大学分析の結果をかけ合わせ、自分にとって最適な出願ポートフォリオを組み立てます。
例えば、共通テストの得点には余裕があるが、数学の記述に不安がある場合、前期は数学の配点が比較的低い安全校を選びます。そして、後期は共通テストの配点比率が極めて高く、二次試験が小論文・面接のみの大学を選ぶ、といった具体的な戦略が立てられるでしょう。
先述した3つの併願パターンも参考にしながら、自分だけのポートフォリオを導き出しましょう。
≫「医学部 国公立大学 入りやすい」のリンク
国公立医学部後期特有の「小論文・面接」試験

後期日程の二次試験では、学力試験を課さず、小論文や面接を重視する大学が数多く存在します。
付け焼き刃の対策では通用しないため、事前の準備が合否を分けるといっても過言ではありません。ここからは「小論文・面接」試験の重要性を詳しく解説します。
小論文・面接試験の基礎知識
小論文では、最新の医療ニュースや生命倫理に関するテーマなどの課題文を読んで要約・意見を述べさせる形式などが出題されます。単なる知識だけでなく、論理的思考力や表現力、医師としての倫理観が評価されます。
一方、面接では、以下の質問が頻出です。
- 医師志望理由
- 大学志望理由
- 地域医療への貢献意欲
医師志望理由や大学志望理由といった基本的な質問に加え、多角的に人間性をチェックされます。また、個人面接だけでなく、集団討論やMMI(マルチプル・ミニ・インタビュー)を導入している大学もあるため、志望校の形式に合わせた対策が必要です。
≫医学部 小論文の記事のリンク
≫医学部 面接の記事のリンク
後期対策はいつから始めるべきか
後期対策は出願校を決定した段階で対策を始めるのがベストです。まずは志望校の過去の出題テーマや面接の形式を調べ、傾向を把握しましょう。
しかし、多くの受験生は前期試験の対策で手一杯なのが現実です。そのため、前期の勉強と並行して、日ごろから医療関連のニュースに関心を持ち、自分なりの意見を考える習慣をつけるところから始めてみましょう。
本格的な記述練習や模擬面接は、前期試験終了後から集中的に取り組む計画を立てておくと、スムーズに対策を進められるでしょう。

まとめ:戦略的な出願計画が、医学部合格の第一歩
国公立大学医学部の後期日程は、受験生に与えられた貴重なチャンスです。重要なのは、後期日程を「保険」としてではなく、合格の可能性を追求するための積極的な「戦略」と捉え、早期から準備を進めることです。
本記事で紹介した、データに基づいた大学選定のステップや、前期・後期の併願パターンを参考に、ぜひご自身にとって最適な出願ポートフォリオを組み立ててください。
周到に練られた出願計画は、受験期間中の精神的な支えとなり、前期試験への集中力を高めてくれるはずです。戦略的な出願計画こそが、医学部合格というゴールへの確かな第一歩となるでしょう。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。












