*紹介している教材にはプロモーションを含みます
大学入試における日本史は、正しい対策を講じれば、得点源になる科目です。そんな日本史ですが、「暗記項目が多くて苦手」と感じている人も多いでしょう。
本記事では、日本史をマスターするためにおすすめの勉強法や効果的に学習を進められるおすすめの教材を紹介します。
暗記が苦手で、勉強時間に見合った成果が出ていない人や日本史は暗記力だけで乗り切れると考えている人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
これから紹介する勉強法で日本史の克服を目指しましょう!効果的な日本史学習の進め方は、以下の動画でも解説しているので、あわせてご覧ください。

いつから始める?受験対策の開始時期

日本史の学習開始時期は、あなたの科目ごとの習熟度や、志望大学の配点によって異なりますが、高校3年生の夏休み前を目安に、全範囲の通史を終えるのが理想的です。
通史完了の時期から逆算すると、高校2年生の11〜12月頃にスタートできれば、余裕を持って通史を進められるでしょう。
ただし、英語や国語など、他の科目の基礎がまだ固まっていない場合は、そちらを優先すべきです。特に英語は、多くの大学で配点が高いため、最優先で取り組むようにしてください。
一方で論述問題が出題される難関国公立大学(旧帝大レベル)や、難関私立大学(MARCH・関関同立レベル)を目指す場合は、高校3年生のゴールデンウィーク頃には通史を終えている状態を目指しましょう。

日本史を効率的にマスターするための3ステップ

日本史の学習は、以下の3つのステップに分けられます。
【日本史学習の3ステップ】
- STEP.1 通史の理解
- STEP.2 用語の暗記
- STEP.3 志望校の出題形式に合わせた演習
日本史の問題は、選択問題と論述問題がよく出題されます。なので、単なる暗記に終始するのではなく、歴史の流れや因果関係に着目し、通史を理解することから始めましょう。それでは、各ステップの具体的な学習ポイントを見ていきましょう。
ステップ1:通史を理解する
日本史の学習において最も重要なのは、時代ごとの特徴や、次の時代への移行のきっかけといった「歴史の流れ」を理解することです。通史学習を進める際は、文化史も並行して学習すると、より効果的でしょう。
通史という骨組みを構築し、そこにさまざまな知識を肉付けしていくことを意識すれば、知識が定着しやすいでしょう。「暗記が苦手」と感じている方も、まずは通史から着手してみましょう。
通史学習の進め方については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてください。
ステップ2:重要単語から暗記する
歴史の流れを大まかに理解したら、つぎは単語の暗記に取りかかりましょう。単語暗記を開始する段階では、歴史の流れを復習しながら、単語を関連付けて覚える方法がおすすめです。
多くの人が「日本史一問一答」を使って単語を覚えていると思います。これは英語の単語帳のように、単語と説明が並んだ問題形式の参考書で、手軽に使えるのが魅力です。しかし、最初から一問一答に飛びつくのは必ずしも効率的とは言えません。
なぜなら、一問一答を最初から使うと、理解した歴史の流れを活かせなくなってしまう可能性があるからです。
まずは『詳説日本史ノート』などの穴埋め形式の問題集を使って、歴史の流れのなかで単語を覚えていくのがおすすめです。
単語の暗記や一問一答の活用方法については、以下の記事も参考にしてください。
また、単語暗記を進めるなかで、穴埋めノートや問題集の解説だけでは解決できない疑問が出てくるでしょう。そんな時は、用語集や資料集を活用してください。
日本史の入試では、史料に基づいた問題や、仏像や絵画などの作品名と実物を結びつける問題も出題されます。資料集などで実物の写真を確認しておきましょう。
ステップ3:志望校の出題形式にあわせて問題演習する
通史と単語の学習が完了したら、志望校の出題形式に合わせた対策を講じましょう。志望校によって、選択式、単語記述、論述など、出題形式はそれぞれ異なります。
志望校の出題形式に合わせて、必要な分野の演習を重ねてください。国公立大学では、「指定語句を用いて300字以内で説明せよ」「〇〇について説明せよ」といった論述問題が中心ですが、私立大学では記号問題や単語記述が中心です。
大学ごとに出題範囲や問題形式を過去問で把握しておきましょう。詳しい対策については、以下の記事を参考にしてください。

【ステップ別】日本史学習のおすすめ教材6選
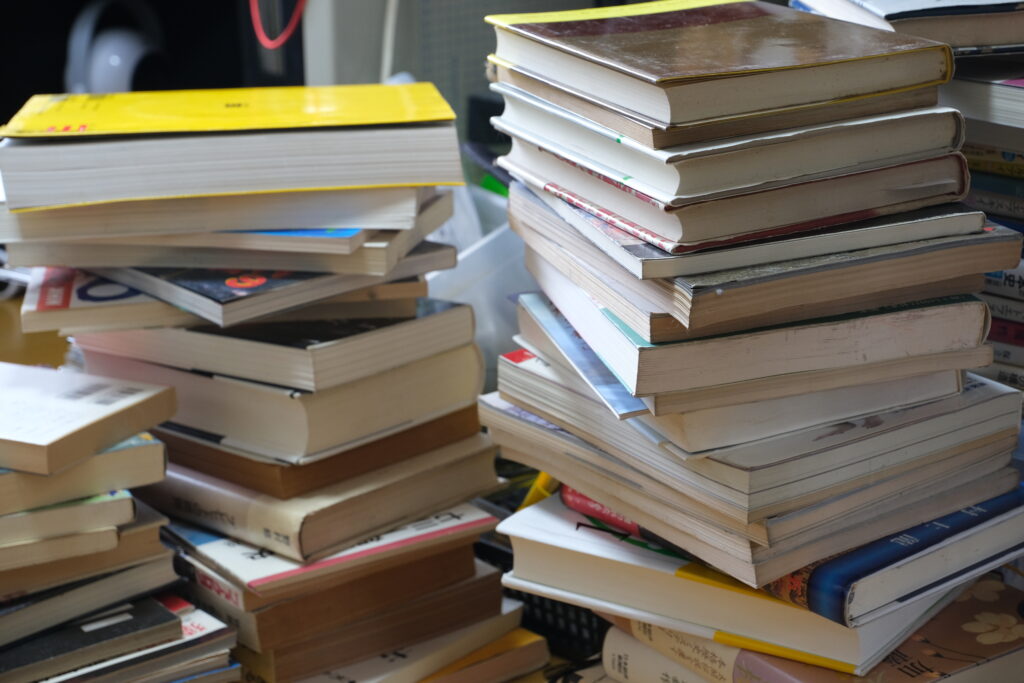
ここからは、日本史学習におすすめの教材を紹介します。日本史の学習は、前述したとおり「通史学習」「単語の暗記」「志望校の出題形式に合わせた問題演習」の順に学習を進めます。
各ステップに応じて、使用する教材が異なるので、おすすめの教材と具体的な使い方をチェックしていきましょう。
【通史学習】おすすめ教材1:『中高6年間の日本史が10時間でざっと学べる』
この本は、日本史の基本的な項目を整理したもので、導入として内容を把握するのに役立ちます。「暗記が苦手」「日本史に関する基礎知識がほとんどない」そんな受験生にもおすすめの一冊です。
タイトルのとおり、中学レベルの基礎的な内容から学び直せるのでとっつきやすいでしょう。
【通史学習】おすすめ教材2:スタディサプリ
歴史の流れをより正確につかむには「スタディサプリ」の映像授業がおすすめです。映像の教材は、参考書と比べてペース管理がしやすく、スムーズに学習を進められます。
具体的な使い方は以下のとおりです。
- Step.1 テキストを印刷し、該当箇所を開く
- Step.2 動画を視聴する
- Step.3 テキストや参考書に、授業で強調された重要な点を書き込む
- Step.4 確認テストを解く
日本史や世界史などの社会科系の科目は、学校の授業進度が遅いことも多いので、映像授業を活用し、授業内容を先取りしましょう。
【単語暗記】おすすめ教材3:『山川詳説日本史ノート』
山川詳説日本史ノートは、山川出版社の教科書に準拠した穴埋め形式の参考書です。教科書よりも簡潔に歴史の流れがわかるように文章がまとめられています。
いきなり一問一答に取り組むと歴史の流れを見失ってしまう可能性があるので、前後の文章もきちんと読みながら知識を定着させましょう。
スタディサプリなどと並行して取り組み、高校3年生の夏休みには単語の暗記が仕上がっているのが理想です。具体的な使い方は以下のとおりです。
- Step,1 文章中の( )に入る単語を別のノートに書き出してテストする
- Step.2 半分以上埋まらない場合は、教科書を見ながら埋める
- Step.3 丸つけをして、間違った単語の( )に印をつける
- Step.4 間違った単語のまわりの文章を3回読んで覚える
- Step.5 1単元分繰り返す
【単語暗記】おすすめ教材4:『山川一問一答日本史』
歴史の流れに沿って基本的な単語を覚えられたら、受験本番までは効率よく単語を覚えていく作業に移行してください。山川一問一答日本史を活用し、時間をかけなくても単語が出てくるように訓練しましょう。おすすめの活用方法は以下の手順です。
- Step.1 単語を隠して、覚えているかテストする
- Step.2 覚えていなかった単語に印をつけて、覚え直す
- Step.3 もう一度全ての問題を解く
- Step.4 すべての単語を覚えるまで、間違えた単語のみ1〜3を繰り返す
旧帝大や早慶などの難関大学を受けない場合は、出題頻度の低い単語はひとまず飛ばしても大丈夫です。ポイントは、「1周目は書いてテストする」ということです。日本史でも難しい漢字や紛らわしい単語は多いため、一度書いて確認するようにしましょう。
【問題演習】おすすめ教材5:実力をつける日本史100題
この問題集は、実際の入試問題などを集めた実践形式の問題集です。穴埋め形式の問題も多いですが、記号問題も半分以上あるため、流れの確認をしながら分野ごとに実践演習を進められるでしょう。
解説が詳しく記載されているため、解いた後にきちんと解説を読み込んで、知識の定着を図りましょう。正解していた問題も「たまたま正解していた」という可能性があるので、正解していたとしても必ず解説を読むようにしてください。
- Step.1 問題を解く
- Step.2 間違えた問題には印をつける
- Step.3 正解していた箇所も含めて解説をすべて読む
- Step.4 解説を読んで知らなかった単語は覚え直す
【問題演習】おすすめ教材6:山川日本史論述問題集
日本史の論述は大学によって傾向が大きく異なりますが、オーソドックスな論述演習に取り組めるのがこの問題集です。
解説にも用語や歴史の流れが詳しく書いてあるので、1冊やりきれば頻出分野の論述で困ることはなくなります。この参考書で基本を押さえた後、志望校の形式や傾向にあわせた過去問や問題集に進むのがおすすめです。具体的な使用手順は以下のとおりです。
- Step.1 記述問題を解く
- SStep.2 解説を読んで記述に盛り込むべきポイントを押さえる
- Step.3 解説の内容を意識してもう一度論述に取り組む
- Step.4 基礎ができたら、志望校の過去問を実践する

【要注意】やってはいけないNG勉強法

ここからは、日本史学習を進めるうえで、注意すべきNG勉強法を紹介します。誤った方法で学習を進めると、効率が低下してしまう恐れがあるので、NGポイントをしっかりと押さえておきましょう。
NG勉強法1:一問一答に頼りすぎる
「暗記しなければ!」と躍起になって一問一答集に頼りすぎるのは危険です。一問一答集は便利な暗記ツールですが、それだけではさまざまな形式の問題に対応する力は身につきません。
通史を行い、地図や図表を資料集で確認してから問題集で応用力を養うなど、バランスよく学習しましょう。
NG勉強法2:文化史を後回しにする
文化史はとっつきにくく、重要度が低いように感じるため、後回しにしがちです。ただし、日本史を得点源にしたいと考えているのであれば、対策は必須なので注意しましょう。
また、文化史は暗記の量が膨大であるため、通史を行う際に、関連付けながら学習するのがおすすめです。通史と並行して行うことで、効率よく学習を進められるでしょう。
まとめ
日本史攻略には、通史の理解が不可欠です。やみくもに単語を暗記するのではなく、まずは歴史の流れを把握し、全体像をつかんでください。
その後、穴埋め問題集で基礎を固め、一問一答で知識を肉付けしたうえで、出題形式に合わせた問題演習を行いましょう。
最も重要なのは、日本史は丸暗記するだけでは点数が上がらないということです。流れを理解していないと正答できない問題が出題されるので、流れのなかで単語を覚えて、志望校形式に合わせたアウトプットに取り組みましょう。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。

















