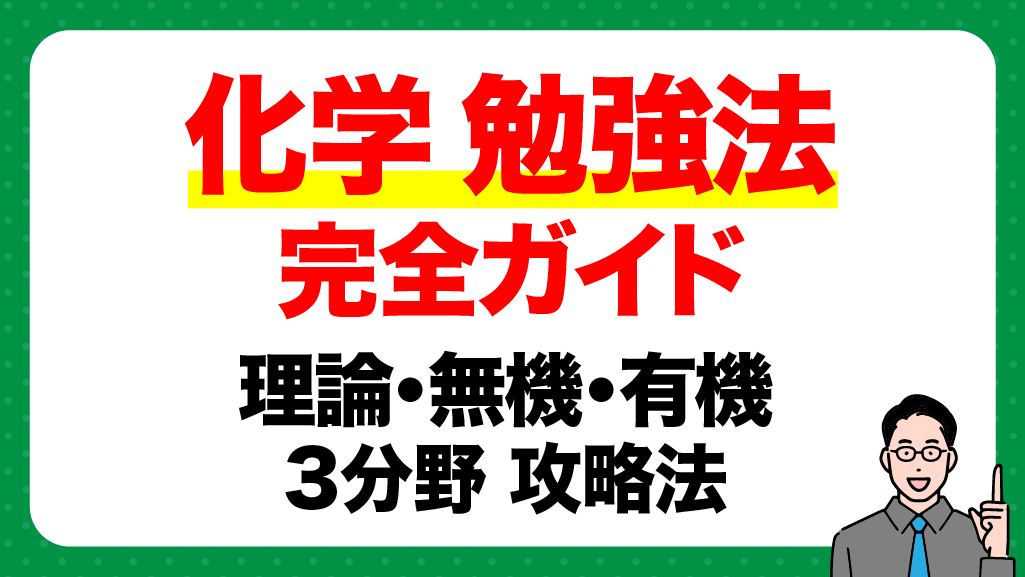
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
「化学での受験を考えているけど、どうやって勉強したらいいか分からない」
「苦手を克服して化学をしっかりと得点源にしたい」
こんな悩みはありませんか?
高校化学の単元は大きく分けて3分野に分かれています。
- 理論
- 無機
- 有機
それぞれに合わせた対策や準備をすることで、化学の成績を伸ばすことができます。
本記事では化学の各分野の特徴や勉強法・おすすめの参考書や問題集を紹介します。
では早速それぞれ見ていきましょう。

高校化学の3分野「理論・無機・有機」の特徴

まず高校化学は以下の3分野に分かれています。
- 理論
- 無機
- 有機
本章では分野ごとの特徴を解説します。
最重要の理論分野
まず理論分野は高校化学の中でも最も重要な分野といえます。
その理由は以下の2つです。
- 他の2分野(無機・有機分野)に関連する内容を含むから
- 入試で配点が高いことが多いから
理論分野は化学の基礎となる内容が多く含まれている分野です。
そのため理論分野で理解できていないことが多いと、無機・有機分野でもつまずいてしまう可能性が高いです。
化学の勉強を始める際は理論分野を押さえてから、他の2分野の勉強を始めると良いでしょう。
また、2024年の共通テストの配点からもわかるように、理論分野は配点が高く、理論分野をマスターすることは志望校合格に不可欠です。
- 第1問:理論(20点)
- 第2問:理論(20点)
- 第3問:無機(20点)
- 第4問:有機(20点)
- 第5問:理論&有機(20点)
このように半分近くが理論分野からの出題であること、また有機・無機分野も理論分野を理解していないと解けないことから、理論分野を勉強することが高得点獲得への近道であることがわかります。
理論分野を勉強することが化学での点数を上げる最短の道筋であると言えるでしょう。
高得点を狙いやすい無機分野
次に無機分野の特徴を解説します。
無機分野の特徴は大きく以下の2つです。
- 暗記要素が強い
- 高得点を狙いやすい分野
無機分野は、他分野と比較して暗記の要素が強く、しっかり演習をこなせば安定して得点を取ることができます。
なぜなら無機分野の入試問題は、一部の難関大学以外では単体での出題が多く、複合的で難しい問題が出ることがほとんどないからです。
理論分野の点数配分が高いですが、無機分野も2〜3割程度の点数配分で出題されることが多いです。
早めに勉強して安定して点数を取れるようにすると良いでしょう。
総合力を問われる有機分野
最後に有機分野の特徴を解説します。
有機分野の特徴は以下の2つです。
- 暗記だけでは問題が解けず、問題のレベルが高くなりやすい
- 頻出の構造決定問題は有機分野の総合力を問われる
有機分野は学ぶ分野が限られているため暗記量が少ないと思われがちですが、実は意外にも覚えることが多い分野です。
また暗記だけで解ける問題は少なく、計算問題もあるため、暗記した内容をベースに問われる応用問題が多いのも特徴です。
そのため「総合力」が問われることが有機分野の特徴であり、暗記・演習・応用をバランスよく学習することが重要です。

高校化学の勉強法3ステップ&ステップ別おすすめ問題集・勉強法

ここからは高校化学の勉強法3ステップとステップ別のおすすめ問題集を紹介します。
本記事では以下の3ステップ毎に解説します。
- 教科書レベル理解
- 問題演習
- 過去問演習
それぞれ見ていきましょう。
ステップ1:教科書レベル理解
1つ目のステップは「教科書レベル理解」です。
どんな科目であっても、教科書レベルの理解が基礎となります。
とくに化学では計算問題や総合力が試される構造決定問題などでは、ただ単なる暗記ではなく、基礎を根本から理解している必要があります。
さまざまな問題形式に対応できるように、まずは教科書レベルの内容を理解することから始めましょう。
教科書レベルの理解をするためには「スタディサプリ」「宇宙一わかりやすい高校化学」が有効です。
教科書レベルの理解をする上での注意点は「先取り学習」をすることです。
学校の授業は進度が遅く、全範囲の学習が終わるのが受験期ということもよくあります。
ただ入試では教科書の範囲はもちろん、応用問題も出題されるため、教科書レベルの学習は早めに終わらせる必要があります。
受験期までを逆算し、志望校のレベルに応じてこれから紹介する3ステップも終わらせられるようにしましょう。
さらに、スタディサプリのような映像授業を上手に活用するために必要な「4つの勉強のコツ」を紹介します。
- テキストを印刷して手元で内容を確認できるようにする
- まずはテキストを見過ぎず、集中して映像授業を視聴する
- 授業で解説された問題を自力で解く
- 問題演習を繰り返す
ステップ2:問題演習
2つ目のステップは「問題演習」です。
教科書レベルの理解が出来たら、基本問題の演習を繰り返し行い、自分に「知識」として定着をさせましょう。
知識を暗記することで単純な問題を解けるようになりますが、入試レベルでは自分が持っている「知識」を活用することが求められます。
また、問題演習に取り組むことで「自分ができていないこと」や「教科書レベルに戻らないといけない箇所」に気づくことができます。
教科書レベルの知識を活かせているか・苦手な分野はないかを洗い出すためにも、問題演習を繰り返し行いましょう。
問題演習で使える問題集としては、『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』などがあります。
早慶理科大や旧帝大クラスを目指すのであれば『重要問題集』を解きましょう。
最難関大を志望する人は『化学の新演習』まで取り組めると良いでしょう。
これらの問題集を活用するために意識したい「6つのコツ」も紹介します。
- 時間を計って問題を解く
- 解説を隅から隅まで読む
- 間違えた問題は後日解き直せるようにチェックをつける
- 間違えた問題に関連する内容を参考書・教科書で復習する
- 間違えた問題を解き直し、解けなかったらチェックをつける
- そこでも間違えたら再度チェックをつけ、正解するまで何度も日をあけて解く
より詳しい問題演習の取り組み方については、以下の記事を参考にしてください。
ステップ3:過去問演習
3つ目のステップは「過去問演習」です。
過去問演習は赤本や共通テストの過去問・予想問題集を活用して解きましょう。
その際には以下の3つのポイントを意識して、取り組みましょう。
- 本番と同じ時間配分で解く
- 志望校と同じ回答方式(マーク式・記述式)に慣れる練習をする
- 計算ミスを減らせるように計算用紙を綺麗に書く
過去問演習は入試対策をする上で最も重要なステップです。
今まで学習した基礎知識を活かして、それぞれの大学・学部に合わせた出題形式に慣れることで、本番でも落ち着いて実力を発揮できます。
遅くとも入試の2ヶ月前には過去問・予想問題集に取りかかり、本番の出題形式や時間配分に意識して取り組みましょう。
過去問・予想問題集を解く際に取り組みたい「7つのコツ」は以下の通りです。
- 本番と同様の時間制限で計って解く
- 丸付け&間違えた問題に印を付ける
- 得点を計算して記録する
- 間違えた問題はチェックをつけて、後日解きなおす
- 間違えた箇所に関連する教科書や参考書を読み、理解する
- チェックをつけた問題を再度解く
- そこでも間違えたら再度チェックをつけ、正解するまで何度も日をあけて解く

まとめ
本記事では化学の勉強法や参考書・問題集について解説しました。
この記事を読んで自分が今どのステップにいるのか・どんな勉強をしたら良いのか、理解できたのではないでしょうか。
ぜひ今回の記事を参考に自分にぴったりの参考書や問題集・その勉強法を選び、活用し、志望校合格を目指しましょう。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。




















