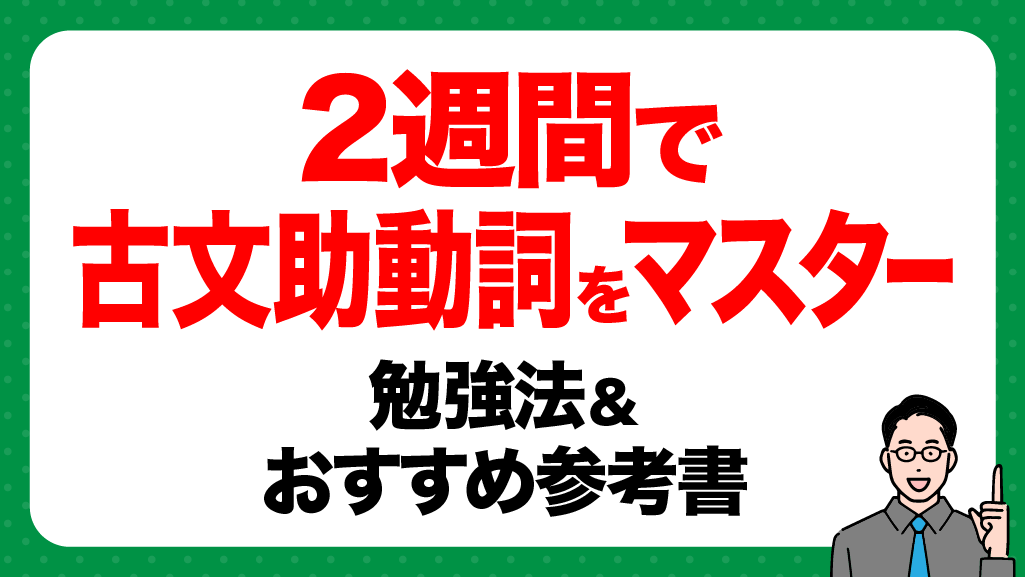
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
古文読解の要となるのが助動詞です。助動詞の学習をおろそかにすると、古文で高得点を獲得するのは難しくなってしまいます。
しかし、助動詞は一つひとつにたくさんの意味があって、複雑なので、「暗記は苦手…」「古文は全然頭に入ってこない」そんな悩みを抱えている受験生も多いでしょう。
本記事では、助動詞に苦手意識を持つ受験生に向けて、2週間で助動詞を完璧に習得できる勉強方法を解説します。古文助動詞の勉強法は以下の動画でも解説しているので、ぜひご覧ください。

古文 助動詞を覚えるべき理由とは?

「助動詞ってたくさんあるけど、本当に全部覚える必要があるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。確かに種類は多いですが、出題頻度は助動詞によって異なるため、すべて覚えていなくても回答できる問題もあるはずです。
しかし、この記事を読んでいる受験生・高校生は、必ず助動詞を全種類覚えるようにしてください。助動詞をすべて覚えた方がよい理由について以下で解説します。
理由1:文の意味を正確にとらえるため
助動詞を正確に理解する必要があるのは、文章の重要な意味を左右するからです。
現代語で例えるなら、「〜した」「〜しよう」「〜しない」「〜したい」など、文末に付く部分が助動詞にあたります。文の前半が同じでも、文末が異なれば意味は大きく変わるのが理解できるしょう。
古文の助動詞も同様に、文の意味を決定づける重要な要素です。助動詞を曖昧に捉えてしまうと、文意を誤解し、なんとなく読み進めてしまい、とんちんかんな和訳になってしまうことがよくあるのです。だからこそ、古文の助動詞学習は最重要課題なのです。
理由2:どのような文章が出題されても対応できるようにするため
前項で紹介したように、古文において助動詞は非常に重要です。そのため、教科書や参考書に掲載されている助動詞は、全て覚える必要があります。覚えるべき助動詞は以下のとおりです。
- 未然形接続:る、らる、す、さす、しむ、ず、じ、む、むず、まし、まほし
- 連用形接続:つ、ぬ、たり、き、けり、たし、けむ
- 終止形接続:らむ、べし、まじ、らし、なり、めり
- 体言・連体形接続:なり・たり・ごとし
- 特殊(サ行の未然形・四段の已然形):り
入試ではあまり出題されない助動詞もありますが、重要な意味を持つものが多くいため、しっかり押さえておきましょう。
また「ごとし」は現代語にも近いため出題されにくい傾向にありますが、それ以外の助動詞はすべて出題される可能性が高いという意識を持っておきましょう。

助動詞で覚えるべき3つのポイント
助動詞はすべて覚える必要がある一方で、具体的に何を覚えるかは限定的です。覚えるべきポイントは以下の3つです。
- 接続:その助動詞の上にくる用言(動詞など)の活用形がなになのか
- 活用:その助動詞をどのように活用するか
- 意味:その助動詞がどのような意味を持っているか
参考書には多くの情報が載っていますが、上記の3つが中心となります。まずはこの3つを集中的に覚え、複数の意味を持つ助動詞は、問題演習をとおして見分ける力をつけていきましょう。
古文助動詞の効率的な覚え方3選

助動詞を覚える際にオススメの勉強法は以下の4つです。
- 分割して反復学習
- 歌に合わせて覚える
- 問題演習しながら覚える
- 「例文+現代語訳」を何度も繰り返し覚える
それぞれの方法に良さがあるので、自分に合った学習方法で勉強を進めましょう。
覚え方1:分割して反復学習
基本的な暗記法は「接続ごとにまとめて覚え、活用や意味も反復する」というものです。分割することで頭が整理しやすくなり、実用的でしょう。具体的なステップは次の通りです。
接続を覚える際は「ずは未然形接続、まじは終止形接続…」と別々に覚えるのではなく「る・らる・す・さす・しむ…は未然形接続!」とまとめて覚えるのが効率的です。
まずは接続ごとに、何度も声に出して覚えましょう。
- 未然形接続:る、らる、す、さす、しむ、ず、じ、む、むず、まし、まほし
- 連用形接続:つ、ぬ、たり、き、けり、たし、けむ
- 終止形接続:らむ、べし、まじ、らし、なり、めり
- 体言・連体形接続:なり・たり・ごとし
- 特殊(サ行の未然形・四段の已然形):り
これは助動詞を接続別にまとめたもので、未然形、連用形、終止形、連体形、特殊形の順番に並んでいます。
接続を覚える際は「る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほしは未然形接続!」このように、まとめて覚えるのがポイントです。
まずは、「接続」ごとに、何度も唱えて覚えましょう。寝る前の15分、通学時間、お風呂の中など、スキマ時間を見つけて勉強するのがおすすめです。
次に、接続ごとに活用と意味を覚えます。
「まずは未然形接続の助動詞」と決めたら、3日間はひたすら「るの活用は、れ・れ・る・るる・るれ・れよ…」と唱えます。同様に、同じ意味の助動詞をセットで覚えましょう。
このように、意味や活用を覚えるときも、分割して覚えていきましょう。このとき、同じ意味の助動詞がある場合はセットで覚えると効率的です。
助動詞には似た意味だけど、微妙に違うものがいくつかありますが、いきなり細かい意味の違いまで覚えようとするとパンクしてしまう恐れがあるため、まずはシンプルに似た意味はまとめて1つで覚えるのがおすすめです。
覚え方2:歌に合わせて覚える
次に紹介するのは、替え歌を活用して助動詞を覚える方法です。歌で覚える方法は、助動詞の「接続」を覚えるのに非常に効果的です。替え歌を活用した方法は、古典ではおなじみの勉強方法であるため、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
以下で紹介する歌を何度も繰り返して記憶に定着させましょう。1日10回以上を目安に繰り返し学習してください。2週間も繰り返せば、ほとんど覚えられるはずですよ。
練習の替え歌として一番有名なのは「もしもしかめよ」の替え歌です。
このうたを接続ごとに分けて歌うことで、接続も一緒に覚えられるという利点があります。
上記の例でもいいですし、学校で習ったもの、自作の歌でも構わないので、繰り返し歌って知識を定着させましょう。
覚え方3:問題演習しながら暗記する
暗記した知識が実戦で使えるかどうかを問題演習で試してみましょう。単語ではなく、文章で出題された時の即座に出てくるよう訓練しておいてください。実際に以下の問題演習をやってみましょう。
問:次の空欄に助動詞「ぬ」を適切な形に活用させて入れよ。
人にも、おほやけにも、失せかくれ( )たる由を知らせてあり。(2016年 学習院大学)
まず、着目すべきは空欄の後ろです。後ろには、助動詞「たり」の連体形「たる」があります。「たり」の接続を歌から思い出してみてください。「たり」は歌の中で、接続は連用形だと覚えました。
連用形接続ということは、この助動詞の前に来る用言は連用形になるということなので、「ぬ」を連用形に直せば正しい形になります。よって、答えは「ぬ」の連用形である「に」となります。
丸暗記はできていても、文章で出題されると、判断できないケースが多いです。暗記と平行して問題を解くクセをつけましょう。問題集は後ほど紹介するので、あわせてご覧ください。
覚え方4:「例文+現代語訳」を何度も繰り返し覚える
短い古文の例文と現代語訳を一緒に、ニュアンスをつかみながら覚える方法も効果的です。
具体的には、単語帳に載っている例文を覚えたり、問題集で演習するときの短文をまるまる覚えたりするのもおすすめです。
こちらのほうが「完了」や「推量」などの用語だけで覚えるよりも、記憶に定着しやすいでしょう。また、助動詞が文中に出てきた時に、それがどんな意味を持っているかがつかみやすくなるはずです。
覚え方のワンポイントアドバイス
助動詞をなかなか覚えられない、というひとは、時間をかけて少しずつ覚えようとしていませんか?
古文の助動詞は、英語の文法に比べて覚える量は少ないため、短期集中で一気に覚え、その後は定期的な復習で定着させるのがおすすめです。
助動詞は全部で30個程度です。1週間で15個ずつ、1日3つに絞って学習すれば、復習日も含めて2週間で習得可能であるため、一気にマスターしてください。
ただし「他の勉強と平行して行うのが大変」「なかなか古文に手を付けられない」そんな人には、コーチング型の学習塾がおすすめです。実際の所は、2週間まるまる古文だけに時間を割くことができるのは少ないはずなので、全科目のバランスを見て、学習計画を作成してくれるでしょう。
以下の記事で、おすすめのコーチング型塾を紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

古文の助動詞暗記におすすめの参考書
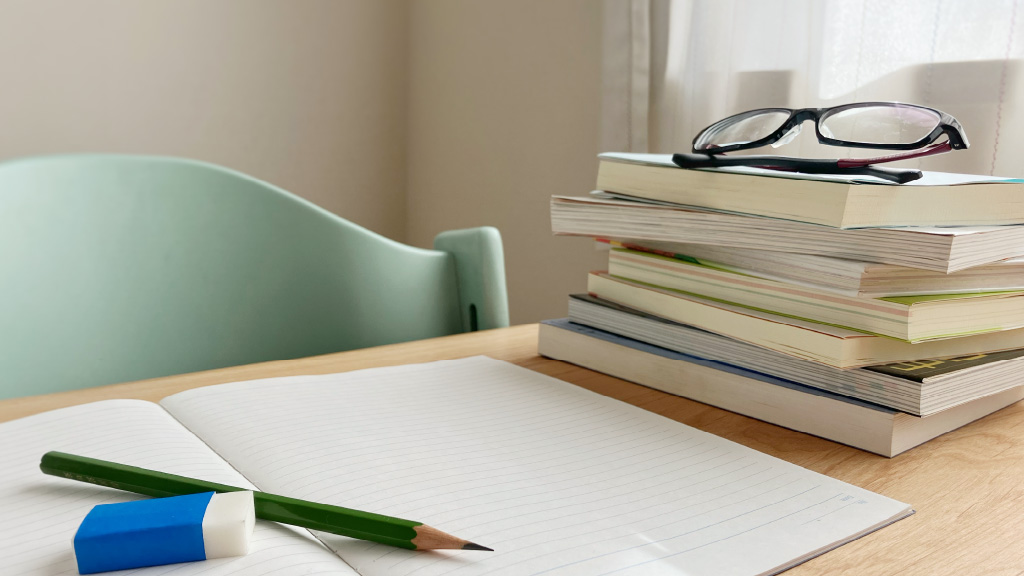
助動詞を暗記しただけでは、試験に対応できないため、問題集や参考書を使って演習を重ねましょう。問題集や参考書の演習で、助動詞の意味を正確に見極める力をつけてください。
助動詞の意味を正確に見極める力があってはじめて、文法問題が解けるようになるのです。
以下で、おすすめの参考書や具体的な勉強法を紹介していきます。
『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』
この参考書は、助動詞だけでなく、文法全体を網羅しています。意味ごとに小分けにして説明されており、見分け方も丁寧に解説されているためおすすめです。
日栄社『発展30日完成古文 高校中級編』
こちらも文法全体を扱っています。後半は文章問題なので、読解の中で文法を復習できます。特に注目すべきは、品詞分解の解説がある点です。
品詞分解とは、文章を単語ごとに区切り、助動詞の意味や敬語の用法などを書き込んでいく作業です。英文解釈に近く、文章の意味を正確に捉えるために有効でしょう。
この参考書を使うときはぜひ「品詞分解」で、出てきた助動詞の意味をすべて確認するようにしてください。
「中級」が難しい場合は「初級」や、文法の演習だけに焦点を当てた「古典文法サブノート」を活用するのもよいでしょう。
助動詞の使い方をマスターするための「参考書の使い方」
問題集は、ただ解くだけでは十分ではありません。長文の中で助動詞の意味を見分けられるように、以下のステップで学習しましょう。問題集の勉強法は次のとおりです。
- STEP1:暗記事項を一旦丸暗記する
- STEP.2:問題集をコピーし、品詞分解しながら解く
- STEP.3:答え合わせをし、間違ったものだけでなく「偶然正解したもの」にも印をつける
- STEP.4:解説を読み、見分け方を理解し、抜けていた文法事項をその場で暗記する
- STEP.5:1周終わったら、間違えた問題に絞って2周目
これらの参考書は、頭に残るまで何周も繰り返すことが重要です。品詞分解する際は、助動詞だけを○で囲み、横に意味を書き込むようにしてください。敬語も一緒に書き込んでいけばさらに効果が高まるのでおすすめです。
また、問題と品詞分解を照らし合わせ、答え合わせで正誤を確認し、たまたま正解した問題は、必ず解き直しましょう。ここで抜けていた助動詞や意味の見極め方や忘れていた助動詞を覚え直せば問題ありません。
今回紹介した問題集であれば、1章につき30分程度を目安に解き進めましょう。
以下で、高校古文の敬語の覚え方を解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
問題週を2〜3週すれば、だいたいの内容を暗記できるでしょう。逆に1周目で覚えられる人
はほとんどいないので、安心して勉強を進めてください。

まとめ
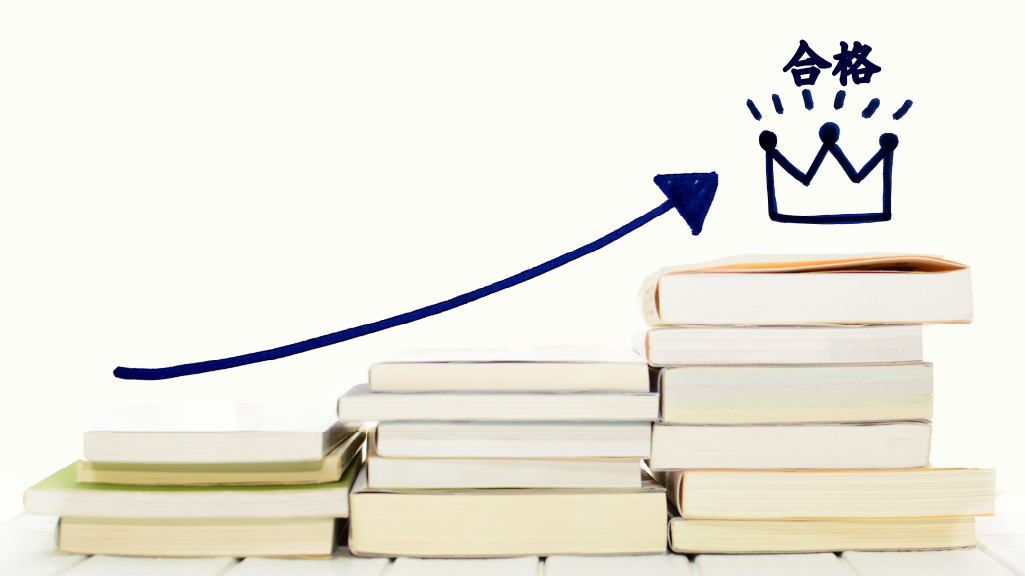
今回は古文文法で非常に重要な「助動詞の覚え方」について解説しました。重要なポイントは以下の4つです。
- 「接続・活用・意味」を必ず覚える
- 助動詞は全て覚える!
- まとめて唱える、歌で覚える
- 問題集でアウトプット
まずは、接続を歌やまとまりで覚え、そこに活用と意味を紐付けましょう。声に出して、繰り返し学習することが重要です。
そして、問題集で演習を重ねましょう。品詞分解で、助動詞の見極めを繰り返し練習できます。助動詞は古文読解の根幹です。助動詞と単語さえ覚えれば、古文を正確に読解できるようになります。
この分野でつまずく方も多いですが、短期間で集中して覚え、古文を得意科目に変えましょう!
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。














