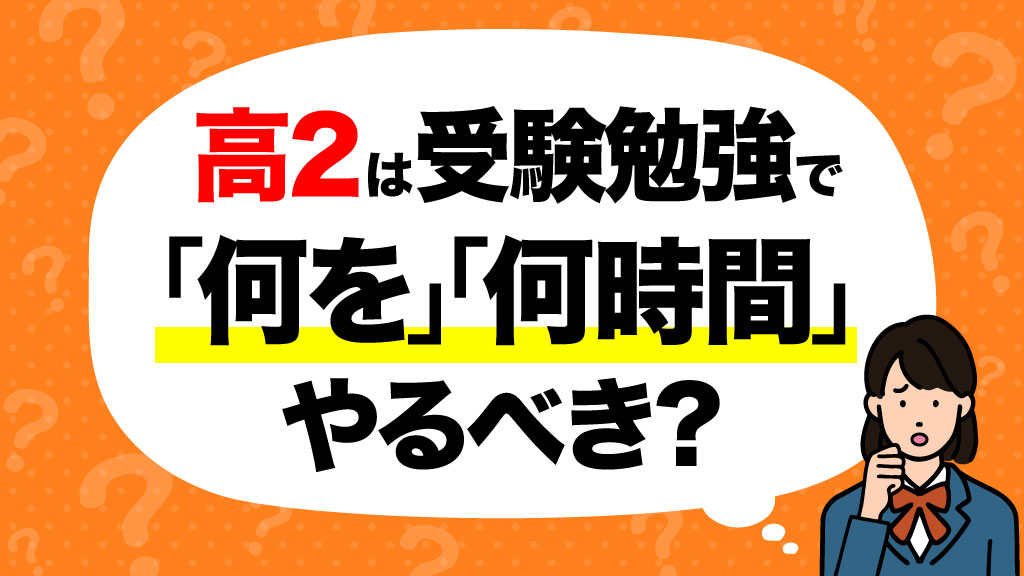
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
高2の早い段階から受験を意識して、勉強を進めている人もいるかと思います。受験勉強は早くから始めるほど有利になるため、是非とも正しい勉強方法で受験まで乗り切りたいところです。
しかし、いざ取り組むとなると、
- 高2から受験勉強するのであればどこまで進めればいいの?
- 具体的にどうやって勉強すればいいの?
- とにかく参考書をたくさん解けばいいの?
など、受験勉強に関してわからないことが浮かぶ人も多いでしょう。
今回の記事では、高2から受験勉強を始めるうえで押さえておきたい勉強方法や計画の作成方法などについて、詳しく解説します!

受験勉強は高2からスタートさせよう!
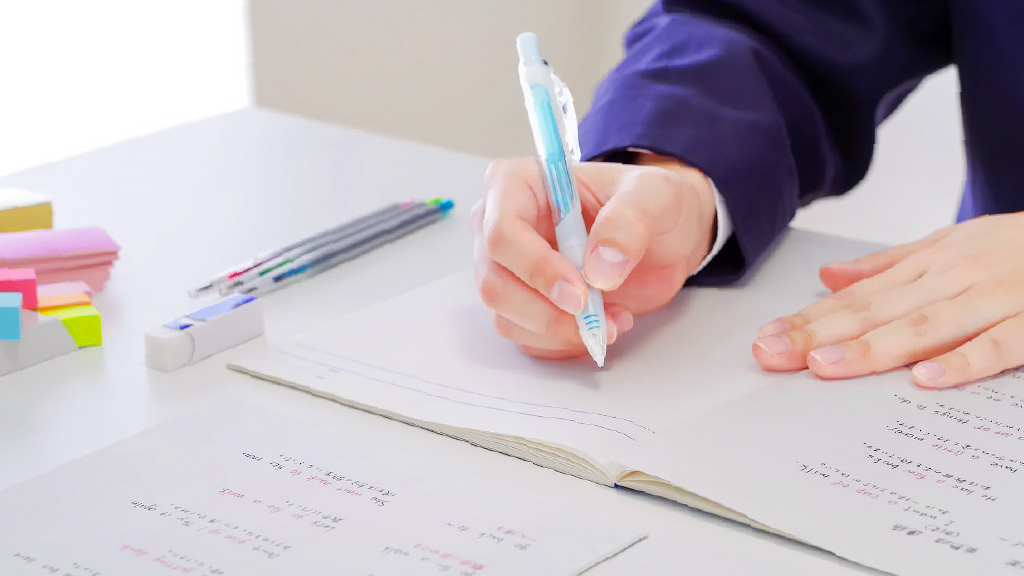
受験勉強は高2からスタートさせましょう!もちろん、高2より早い段階で始めても構いません。
大学受験は高校受験と異なり、希望の学部・学科ごとで入試問題の傾向や必要な勉強量が変わってきます。必要な勉強量は高校受験より圧倒的に多くなるケースがほとんどです。
そのため早めに対策を立てて勉強を始めないと、基礎や応用力が身に付かず、受験間近の時期に慌てることになります。
とくに、勉強に時間がかかる英語と数学が苦手な人は、絶対に高2のうちからスタートさせるべきです。英語は単語や文法などの基礎を固めてからメインの長文読解に取り組む必要がありますし、数学もたくさん問題演習をこなしてあらゆる出題内容に対応できるようにしなければなりません。
さらに「社会・理科・数学3」は学校の授業進度が遅いことが多いため、高2から独学で予習しないと受験に間に合わないことが多いです。
早めに志望校を決めてから受験勉強を始め、高2の間に基礎を固めておけば、高3になってから受験で最も重要な問題演習の時間をたっぷり確保できます。
受験では基礎知識がそのまま出題されることはほとんどありません。それよりも、勉強した基礎知識を活かしながら問題を解くことが重要であるため、「演習時間を確保できたかが合否を決める」と言ってよいでしょう。
高2の理想の勉強時間は?

志望校合格に必要な勉強時間は大学ごとで異なりますが、受験全体で見るとおよそ「3,000時間前後」と言われています。
それでは3,000時間を達成するために、高2の間でどのくらい勉強すればいいのでしょうか?高3の勉強時間を「休日10時間・平日4時間」と仮定して考えましょう。
高3の4月から受験本番までは約300日です。休日約100日・平日約200日なので、高3で勉強できる時間の目安は、以下のようになります。
(平日4時間×200日)+(休日10時間×100日)=約1,800時間
そのため高2で取り組むべきは、3,000ー1,800=約1,200時間となります。
約1,200時間を満たすため、高2の間に各時期で以下を目安に勉強しましょう。
| 時期 | 勉強時間の目安 |
|---|---|
| 1学期 | 平日2時間+休日4時間(約250時間) |
| 夏休み | 毎日4時間(約160時間) |
| 2学期 | 平日2時間+休日5〜6時間(約300時間) |
| 冬休み | 毎日6〜7時間(約80時間) |
| 3学期 | 平日3時間+休日7〜9時間(約360時間) |
高2の間でこれくらい勉強していれば、高3になってから「平日3〜5時間・休日8〜10時間」くらいの勉強ができるようになります。
ただし、これはあくまでも目安の時間です。より具体的な勉強時間は、学校の課題量や部活との兼ね合いなどで異なります。その点も含めて「高2生が学校と受験勉強を両立する方法について」で解説しているので、参考にしてください!

高2生が受験勉強前に取り組むべき「学習計画」の具体的な作成方法

高2から受験勉強を始める前に、必ず勉強計画を作成しましょう。
勉強計画がなければ、自分の勉強が志望校合格に向けて正しく取り組めているかわかりませんし、方向性が間違っていた際の軌道修正も難しくなります。
勉強計画は以下の手順で作成しましょう。
- 志望校を決めよう
- 志望校の目標点数を把握する
- 志望校と自分の学力との差を把握する
- 必要な参考書を調べる
- 年間スケジュールを作成して毎日の計画に落とし込む
1.志望校を決めよう
一番最初にやるべきなのは志望校決めです。大学受験では志望校によって必要な勉強量や問題の傾向が大きく異なります。さらに、文系・理系かによっても取り組むべき科目の優先度は変わります。
志望校を決めないと目標に合わせて勉強を進められないため、必ず最初に設定しましょう。
志望校を決める際は、ひとまず現状の偏差値を気にせず、純粋に自分が一番行きたい大学を選べばOKです。仮に現時点の成績が志望校に届かなくても、早めに勉強を始められれば、十分点数は伸ばせます。
2.志望校の目標点数を把握する
志望校を決めたら目標点数を把握しましょう。この点数が、勉強計画を作成する際に必要なゴールとなります。志望校の目合格最低点については「パスナビ」というサイトに掲載されています。
ただし、合格最低点をそのまま目標点数にするのは少し不安が残るでしょう。「出題傾向の変化」など不測の事態が起きた場合に、入試本番で失敗する可能性があります。
そのため、目標点数は「(過去3年間の合格最低点の平均)×1.1倍」を目安に設定しましょう。
3.志望校と自分の学力との差を把握する
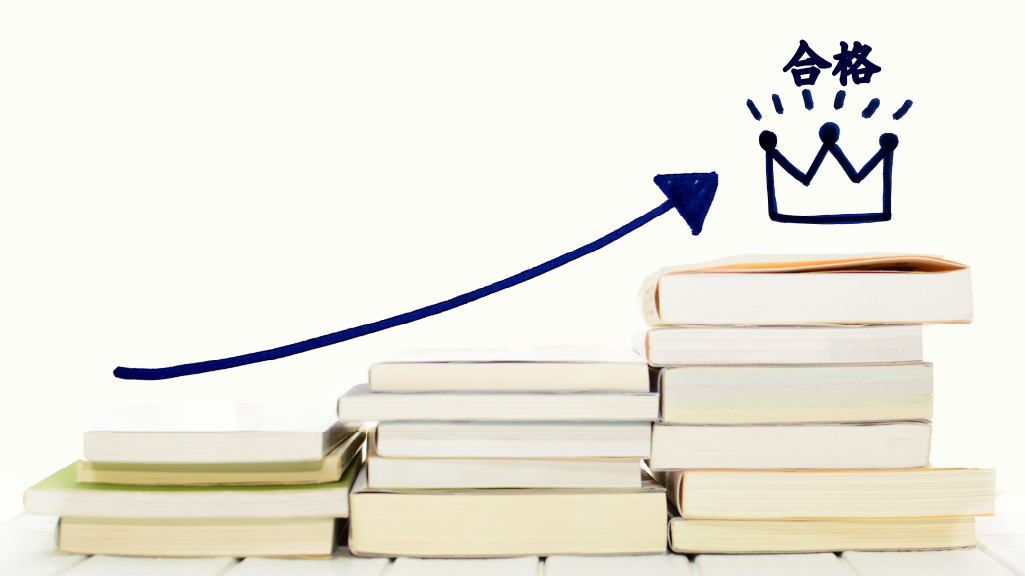
志望校の目標点数を把握したら、自分の現在の成績と比較して「どれくらい実力を伸ばせば合格できるのか」を調べましょう。
自分の現在の成績を把握するには、模試を受けるのが手っ取り早いです。本番に近い環境下で試験を受けるため本来の実力を発揮しやすく、より正確に自分の成績を把握できます。
また、志望校の過去問を解くことでも自分の実力を把握できます。過去問を解く際は、実際の試験と同じ時間で解きましょう。
4.必要な参考書を調べる
合格最低点と自分の実力の差が分かったら、差を埋めるための勉強内容=参考書を調べましょう。
インターネットで「東京大学+数学+参考書」のように、大学名・科目・参考書で検索すれば、必要な参考書が出てきます。
このときに重要なのは、1つの情報源だけを信用しすぎないこと。1つの記事や動画だけだと「その記事を書いた人にとって最適な参考書」がヒットする可能性が高く、あなた自身に最適なものが出てくるとは限りません。必ず複数の情報源にあたって、自分に必要なものを絞り込んでいってください。
5.年間スケジュールを作成して毎日の計画に落とし込む
目標までに足りない点数を把握したら、それをもとに勉強計画を作成しましょう。まずは年間スケジュールを作成して、「夏休みまで」「冬休みまで」というように大まかな時期ごとで必要な勉強を洗い出します。
年間計画の次は週間計画を作成しましょう。週間計画では「どの参考書を」「いつまでに」「何ページ進めるか」という具体的なスケジュールまで落とし込みます。参考書レベルまでやるべき勉強を洗い出せれば、毎日取り組む内容に迷わないため時間を有効活用できます。

高2生が学校と受験勉強を両立する方法について

高2の段階では、周りの生徒も受験を意識していないので、ついつい直近にある定期テストや部活が優先になってしまいます。ですが、計画的に受験勉強を進めなければ受かるのが難しい以上、両立させることが重要です。
そこで、以下の2つの点についてコツを解説していきます。
- 定期テスト・学校の課題と受験勉強の両立
- 部活と受験勉強の両立
定期テスト・学校の課題と受験勉強の両立
まず最初に超えなければならないのが定期テストや学校の課題と、受験勉強の両立です。
ポイントは3つあります。
- 科目ごとの優先度を意識して勉強する
- ペースメーカーとしてテストを活用する
- 課題は時間を決めて取り組む
定期テスト勉強が受験につながる科目は優先度が高い
科目によっては定期テスト勉強がそのまま受験につながる場合もあります。数学・理科・社会が代表例です。
数理社は、学校の教科書で習った内容が入試に直結するので、定期テストを通じて教科書レベルの基礎知識を身につけておくことが重要です。
そのため、学校の課題や定期テストの勉強はかなり優先度が高いと思っておいてください。定期テストで毎回満点を狙うつもりで勉強すれば、自然と受験でも対応できる実力を身につけられます。
一方で、英語や現代文は学校で習った文章がそのまま受験に出る可能性は限りなく低いので、テスト直前以外は受験勉強の方が優先度が高くなることを覚えておいてください。
テストをペースメーカー&長時間勉強の機会と考える
上記のように定期テストの勉強が受験につながるケースではしっかり両立すべきです。とはいえそれ以外の場合であっても、定期テストを「受験勉強に向けたペースメーカー」として活用できます。
たとえば、「次の定期テストの勉強を始める前までに必ず英文法の参考書の1周目を終わらせる!」といった目標を持ちながら進めるのは非常に有効でしょう。
また、大学受験では「志望校用の対策+幅広い科目の勉強」が必要になります。そのため、受験生になったら「休日に最低10時間勉強」くらいはしないといけません。
とはいえ、受験生になってからいきなり長時間の勉強習慣を身に付けるのは難しいです。
しかし、定期テストの勉強を「早い段階から長時間勉強する絶好の機会」と捉えてトレーニングしておくと、受験生になってからスムーズに受験勉強へ切り替えられます。
学校の課題は時間を決めて取り組む
学校の宿題や予復習をダラダラと進めてしまうと、いくら勉強時間を確保しても、受験勉強に使える時間がかなり限られてしまいます。
そこで学校の宿題、予習、復習は制限時間を設けて、その時間内で終わる分だけ必死で取り組むようにしましょう。時間制限がある方が集中できるので、むしろ短時間で完璧に課題をこなせるようになる場合もあります。
部活と受験勉強の両立
高2の間は部活と受験勉強の両立についても考える必要があります。
本格的に受験勉強が始まるのは、一般的には高3になってからです。とはいえ、ここまで解説したように、受験生になってからいきなり1日10時間勉強するのはハードルが高いです。そのため、部活と学校の間で上手く時間を見つけて両立させ、勉強を進めましょう。
両立のために重要なことは以下の2つです。
- 勉強時間ゼロの日をなくす
- スキマ時間を活用する
勉強時間ゼロの日をなくす
部活と両立させるには、毎日少しずつでも勉強することが大切です。
部活をやっていると、大会で1日潰れたり練習で疲れたりすることもあるでしょう。その場合でも、「風呂上がりに少し数学の問題を解く」「大会前の待ち時間に英単語を少し暗記する」というように毎日取り組むことで、徐々に両立できるようになります。
1日30分でも15分でも構いません。とにかく勉強時間ゼロの日をなくすことに注力してください。
スキマ時間を活用する
部活が終わって家についてしまうと、その時点で疲れが押し寄せて勉強する気分にならないことも多いはず。
そのため部活が大変な時期には、部活が始まる前のちょっとしたスキマ時間を活用して少しでも受験勉強を進めるといいでしょう。
他にも、「登校中の電車で勉強する」「朝、HRの前に勉強する」「昼休みに勉強する」など、少しの積み重ねが重要です。

高2が受けるべき模試

高2生も、なるべく模試を定期的に受けておきましょう。
模試は実際の試験に近い時間配分や緊張感の中で問題を解くため、自分本来の実力が発揮されやすいです。本来の実力を把握できれば、志望校合格までに必要な学力差を正確に掴めるため、計画の修正にも役立ちます。
「高得点を取る自信がない」という理由で模試を受けないのはもったいないです。高2の前半くらいであれば、そこまで点数を気にしすぎる必要はありません。それよりも、実際の試験の雰囲気の中で、自分がどれくらい実力を発揮できるのか把握するほうが重要です。
受けるべき模試は次の通りです。
- 早慶、国公立志望→駿台全国模試
- 旧帝大、東工大、一橋大など→駿台全国模試+冠模試
- その他→河合全統模試
河合塾の模試は比較的多くの高校生に進められる模試です。どの大学を目指すのでもおすすめできます。難関大を目指すのであれば、駿台の模試をメインに受験するといいでしょう。
さらに「冠模試」と書かれている模試は、大学の過去問と同じ出題形式、同じ難易度になっている模試です。高2の時点では全く歯が立たないかもしれませんが、高3と混ざって受験できる機会なので、最難関大学を目指している人は、ぜひ受験してみてください!
こちらが実施時期をまとめたものです。参考にしてください。
| 時期 | 模試一覧 |
|---|---|
| 5月 | 第1回全統高2模試(河合) |
| 6月 | 第1回高2駿台全国模試(駿台) |
| 8月 | 第2回全統高2模試(河合) 河合冠模試(東大・京大・名大) 駿台Z会冠模試(東大・京大) |
| 10月 | 高2プライムステージ(河合) 第2回高2駿台全国模試(駿台) 第3回全統高2模試(河合) 河合冠模試(早慶・一橋・東工大) 代ゼミ駿台早大入試プレ |
| 1月 | 全統記述高2模試(河合) 全統共通テスト高2模試(河合) 高2アドバンスト(Z会・駿台) 各社共通テスト同日模試 駿台冠模試(旧帝大など) 河合冠模試(旧帝大など) 代ゼミ駿台慶大入試プレ |
| 2月 | 第3回高2駿台全国模試(駿台) |
高2から勉強する際に意識したい!受験科目ごとで押さえるべきポイント

高3になってからは、本格的な問題演習や過去問などに取り組み、入試本番に向けた実戦力を養う必要があります。そのためには、高2の段階で各科目の基礎を押さえておき、高3でスムーズに問題演習へ切り替えられるよう準備することが必要です。
科目の基礎が身についていないと応用問題も解けないため、高3になってから問題演習が進まず、入試までに必要な学習量をこなせません。とくに、科目数が多い国公立や理系大学を志望する場合は、勉強量も多いので「前倒しで基礎を固める」という気持ちが必要です。
各科目で高2の間に押さえるべき内容は以下の通りです。
| 科目 | 押さえるべきポイント |
|---|---|
| 英語 | 「単語・文法・英文解釈」の基礎事項を高2までに終わらせる |
| 数学 | 高3で問題演習へ取り組めるよう教科書の基礎事項は高2で完璧にしておく |
| 国語 | 早めに古文の文法と漢文の句法を勉強する |
| 理科・社会 | 覚えた単語や知識がそのまま出題されるため、授業も活用して早めに勉強を進める |
英語
英語は、必ず「単語・文法・英文解釈」の基礎事項を高2までに終わらせましょう。英語の試験では長文読解問題を中心に出題する大学がほとんどです。
とくに共通テストについては、長文読解問題のみが出題されます。そのため、読解の基礎である「単語・文法・英文解釈」が身についていなければ問題を解けません。
受験生になってから本格的な読解演習に取り組めるよう、高2の段階で英語の基礎は終わらせましょう。
英単語は、最低でも単語帳3周には取り組みます。最初の3周は、メインの単語の意味だけ覚えればOKです。
文法は「知識をインプット→英文法の問題集を解く」という流れで知識を活用し、入試本番でも使えるよう準備しておきます。英文解釈については、品詞の見極めができるようにしておきましょう。
数学
数学の試験では、授業で習った教科書の内容が基礎となります。授業で習う公式や定理などを使ってさまざまな問題に取り組むため、授業内容をどれだけ押さえているかが受験結果に直結します。
そのため、受験生になってから問題演習へ取り組めるよう、教科書の基礎事項は完璧にしておきましょう。毎回の定期テストで満点を狙うつもりでしっかり演習を続けていき、普段の学習では青チャートのような網羅系問題集も着実に進めたいですね。
理系で数学3が必要な大学・学部を目指す場合は、スタディサプリのような映像授業も活用し、少しずつ予習を進めたい所です。
遅くとも高3の始め頃までには、教科書の内容を完璧に把握しておきましょう。
国語
国語で早めに押さえるべきは、古文の文法と漢文の句法です。高3になってからは、入試での配点が大きく難易度も高い英語や数学の演習に時間を取られるため、余裕のある高2の段階で国語の暗記事項を押さえておきましょう。
高2の間に単語帳や文法問題集に1冊ずつ取り組むことが理想です。基本的には「文法・句法の理解→演習」の順番で取り組みます。
現代文については、易しめの参考書を1冊解いて読み方を身につけておけばOKです。文系であれば、共通テストの過去問を解くのもよいでしょう。
理科・社会
理科と社会は、授業の内容が受験に直結します。覚えた単語や知識がそのまま出題されることも多いため、学校の授業も活用して早めに勉強を進めましょう。
ただし、理科と社会は範囲が広いため、授業ですべてを扱うのが受験直前になることも珍しくありません。そのため、完全に授業ペースに合わせることはせず、高2〜高3夏前に受験範囲が終わるよう、予習して進めておきましょう。
理科と社会の勉強ペースは、志望校によって以下のように変わります。
- 東大・京大・上位医学部志望→高2の段階で終わらせる
- 旧帝大以上・早慶→高3のGWまでに終わらせる
- 上記以外(マーチや日東駒専など)→高3の夏休み前までに終わらせる
理科については「教科書理解→問題演習(定石理解)→入試問題演習」という流れで勉強しましょう。本格的な演習は受験生になってからでOKです。毎回の定期テスト勉強ごとに復習して、授業内容を完璧にしておきましょう。
社会については、最初に通史を覚えてから基本の単語を押さえていきます。理科と同じく授業内容が受験に直結するので、毎回の定期テストごとに復習して完璧にしましょう。

高2の受験勉強スケジュール

ここまで解説した必要な勉強時間を満たし、各科目で押さえるべき内容をしっかり身につけるためにも、大まかに以下のようなスケジュールで勉強を進めましょう。
1学期
受験で必要な勉強習慣を身につけるために、授業の復習サイクルを早い段階で身に付けておきましょう。授業内容や理解できなかった部分を、毎回の授業後にスタディサプリで復習するという方法が効果的です。
高1の内容でつまづいている部分があれば、土日を活用して振り返っておきましょう。1学期の段階でわからない部分を解消しておけば、夏休みに行う基礎の振り返りにおいて、自分の苦手部分を重点的に潰す時間も確保できます。
夏休み
高2の夏休みは基礎を一気に振り返るチャンスです。受験生になると、基礎が身に付いている前提で問題演習にたくさん取り組まないといけません。
とくに「英語は単語と文法」「数学は公式や定理」という基礎を固めておかないと、演習をしても問題が解けません。
2学期以降から問題演習を進められるよう、夏休み中に1学期までの内容を総復習しておきましょう。最低でも1日4〜5時間くらい勉強することが理想です。
もちろん、取り組めるならもっと勉強時間を確保しても大丈夫です。
2学期
高3の2学期以降は、過去問演習に取り組み志望校に合わせた実践的な勉強を積み重ねる必要があります。それを考えると、参考書を使って勉強できるのはあと1年ほどしかありません。
高2の2学期の段階で本格的に受験勉強をスタートさせて基礎を固めておかないと、過去問演習に取り組むべき高3の2学期以降の時期に「知識が身に付いていない」という状態になり、本番に間に合わない可能性が高いです。
高2の3学期を「高3の0学期」ということも多いですが、実は「高2の2学期」が一番大事なのです。
冬休み
冬休みには先の範囲の予習もスタートさせたいため、高2までに習った基礎を総復習するには、冬休みが最後のチャンスです。
また、高2の春休みはガッツリ受験勉強の時間を確保したいため、冬休みの間で長時間勉強に慣れておきましょう。
具体的には、冬休みの間に「丸1日勉強する日を作る」ということがオススメです。1日7時間平均で勉強に取り組み、可能であれば10時間勉強も体験しておくと、春休みは受験生としてスムーズに受験勉強を始められます。
3学期
冬休みと同じく「高3の0学期」として勉強を進めます。受験生になる前に、数学3C・理科・社会など受験で使う科目の高3範囲の予習を進めておきましょう。具体的には、「教科書を読む」「スタディサプリで高3の範囲を進める」などがオススメです。
先ほども勉強時間について触れましたが、そろそろ学年も変わるので、受験生になったつもりで「休日は8時間勉強する」というように慣れておきましょう。
3学期には志望校の過去問も確認しておきます。現段階ではまだ点数を気にする必要はなく、まずは志望校の問題の傾向を掴んでおくことが重要です。
共通テストの同日模試も受けましょう。本番の共通テストと同じ雰囲気を味わいながら自分の実力を試せます。
高2から塾に通って受験に備えるのもアリ

このように、高2から受験勉強を始めるうえで意識すべきことはたくさんあります。勉強計画の作成が必要ですし、各科目で最低限終わらせておくべき範囲なども考えなければなりません。
何よりも重要なのは、受験生になってから問題演習の時間を確保するために「基礎を高2までに終わらせておく」という点です。各科目の基礎範囲は膨大であるため、しっかりと勉強習慣を身につけて、毎日着実に積み上げなければなりません。
とくに「難関大志望だが英語と数学に不安がある」という人は、なおさら高2から受験勉強を始めましょう。英語と数学は覚える範囲が広いため、部活が終わってから難関大に向けた勉強を始めても間に合わない可能性が高いです。
もしも「自分一人では勉強する自信がない」ということであれば、塾通いも検討しましょう。塾に通えば強制的に勉強できる環境に身を置けるので、習慣を身に付けて受験生になる前に効率よく基礎を固められます。
勉強習慣は、受験生になってからいきなり「今日から10時間勉強しよう」と身に付けられるものではありません。独学で勉強を続ける自信がないのであれば、高2のうちから塾を活用し勉強に慣れておくことが大切です。
まとめ
高2から受験勉強を始めるのであれば、最初に志望校を決めて勉強計画を作成してから勉強を始めることが重要です。入試本番までの長い期間の勉強計画をしっかり定めておくことで、やるべきことに迷わず正しい方向性で受験勉強に臨めるようになります。
きちんと計画があれば、各科目で必要な内容を身につけられる「受験までに間に合わない!」という事態も減らせるでしょう。
とはいえ、長期の勉強計画を作成した経験を持つ人は少ないため、なかなか正しい方向性で作成するのは難しいかもしれません。
作成したとしても、実際に受験勉強を進める中で感じた「この方向で合っているかな?」「科目でどうしてもわからない部分がある」などの疑問点は、自分だけでは解消するのも大変です。
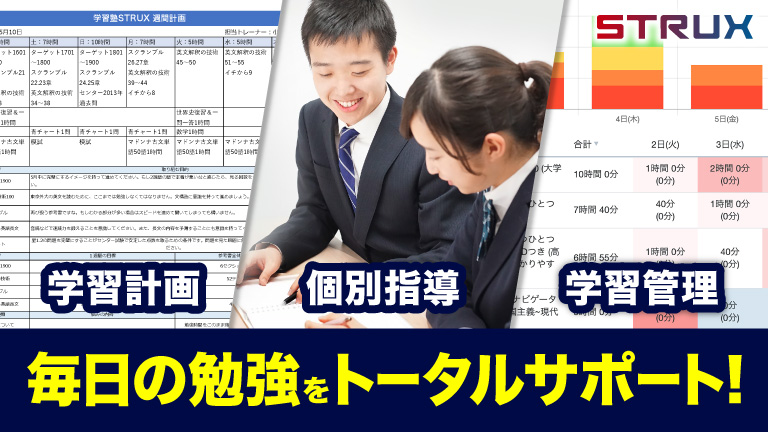
学習塾STURXでは、専任講師が生徒の志望校に応じた勉強計画を作成し、受験本番までの長い道のりを徹底的にサポートします。高2という早い時期から受験勉強を始めたからこそ感じる疑問にもしっかり答えてくれるため安心です。具体的には、定期的な面談や質問受付アプリを活用して、普段の勉強をサポートしています。
「具体的にどのくらいサポートしてくれるの?」と感じた方は、ぜひ無料体験にお越しください。無料体験では実際の指導で使用している勉強計画を作成してお渡ししているので、参加するだけでも今後の受験勉強に役立つこと間違いなしです。
早くから受験勉強を始めて不安が多いからこそ、普段の学習もみっちりサポートしてくれる学習塾STRUXを検討してみてはいかがでしょうか。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。












