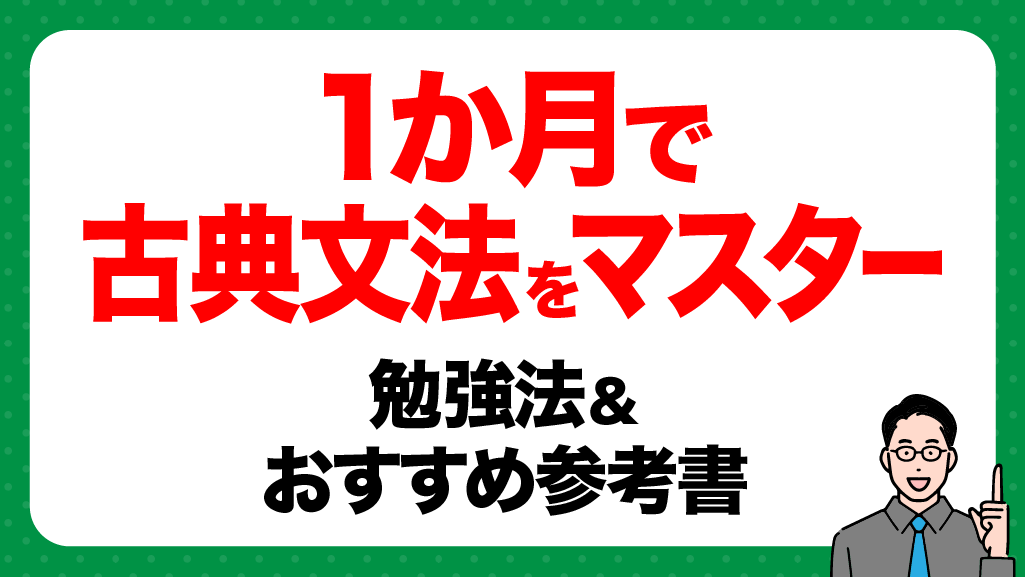
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
古典文法は古文単語と並んで、古文の勉強の核となる部分です。この記事では、「たった1ヶ月」で古文文法を覚えられる勉強法を解説します。

古典文法で覚えるべきポイントはたったの3つ!

そもそも「古典文法の勉強」をする上で絶対にやるべきことを知っていますか?
同じ日本語とはいえ、古文は「外国語」のつもりで勉強すべき科目です。英語と同じように、単語や文法を覚えたうえで、正確に文章を読む練習が必要になります。
古典文法をいざ覚えるとなると、助動詞や敬語など難しそうな内容が多いですが、実は古文の文法事項において押さえるべきポイントは英語と比べてもとても少なく、シンプルに覚えることができるようになっています!
早速、古文文法を勉強するときに押さえるべき3つのポイントを紹介しましょう!
古典文法で覚えるべきことはこの3つ!
- 活用
- 意味
- 接続・識別
以下でひとつひとつ説明していきます。
古典文法で覚えるべきポイント①:活用
古典文法「活用」とは、古文の動詞や形容詞、形容動詞、助動詞で、後ろに来る言葉によって語尾の形が変わることを指します。
たとえば、「書く」という動詞は、後ろに続く言葉によって次のように形が変わります。
書か ず / 書き て / 書く 人 / 書け ば / 書け
このように、まったく同じ単語でも後ろに来る言葉で語尾の形が変わるため、活用を覚えていないと文章が全く読めません。
活用は次の6種類に分かれるので、動詞や形容詞・形容動詞、助動詞など活用する単語はすべて、「未然形はどういう形」「連用形はどういう形」というものを覚えていないといけません。
- 未然形
- 連用形
- 終止形
- 連体形
- 已然形
- 命令形
そして、この活用形がなにかを知っていないと、後ろに来る言葉の意味がわからないということもあります。
次の2つの文章を見てみてください。
- 花、咲きぬ。
- 花、咲かぬこと、
この2つの文では同じ「ぬ」という単語が使われていますが、意味は大きく違います。
違いに気づくには、
- 1つめが「咲き」という「連用形」の活用になっていること
- 2つ目が「咲か」という「未然形」の活用になっていること
- 連用形+「ぬ」と未然形+「ぬ」では意味が異なること
の3つを知っていないといけません。
詳しくは3つ目のポイント「接続・識別」のところでお伝えしますが、活用形を完璧に覚えていないと意味の識別が正確にできないので、古文を読み解くために、活用は一番最初に覚えましょう。
古典文法で覚えるべきポイント②:意味
活用を覚えたら、次に覚えるのは「意味」です。
文法事項として、助詞や助動詞などの意味を覚えていなければいけません。
たとえば、先ほどの例で使った「書かず」の「ず」は”打消”の意味を持っています。現代語に訳すと「〜ない」です。
助動詞や助詞には「1つにつき2つ以上の意味を持つ」というものが多く、すべての意味を覚えないと試験で対応できないのです。
日本語は「〜しよう」「〜したい」「〜しない」のように語尾で意味が決まるので、助動詞や助詞など語尾に来る部分の意味を正確に覚えていないと、いくら単語の意味がわかっても正確に読めません。
助動詞の意味はすべて覚える必要がありますし、助詞も重要なものだけでも表などで覚えておく必要があります。
古典文法で覚えるべきポイント③:接続・識別
活用と助詞・助動詞の意味がわかったら、最後に「助動詞の接続」を覚えて、助動詞の見極め、いわゆる「識別」ができるようにしていきます。
助動詞の種類によって、その上に来る動詞や形容詞の活用形は決まっていて、これを「接続」とまとめて呼びます。
たとえば、打消の助動詞「ず」の上にくる動詞は、「起きず」「動かず」など必ず未然形になります。
この場合、助動詞「ず」は「未然形接続の助動詞」と呼ばれます。
これまで勉強してきた「活用」は、この助動詞の「接続」を見極めるために重要になるわけですね。
そして識別とは、文章中に書かれている単語の品詞・意味が何かを判別することです。
古典では、一見同じ文字を使っていても意味が違うことがあります。そのため、どの文法事項が使われているかを区別できないと、文章の意味を捉え違えてしまいます。
きちんと識別できるようになるには、助動詞の「接続」がきちんと覚えられていなければいけません。
識別のポイントは、学校で配られる文法書や、『古典文法基礎ドリル ステップアップノート』などの参考書で詳しくまとめられています。
例えば、
“「る・れ」の識別では「る・れ」のすぐ上の一字の音を見て判断する”
といったもので、この判断ポイントをしっかり覚えることが大切です。
識別をする際は、助動詞だけでなく動詞や助詞など複数の品詞から選ぶため、はじめはわかりづらいなと思う部分もあるかもしれません。しかし、「どこが識別するポイントなのか?」を理解できれば必ず識別できるようになるので、根気強く覚えたうえで、問題を解いて慣れていきましょう。
識別の際に迷いがちな助詞と助動詞について詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしましょう。

古典文法の覚え方と勉強法のポイント

古典文法で何を勉強すればいいかわかったところで、具体的な勉強法を解説していきます。
古典文法は次の順番で勉強していきましょう。
- Step1 用言(動詞・形容詞・形容動詞)の活用を覚える
- Step2 助動詞の「活用・意味・接続」を覚える
- Step3 助詞やその他の文法事項を覚える
- Step4 識別の練習をする
それぞれ詳しく説明していきます。
古文文法の勉強ステップ1:用言(動詞・形容詞・形容動詞)の活用を覚える
まずは簡単なところ、かつ基本的なところから覚えていきましょう。
活用する自立語(単体で意味をなす単語)のことを「用言」といいますが、まずは用言である動詞・形容詞・形容動詞の活用から覚えていきます。
活用で覚えるべきなのは
- 活用の種類(四段活用など)
- 活用形
の2つだけです。
活用の種類は次の通りで、それぞれの用言がどの活用なのか、そしてそれぞれの活用がどういう変化をするのか覚えていれば大丈夫です。
- 動詞の活用
- 四段活用
- 上一段活用
- 下一段活用
- 上二段活用
- 下二段活用
- 変格活用(カ行・サ行・ナ行・ラ行)
- 形容詞の活用
- ク活用
- シク活用
- 形容動詞の活用
- ナリ活用
- タリ活用
活用形を覚える場合は、声に出して何度も音読することが大事です。
ここでは動詞の四段活用を例に、実際にどうやって音読すればいいか説明しましょう。
動詞の四段活用の活用パターンは、
未然形・連用形・終止形・連体形・已然形・命令形の順に、必ず「ア・イ・ウ・ウ・エ・エ」
となります。
たとえば「書く」という四段活用の動詞は、「書か・書き・書く・書く・書け・書け」です。
この活用パターンを、おもわず口ずさんでしまうくらい何度も何度も音読してください。
この例で言うと「ア・イ・ウ・ウ・エ・エ」と、毎日何度も繰り返しましょう。
「1ヶ月間・毎日5回」続けるだけでも、テキストを見なくても活用がすらすら言えるようになります。
古文文法の勉強ステップ2:助動詞の「活用・意味・接続」を覚える
用言の活用を覚えることができたら、次は助動詞の勉強に入ります。
古典文法で一番重要で、覚えることも多い「助動詞」ですが、覚えることは次のたった3つです。
- 活用
- 意味
- 接続
ポイントは、この3つを用言と同様に何度も声に出して唱えながら覚えていくことです。参考書などについている助動詞の表には、必ず上から「接続」「活用」「意味」の順に載っているので、表を使ってこの3つを覚えていきましょう。
いきなりすべてを覚えるのは大変なので、接続→活用・意味の順に整理して覚えるのがおすすめです。
まずは助動詞の接続を覚えます。未然形接続はどの助動詞で、連用形接続はどの助動詞で、と覚えていくのがポイントです。
- 未然形接続:る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし
- 連用形接続:つ・ぬ・たり・けり・たし・き・けむ
- 終止形接続:らむ・べし・まじ・らし・なり・めり
- 連体形・体言接続:なり・たり・ごとし
- 特殊系(「サ未四已」):り
古文の助動詞接続は、表を見るとこれらに分類されているはずです。
これをたとえば「未然形接続は『る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし』、『る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし』……」と何度も唱えて覚えていけばOKです。
唱えるだけで覚えにくい場合は、替え歌の語呂合わせで覚えるという手もあります。歌だとより口ずさみやすく、かつフレーズごとに助動詞の接続が分けられているので、無意識のうちに覚えられます。
「接続」を覚えたら、次に「活用」と「意味」を覚えます。
このときもいきなり全ての助動詞を覚えようとするのではなく、「まず今週は未然形接続の助動詞の活用を覚えよう」と、接続ごとに分けて覚えるのがおすすめです。
未然形接続の活用をすべて覚えたら意味を覚えて、それを覚えたら連用形接続に進んで、というふうに取り組むと、1ヶ月〜2ヶ月で助動詞をすべて覚えられるはずです。
複数の意味がある助動詞については、意味の覚え方のコツが文法書などに載っていることがあるので、不安であれば参照しておくといいですね。
古文文法の勉強ステップ3:助詞やその他の文法事項を覚える
助動詞をすべて覚えることができたら、助詞やその他の文法事項も覚えていきます。
助詞も助動詞のように表にまとめられていますが、すべてを覚える必要はありません。現代語と同じ使われ方の助詞も多いため、現代語と違う意味のものの意味だけを覚えられれば問題ありません。どうしても必要なものは演習しながらでも覚えられるので、助詞の暗記には時間をかけすぎないようにしましょう。
助詞以外にも「係り結びの法則」など細かい文法事項があります。参考書によっては敬語も文法事項として扱っていることがあるので、これもこの際に覚えておきましょう。
古文文法の勉強ステップ4:識別の練習をする
ここまでで、古文の品詞ごとの重要なものについては一通り覚えました。ここからは問題集を使って識別の練習に取り組みます。
ここまでの勉強は表さえあれば覚えられましたが、識別は実際の文章を見ながら実践していくことではじめて身につきます。
古文の「文法問題集」と言われる参考書、例えば先程紹介した『ステップアップノート』やこの後紹介する『日栄社30日完成古文』などでは、最後のほうに必ず識別についてのページが複数あります。使いやすい参考書で構わないので、問題を解いて識別の練習をしていきましょう。
このとき、忘れていた活用形やルールは参考書や文法書を見返してその都度覚え直す、ということを忘れないでください。

古典文法を覚えるためのおすすめ参考書

ここからは、実際に古典文法を勉強していくうえで取り組みたい参考書を紹介していきます。学習塾STRUXでも実際に計画に盛り込んでいる参考書なので、ぜひ参考にしてください。
ここでは、
- 古典文法の基本をゼロから勉強するための参考書
- 古文の識別を中心に、知識を定着させる問題集
の2つを紹介します。
「表だけで知識を覚えてもいまひとつ不安…」「この記事で読んだ内容を完全に理解できていない…」という場合は1冊目から、「助動詞の活用はある程度覚えているから、抜け漏れがないか、識別があっているかを確かめたい」という場合は2冊めから取り組むのをおすすめします。。
古典文法おすすめ参考書①:『八澤のたった6時間で古典文法』
『八澤のたった6時間で古典文法』では、古典文法の最初の学習で必要な活用のルールなどだけでなく、文法の覚え方まで過不足なくまとめられています。
たった6時間の映像授業と、テストでの繰り返しの演習を活用することですぐに古典文法を覚えられるため、独学でも読み進めやすい参考書になっています。古文が苦手な人はまずこれから始めることをおすすめします。
その他のおすすめ参考書としては、『富井の古典文法をはじめからていねいに』や『スタディサプリ』などの映像授業があります。
古典文法おすすめ参考書②:『ステップアップノート古典文法基礎ドリル』
文法事項の説明に加えて、ちょうどいいレベル・量の問題が掲載されている『ステップアップノート』は、30日で完成できるようになっている手軽さも魅力です。1冊で活用だけでなく識別、敬語などまで覚えることができます。
現代語訳の問題など、1周取り組むだけでは難しい問題もあるので、必ず3周取り組んで完璧にしましょう。
その他のおすすめ参考書としては、日栄社『発展30日完成 古典文法サブノート』『発展30日完成古文 高校中級編』などがあります。
古典文法問題集の使い方
今回紹介した参考書は暗記用として取り組むため、1回読むだけ・解くだけでは不十分です。正しい使い方で取り組んでこそ身につくので、必ず守りましょう。
- Step1 文法の重要ポイントを確認
- Step2 実際の問題を解く
- Step3 解説を読み、わからないところ、覚えられてないところを復習
- Step4 間違えた問題、不安な問題をもう一度解く
このステップを1回あたり30分から1時間程度で毎日取り組めば、仮に『ステップアップノート』を使う場合は2ヶ月程度で3周することができます。
それぞれのステップについて簡単に見ていきましょう。
Step1. 文法の重要ポイントを確認
まずは文法の理解から。勉強しはじめてすぐの人や古文が苦手な人は、必ず問題を解く前に「重要ポイント」などまとめのページを見て、頭の中で整理してから問題を解きましょう。この部分を問題集ではなく『八澤のたった6時間で古典文法』などで補うのもおすすめです。
Step2. 実際に問題を解く
理解ができたら実際に問題を解いていきます。
ここでのポイントは、「なぜその答えになったのかを考えながら解く」ということです。受験で出題される問題には必ず正解になる根拠があります。「前の動詞が連用形だから、この助動詞はこちらの意味」といった根拠がわかっていないと、次に問題を解いたときに間違えてしまう可能性が高いです。
Step3. 解説を読み、わからないところ、覚えられてないところを復習
問題を解いたら解説を読みます。このとき、間違えた問題はもちろん、もし正解していても根拠がわかっていなかった問題は×をつけておきましょう。
Step4. 間違えた問題、不安な問題をもう一度解く
間違えた問題をもう一度解きましょう。「正解していたがたまたま合っていた」という問題も、この時必ず解き直してください。
まとめ
今回はSTRUXでも実際に教えている古典文法の覚え方と、参考書を使った勉強法をすべて解説しました。
ポイントは次のとおりです。
- 毎日唱えて覚えることが重要
- 助動詞は「活用」「意味」「接続」を覚える
- 問題集を繰り返し解いて「識別」の練習をする
一見すると覚えることが多いですが、英語や社会に比べれば圧倒的に覚えることは少なく、長期休みでまとめて覚えてしまうことも可能です。高2の間にすべて覚えてしまって、高3からは読解の演習に入れるようになるのが理想です。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。
















