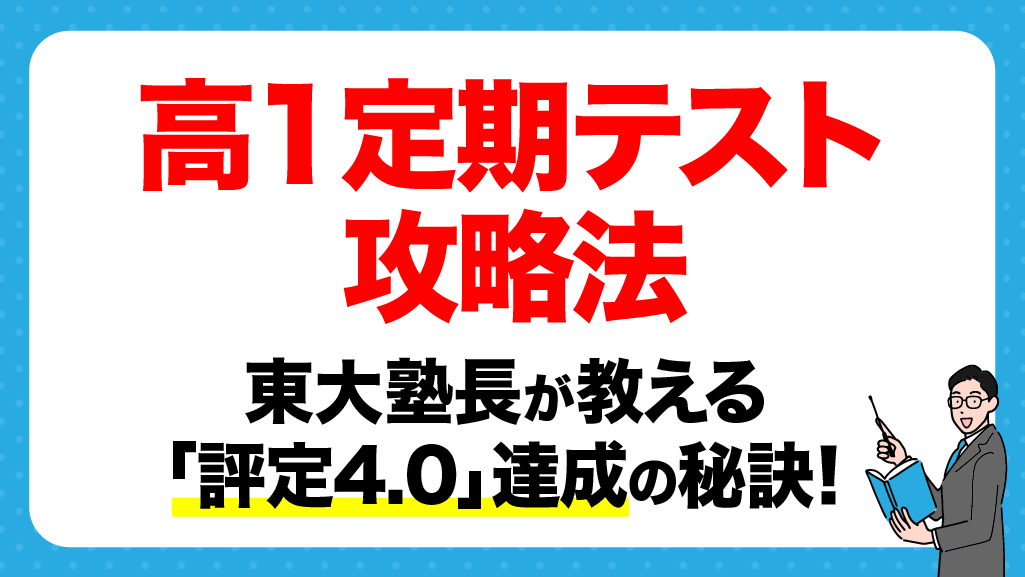
*紹介している教材にはプロモーションを含みます
まだ高1だし、定期テストも中学と同じでしょ?
そんな風に思っているあなた、3年後に必ず後悔します。
高校1年生の定期テストは、あなたの大学受験の合否を決める第一歩です。中学では中3の成績だけが重要でしたが、高校では1年生の最初のテストから評定平均に直結します。国公立大学の推薦入試では評定平均4.0以上が必要で、高1で失敗すると挽回はほぼ不可能です。
しかも、高校の定期テストは科目数・範囲・難易度すべてが中学の2倍以上。一夜漬けで乗り切れる時代は終わりました。
でも、正しい対策さえ知っていれば大丈夫。
この記事では、東大出身塾長が教える3週間前からの逆算スケジュール、科目別攻略法、そして成績を劇的に上げる秘訣を完全公開します。ライバルがまだ気づいていない今こそ、圧倒的な差をつけるチャンスです。

なぜ高1の定期テストは「最重要」なのか?中学との決定的な違いと大学受験への影響

高校1年生の定期テストは、高校生活の土台をつくる大切な機会です。中学のテストとは範囲も出題形式も大きく変わるため、早い段階で勉強習慣を整えましょう。高1の成績は評定平均に直結し、推薦や総合型選抜の合否を左右します。ここからは、高校のテストの特徴や注意点を具体的に解説します。
中学より定期テストの科目数・範囲・難易度が増すから
高校1年生の定期テストは、中学の頃のテストと比べて科目数や範囲、難易度が大きく変わります。
まず、扱う教科が増え、理科や社会も細かく分かれるため、計画を立てないと勉強が追いつきません。
さらに、テスト範囲が広くなるため、一夜漬けのような短期間の対策では高得点が難しいです。1科目あたりに必要な勉強時間は、最低でも高1の頃の2倍は見ておくのが無難でしょう。
数学Iでは2次関数やデータの分析など、大学受験でも出題される単元を早くから学びます。中途半端なテスト対策をしていると後で苦労するのは目に見えています。
英語も中学と異なり、英文法や英作文の比重が高くなりますし、1回のテストまでに習う単語の個数もかなり増えます。十分な時間を確保しないと、テストで点を取れないどころか、英語の基礎となる英文法を習得しないまま学年が上がっていってしまいます。
よって、高1の定期テストは「赤点回避」だけを目的にすると、のちの学年で苦労しやすいのです。毎回のテストを大学受験の基礎力を高める場と考え、定期テスト計画を早めに作りましょう。
学習塾で定期テストスケジュールを一緒に組んだり、定期テスト効率を上げる勉強法を身につけたりすることも効果的です。
推薦・総合型選抜を目指すのであれば高1から評定平均を意識する必要があるから

大学受験では、高校1年生の最初のテストから、評定平均が算出の対象になります。評定平均は3年間の全科目の成績をもとに計算され、推薦入試や総合型選抜で合否を大きく左右します。例えば、国公立大学の推薦では4.0以上の評定平均が求められることが多く、初回の定期テストで低い点を取ると、その後挽回するのが難しくなります。
高校受験の推薦では、(都道府県によっても異なりますが、)中3の成績だけ提出が必要だったり、中1中2の成績が必要でも、中3の方に重みを置いていたりすることが多いので、それとは全くシステムが異なります。
特に英語や数学の基礎を高1で固めておかないと、高2以降で挽回するのはかなり難しいので注意しましょう。
保護者の方も、推薦などの多様な入試形式を意識するのであれば、高1の頃から定期テストで得点を積み重ねておかないといけないことは頭に入れて、それをお子さんにも必ず伝えるようにしてください。
定期テストで身に付けた基礎力が一般選抜の勉強にも繋がるから
定期テストの目的は赤点を回避することだけではありません。高校1年生の定期テストを通して学ぶ内容は、共通テストや私立大学の入試でそのまま出題されます。例えば、英語の仮定法や数学Iの因数分解などは、定期テストで身につけた理解がその後の模試や入試問題の得点に直結します。
さらに、定期テストは復習と弱点分析の大きなチャンスです。テストが返却されたら、間違えた問題の類題を解き直し、次に向けてどの単元を強化するか明確にしましょう。定期テスト計画を作るときは、毎日の学習習慣も意識して、計画のルーティン化が重要です。
親ができることとして、テスト前に集中できる環境づくりや、当日までの勉強計画を一緒に確認するサポートも有効です。赤点回避の先を見据えた学習が、高校3年間を支える土台になります。

【実践ロードマップ】定期テストで高得点を取るための準備と対策スケジュール
それでは、定期テストで高得点を取るための準備と対策スケジュールを具体的に見ていきましょう。
ここでは、計画例を提示するので、自身の定期テストの範囲に合わせてカスタマイズすれば、そのまま計画を使うことができます。
目標設定から計画立案まで!テスト対策を始める前の「見える化」ステップ
まずは定期テストまでにやることを整理しましょう。
やるべきことは次の通りです。
- 各科目の目標点数を設定する
- 各科目のやるべきことを全て洗い出す
- やるべきことを終えるまでのスケジュールを作る
まずは目標点数を設定します。たとえば
- 前回のテストで点が悪かった科目は最低でも平均点
- 他の科目は一旦満点を狙う
のような感じです。このときに注意したいのが、平均点で満足しないこと。
高1のときに平均点しか取っていない科目の知識は、多くの場合、高3になるころには頭から抜けていって、1から勉強し直すことになります。可能であれば、全科目満点を狙って勉強するようにしましょう。
次に各科目のやるべきことを全て洗い出します。たとえば、
- 授業ノートを見返しながら教科書を全て読み返す
- プリントを全て読み返す
- 問題集を3周する
- 文章を3回ずつ音読する
- 覚えていなかった単語や用語を全て覚える
のような感じですね。これを各科目ごとに洗い出してください。この段階では思いつく全ての内容をまとめるのが重要です。
そして最後に計画の作成です。思いついたことを全てこなすためには、いつから何をしていけばいいのか考えるようにしましょう。多くの場合は、3週間前くらいから始めないと間に合わないことが多いので、以下では3週間前から少しずつ始める形で解説を進めます。
テスト3週間前からの逆算スケジュール:暗記・苦手克服・応用演習の段階別戦略
それでは、スケジューリングについて解説していきましょう。
3週間前:基礎固めと苦手分野の洗い出し
3週間前から始めるのは苦手科目や、重い科目です。
苦手科目は学校の授業についていけていない可能性も高いので、
- 教科書を読み返す
- 『スタディサプリ』などの映像授業を見る
などをして、授業で解説されている内容をまずは理解するようにしましょう。
英語や数学は、かなり勉強しないと満足する得点が取れないことが多いので、3週間前から少しずつ始めましょう。
英語なら、改めて最初から文法要素を理解しているか全てチェックしたり、文章を頭から読み返したりしてみてください。数学なら早めに問題集に少しずつ取り掛からないと他の科目よりも問題集の進みが遅くなってしまうので、注意しましょう。
理解していない部分はまず理解することが重要です。
2週間前:問題演習と不明点の解消
2週間前には、問題演習をガッツリ始めてください。問題集のある科目は問題集の1周目を必ずテストの1週間前までに終わらせましょう。
問題集を持っていない科目は問題集を買っておいた方が無難です。定期テスト用の簡単なものでも構わないので、Amazonや大型書店に行って探してみてください。
この期間に「答えを読んでも分からない箇所」が見つかったら、友だちや先生に確認するようにしましょう。1週間前になると、友だちも先生も忙しいので、なかなか質問するのも難しくなるので、早めに確認するのが大事です。
1週間前~直前:弱点補強と最終確認
1週間前から直前は、問題集の2周目3周目をこなしつつ、暗記し切れていない内容を全て暗記していきます。
ここまでに解説したことが全てクリアできれば、十分、満点を狙うことも可能なはずです。

【科目別攻略法】高1定期テストで差をつける「+α」の勉強テクニック

科目別に効果的な定期テスト勉強法を実践することで、短期間で大きな差をつけられます。ここからは英語・数学・国語・理科・社会・実技科目の勉強法を具体的に解説します。
英語:単語・文法は「音読」で定着!長文読解とリスニングの効率的学習法
英語は「基礎知識を繰り返し暗記し、演習で確認すること」が大切です。定期テストでは「論理・表現」「英語コミュニケーション」の2つが出題されるため、範囲ごとに対策を進めましょう。
まず論理・表現では文法や英作文が中心です。単語は「スペル・発音・品詞・意味」を正確に覚え、2週間前から毎日少しずつ取り組むと効率的です。暗記は一夜漬けでは身につかないため、スキマ時間勉強法を活用し、繰り返し確認しましょう。
問題演習は最低2周行い、1周目で基礎の理解、2周目で自力で解けるか確認してください。例文暗記も有効です。時間に余裕があれば、英作文の頻出例文を丸暗記し、和文英訳に慣れましょう。
英語コミュニケーションでは教科書の長文理解が鍵です。2週間前から英文を精読し、内容を和訳できるか確認してください。単語や文法は暗記リストを作り、毎日覚える習慣をつけましょう。1週間前からは音読を繰り返し、文章を暗唱できる状態にすると記憶が定着します。
リスニング対策は音読と併用が効果的です。教科書の音声を毎日聞き、ネイティブの発音をマネしながら声に出しましょう。
数学:公式の「なぜ?」を解明!問題演習の効果を最大化する思考プロセス

数学は「公式の意味を理解する」ことが重要です。ただ問題を解くのではなく「なぜこの公式を使うのか」「どうしてこの解き方になるのか」を説明できるようにしましょう。
特に数学は積み重ねが必要な科目です。公式を丸暗記しているだけでは、定期テストや共通テストなどの入試で得点が安定しません。定期テストスケジュールを立てる際は、問題集を最低2周し、間違えた問題は「その場で解き直す」習慣をつけると効率的です。
具体的には、テスト3週間前から問題集を始めてできるだけ早い段階で1周し、解法を覚えるのではなく「どこでつまずいたのか」「計算ミスをなぜしたか」を書き出しましょう。1週間前からは、間違えた問題だけを2周目として解き直し、解き方を自分の言葉で説明できる状態を目指します。
国語(現代文・古文・漢文):読解のツボと暗記のポイント、古典文法・句法の効率的攻略
高校1年生の定期テストで国語は点数を安定させやすい教科ですが、定期テスト対策では「計画性」と「暗記の深さ」が重要です。現代文では授業ノートの見直しが得点アップに直結します。特に、先生が口頭で補足した内容は出題されやすいので、ノートに記入漏れがないか友達と確認してください。
現代文は2週間前からテスト範囲を把握し、ノートを繰り返し復習しましょう。出題傾向として「心情説明」「文章の要約」「指示語の解釈」が頻出です。授業内容を理解した上で、解答の型を覚えると効率が上がります。
古文は単語と助動詞・助詞・敬語の暗記が軸になります。3週間前に範囲を確認し、2週間前から単語・助動詞・助詞・敬語の活用を暗記しましょう。助動詞は意味だけでなく、活用形や敬語の対象も確認が必要です。本文の内容理解は1週間前から進めると記憶が定着します。特に古文は主語が省略されやすいため、「誰が何をしているか」を一文ごとに把握してください。
漢文は句法と返り点を理解するのが先決です。句法は文法に近い役割があり、意味の解釈に直結します。例えば、「使役」「否定」「受身」など句法ごとのルールを整理しましょう。2週間前には句法を集中して覚え、1週間前から本文の内容を音読や書き下しで定着させます。授業で扱った文章を暗唱レベルまで復習するのがおすすめです。
理科(物理・化学・生物・地学):実験・観察から導く理解と、計算問題・暗記問題の対策

理科はインプットとアウトプットを繰り返すことが重要です。高1の定期テスト対策では「教科書理解→演習」の順で進めると効率的です。特に理科は中学の定期テストの違いがはっきり表れ、授業の板書や資料集をどれだけ読み込み、定期テストスケジュールを立てて計画的に進められるかが得点に繋がります。
まず、出題範囲を確認し、教科書とノートで基礎知識を徹底的に理解します。暗記項目が多い生物や地学では、語句を丸暗記するのではなく、図や仕組みとセットで覚えると効率が上がります。物理や化学は計算問題が中心のため、公式を単に覚えるのではなく「なぜそうなるか」を理解し、問題集を2~3周繰り返しましょう。
赤点回避を目標にする場合でも、教科書理解とワーク演習を最低1周は行い、わからない部分を放置しないようにしましょう。大学受験で理科を使う場合は、基礎知識を早期に定着させる必要があります。
社会(日本史・世界史・地理・公民):横断的学習で「点」を「線」にする!年号・用語暗記の工夫
社会は暗記要素が強い科目です。ただし、単純に用語を覚えるだけでは大学受験に直結する力はつきません。日本史や世界史では、年号・出来事・人物がバラバラに見えますが、流れを理解することで知識が繋がります。
計画を立てる際、まず教科書と資料集を確認し、全体の流れを把握しましょう。そのうえでワークや一問一答に取り組むと知識が定着します。「1週間前までにワーク1周、当日までに3周」を目安に進め、モチベーションを維持しましょう。覚えた用語は自分の言葉で説明できるように練習してください。例えば、倫理では思想の違いを説明し、公民では制度の仕組みを解説できるようにするのが理想です。
実技科目:侮るなかれ!評定を上げるための重要性と対策法
実技科目を後回しにする人が多いですが、評定平均を上げるためには実技科目の対策を丁寧に進める必要があります。体育や音楽、美術、家庭科は中学と違って「提出物」「授業態度」の比重が大きく、普段の取り組みも評価されます。
定期テストの計画を立てる際は、ワークの進め方だけでなく提出期限を守る意識を持ちましょう。例えば、美術の作品や家庭科のレポートを早めに完成させておくと、提出忘れによる減点を防げます。スキマ時間も活用し、授業で習った内容を毎回少しずつ復習する習慣を作ると定期テストの効率も上がります。
推薦入試や総合型選抜を考える場合、実技科目の評定も重要です。赤点回避だけでなく評定を意識して高得点を目指しましょう。
東大出身STRUX塾長が教える!成績を劇的に上げる定期テスト勉強術

ここでは、学習塾STRUXの塾長が教える成績を劇的に上げる勉強術を簡単に説明していきます。
STRUX式「オーダーメイド学習計画」で無駄なく効率的に成績アップ
まず、学習計画はやはりプロに頼むのが1番です。高1の初めのテスト勉強くらいなら、自力で対策できないでもないですが、高1の2回目のテストからは次のような難しさに悩むことになります。
- 前のテスト範囲の内容が頭に入っていないからどこから勉強すればいいか分からない
- 3週間前から勉強しようと思ったけど、モチベーションが続かなかった
- 勉強したつもりなのに成績が悪かったからどう直せばいいのか分からない
このような悩みはやはり個別に問題点を指摘してもらい、それに合わせたオーダーメイドの学習計画を作ってもらうのがベストです。
独学で対策するのであれば、
- 前回のテスト勉強の反省点を具体的な行動として必ず盛り込む
- 全科目オーバーキルを目指す
- スケジュールは事前に準備して必ずやり切る
という3点を意識してください。
経験上、テストの反省はしても、テスト勉強の反省をしない人が多いのは間違いありません。ですが、テストの反省よりも重要なのは、テスト勉強の反省なのです。
スタートが遅かったのであれば「1週間だけでも早く動き出す」、演習が足りなかったのであれば「必ず問題集を3周する」と具体的な行動で、反省するように。「前回悪かったから今回は頑張る」では何の意味もありません。
保護者の方がサポートするのであれば、前回の反省が具体的な行動に紐づいているかのチェックはかなり有効なので、ぜひ実行してみてください。
次に必ず全科目オーバーキルを目指すこと。「基本問題だけ取れれば平均点は行けるはず」と甘く考えずに「発展問題までちゃんと勉強して満点を狙う!」の方が良いんです。特に高1のうちは、受験勉強以上にテスト勉強で成功することが重要になることが多いので、頑張ってみてください。
最後はスケジュールの実行です。「スケジュールは立てたけど、友だちと遊びに行った」「部活後ダラダラして帰るのが遅くなった」みたいなこともあるある。スケジュールは立てるだけでは意味がありません。必ず実行しましょう。STRUXでは毎週の面談で、どれだけ実行できたのかも必ずチェックしています。自力でやるなら、チェックも自力でやりましょう。
苦手克服に特化!「つまずきポイント」解説と実践演習
また、STRUXの授業では、一般的な学習管理型の塾とは異なり、学習計画だけでなく、科目の指導も行っていて、テスト前には、つまずいたポイントも授業中に解説しています。
学校ではなかなか質問できなかった場合でも、個別指導であれば、「ここが分からない」ということも質問できます。質問内容から講師が深掘りして「じゃあ、ここももしかして分かってないんじゃない?」とより深い理解を得ることもできます。
定期テスト後も成長が止まらない!復習計画と次への活かし方
学習塾STRUXの強みは、定期テスト後もフォローもしっかりしている所です。受験に直結する科目は必ずテスト直しまでするように指導し、分からなかった部分は改めてテストで確認しましょう。

読者の疑問を徹底解消!高1定期テスト対策Q&A
ここでは、高校1年生が定期テスト対策で悩みやすい疑問を解説します。
テスト勉強のモチベーションが上がらないときはどうすればいい?
勉強しようとしても、モチベーションが続かないと感じることはよくあります。特に定期テストが難しいと感じると、やる気が落ちやすいです。対策として短時間でも取り組む習慣を作りましょう。毎日5分だけでも机に向かうと、少しずつ勉強効率が高まります。
勉強を始めるハードルを下げるため、計画を細かく分けるのがおすすめです。例えば、今日は数学ワークの2ページだけ進めると決めると取り組みやすいです。
一夜漬けは本当にダメ?
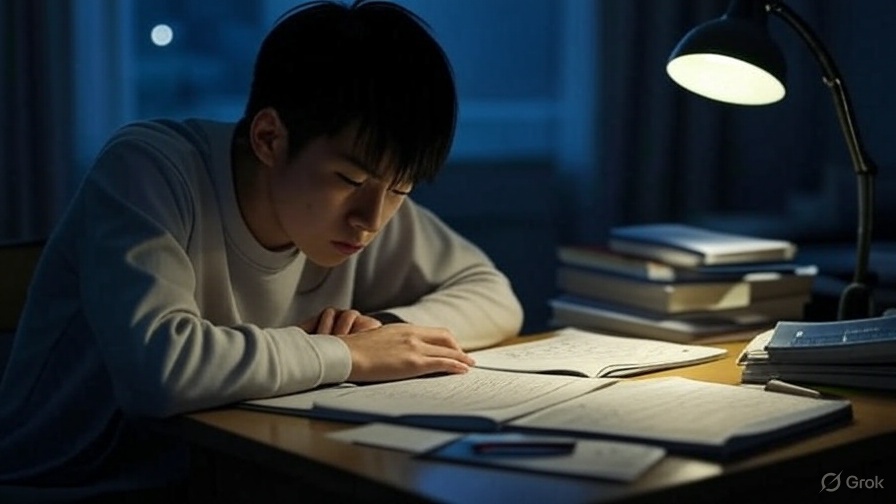
定期テスト対策において、一夜漬けは効果が限定的です。高校生の評定は1回のテスト結果だけでなく、提出物や授業態度も含めた総合評価です。一夜漬けだけで赤点回避を狙うのはリスクが高く、知識の定着も弱いです。そのため、定期テストのスケジュールを立てて、2週間前から計画的に勉強を進めましょう。例えば、毎日30分だけ復習するだけでも知識が定着します。
どうしても一夜漬けになる場合は、暗記系科目に絞って取り組みます理解が必要な数学や理科は、短期間で対策が難しいため注意してください。大学受験に向けて、普段から授業を大切にし、定期テスト対策を行うことがおすすめです。
ただし、「やらないよりは一夜漬けでもやる方がマシ」ではあるので、「一夜漬けはダメらしいから諦める」みたいな言い訳はしないようにしてください。
ワークを何周しても点数が上がらないのはなぜ?
ワークに何周も取り組んだのに点数が上がらない理由は、解き方を理解せずに作業的に進めている可能性があります。定期テストの勉強では「ワークを解いて解説を読む→考え方を説明できるレベルにする」という流れが大切です。
正解した問題も解説を確認し、理由を説明できるかを確認しましょう。例えば、数学なら「なぜこの公式を使ったのか」を意識しながら復習してください。理解が浅い部分は学習塾の定期テスト講座などを参考にしながら補強しましょう。別のワークも準備して、類題を解いてみるのもお勧めです。
また、定期テスト後は間違えた問題を分析し、次回の勉強計画に活かすことが重要です。
【チェックリスト付き】あなたの定期テスト対策、抜かりなし?
最後にテスト対策のチェックリストを準備しました。
テスト勉強が終わった段階で、これを全てクリアできていれば、どんな科目でも満点を取ることが可能です。ぜひ活用してください。
理想の定期テスト対策を始めよう!
今回の記事の内容を1枚の画像にまとめてみました!
高校1年生の定期テストは、あなたの未来を変える最初のチャンスです。ライバルがまだ中学生気分でいる今こそ、圧倒的な差をつけるタイミングです。
完璧な対策は一日では身につきません。でも、今日から始めれば、次のテストでは必ず結果が変わります。3年後の自分が「あの時頑張ってよかった」と思えるよう、今すぐ行動を起こしましょう。
学習塾STRUXでは、定期テスト対策をあなたに合わせたオーダーメイドの学習計画に落とし込んでお渡ししています。自分で勉強して分からない内容は授業中に質問することもできますし、チャットで質問することもできます。
また定期テスト後のテスト直しや、苦手分野の対策にもコミット。苦手を払拭して、徐々に大学受験へと意識を向けていきませんか?興味があれば、以下のリンクから無料体験にぜひ参加してください。
*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。












